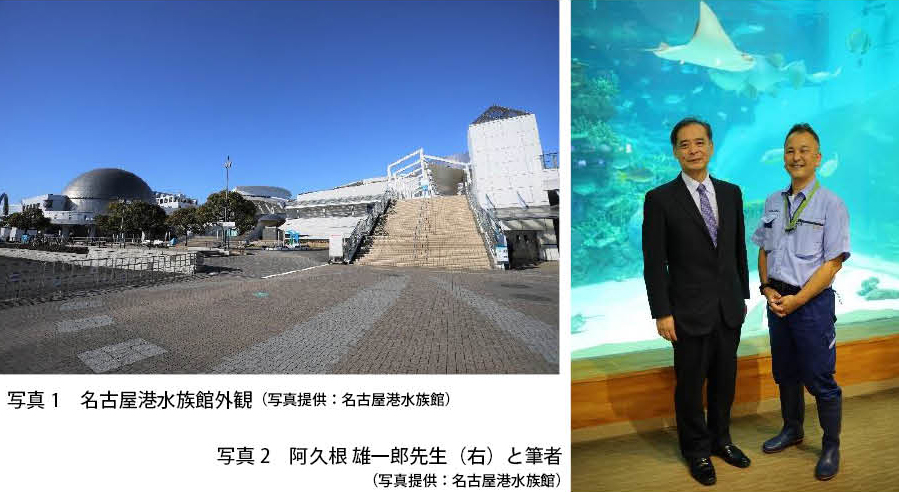HOME >> JVM NEWS 一覧 >> 個別記事
記事提供:動物医療発明研究会
インタビュアー・構成・執筆 伊藤 隆
動物医療発明研究会 広報部長/獣医師
前回は、大阪博記念公園に隣接するエキスポシティという複合商業施設内にあるNIFREL(ニフレル)の獣医師の先生にインタビューを行いました。
今回は、総水量25,000t以上、延べ面積が日本最大級の水族館である名古屋港水族館(写真1)の獣医師、阿久根雄一郎先生(写真2)、神尾高志先生、小谷由佳子先生にお話をうかがいました。
(取材日:2024年11月6日)
Q1.獣医師として名古屋港水族館の魅力や特徴を語ってください。
- 阿久根 生体展示にこだわっています。生き物たちが持つ能力や生態を引き出す演出を行っています。具体的には、イルカパフォーマンス、マイワシのトルネード、ライブコーラル水槽、ウミガメ回遊水槽などを通じて、動物の生態を見てもらえる工夫をしています。また名古屋港水族館では液浸標本、骨格標本、化石のレプリカ、3D映像など様々な展示方法を取り入れ、生体展示が難しい生き物を紹介しています。
- 神尾 展示の中で「進化の海」があります。この展示では陸地で暮らしていた哺乳類が現在の海の中で暮らす鯨へと進化する過程を紹介しています。貴重な化石のレプリカをはじめ、シャチやキタトックリクジラの実物の骨格標本など、水族館にいながら博物館のような雰囲気を体感できます。約5000万年の時の流れを感じて欲しいです。クジラの化石レプリカとして、まだ4本の脚で陸上でも生活していた初期のクジラ“パキケタス”(写真3)があります。その後、後肢は退化していき、水中生活に適した泳ぎやすい流線形の体へと進化していきます。また水族館は研究機関でもあります。名古屋港水族館ではアカウミガメの繁殖や回遊経路を解明する調査・研究、鯨類の繁殖生理・生態などの種の保存に関する研究など、様々な分野で多くの大学や研究機関と協力しながら、研究活動を進めています。
- 小谷 ウミガメについては、1995年に世界で初めて屋内施設でアカウミガメが産卵して以来、継続的に繁殖に成功しています。さらに、名古屋港水族館生まれのアカウミガメが産卵し、繁殖2世代目が誕生したことで、アカウミガメのライフサイクルを水族館内で完結させることにも成功していることが、魅力ではないかと思います。ウミガメが上陸して産卵できる砂浜があり、孵化した子ガメの個体も展示しているのが特徴的です。
Q2.イルカパフォーマンスの特徴も教えてください。
- 阿久根 イルカパフォーマンスが開催されるメインプールは日本一の大きさを誇ります(写真4)。大きさは幅60m、奥行き30mもあります。観客席は最大3000人収容でき、その向かい側には大型モニターが設置されており、イルカのジャンプが見れて大迫力があります。
Q3.メインプ―ルはとても広いですね。深さは如何でしょうか?
- 阿久根 そうです。深さもポイントです。このプールは30m×60mの楕円形平面で深さが最大で12mあります。しかも底面がすり鉢状です。是非2階の水中観覧席から見て欲しいです。
私も水中観覧席から見ましたが、イルカたちが見たことのない猛スピードで泳いでいることと、こんな深いところまで泳いでいることが良くわかりました。
Q4.南館と北館の2つの館がありますが、それぞれの特徴を教えてください。
- 阿久根 最初にできたのは球形のシアターが目印の南館で、1992年10月に開館しました。屋外のメインプールなどがある北館は9年後の2001年に11月に完成しました。南館は水族館の目の前に係留されている「南極観測船ふじ」がかつて通った航路を辿り、「日本の海」「深海ギャラリー」「赤道の海」「オーストラリアの水辺」「南極の海」の5つの水域に生息する生き物たちをその環境とともに紹介しています。
- 最初に出てくる南館の目玉は「黒潮大水槽」、約3万5000尾のマイワシが群れをなします。食べられる側の弱い存在であるマイワシですが、群れを成し、群れ全体が大きく動く時に見せる力強さは息を飲むような迫力です。群れで動くこの習性を利用したのが「マイワシのトルネード」(写真5)と名付けられたイベントです。
- また、「ウミガメ回遊水槽」も目玉です。大きなドーナッツ型の水槽です(写真6)。内部には海中の岩などが再現されており、ウミガメが隠れる場所があるなど工夫をしています。アカウミガメ、アオウミガメ、タイマイなどがゆうゆうと泳いでいます。
- 北館はシャチやベルーガといった鯨類たちが暮らしています。先程説明した巨大なメインプールがあります。イルカパフォーマンスは、縦4m、幅29mの巨大な観察窓がある北館2階の水中観覧席で見ると、ジャンプに向かう前の力強い泳ぎがよくわかります。メインプールの観客席からは、シャチの公開トレーニングも見れます。国内でシャチを飼育しているのは、名古屋港水族館、鴨川シーワールド、神戸須磨シーワールドの3か所だけです。
- 私は、北館建築・準備の時期に入社で、1994年に就職いたしました。
Q5.勤務する3人の獣医師は、どのような役割分担をされているのでしょうか?
- 阿久根 私は飼育展示第三課の課長で、ベルーガとケープペンギンの飼育と診療をまとめて担当しています。神尾先生は主にイルカやクジラなどの鯨類の診療を担当し、小谷先生はペンギンなどの鳥類やカメの診療を担当しています。
Q6.診療経験のなかで印象深いことはありますか?
- 神尾 トレーナーの方と協力し、ベルーガの皮膚疾患に対して半年以上、デブリードメントなどの治療を施し、全快しました。とてもうれしかったです。回復できたのは獣医師とトレーナ―とのチーム医療による総合力の結集によるものではないかと思います。
Q7.海獣の診療ではどのようなものを参考にするのでしょうか?
- 神尾 関連する疾病の論文検索を行って、診療の参考にしています。論文検索の中で参考となる本が見つかる場合があります。それ以外に海外の学会などに参加してその発表報告を参考にしています。学術本として参考になるものとしては、『CRC Handbook』や『Handbook of Ultrasonography in Dolphins』があります。
Q8.ウミガメの診療の特徴を教えてください。
- 小谷 ウミガメは外傷が多く、抗菌剤による治療が主となります。抗菌剤の投与量については、『Sea Turtle Health & Rehabilitation』を参考にしています。
Q9.国内でシャチを飼育しているのは3館とのことですが、その飼育や診療には特別な困難が伴うのではないでしょうか?
- 神尾 症例数が少ないので治療する際に情報が集まりにくいという苦労があります。またイルカやベルーガは陸にあげて治療をすることが比較的容易ですが、シャチは大きいので、陸にあげての治療が難しいという問題があります。オスの「アース」は体長6m、体重3.6tです(2024年11月時点)。
- エコー検査でも、シャチの体が大きすぎて手が届かないことや、皮下の脂肪組織が厚く、腹腔臓器の十分な描出ができない難しさがあります。当館では必要な時に、動物に対して陸での処置を可能にするため、昇降式の床が設置された水槽があります。これはオープン当初からあります。
- 体の大きなシャチの健康管理を安全に行うため、検査においてシャチ自らが必要な体勢を取りじっとするなどの受診動作と呼ばれる行動を形成するトレーニングも日々欠かさず行っています(写真7)。
Q10.生活環境を再現し、野生そのものの姿を伝える展示のためのこだわり、工夫を教えてください。
- 阿久根 2つの代表的な水槽について説明します。
- 1番目は、オーロラの海(ベルーガ水槽)です。ベルーガは北極圏の冷たい海に暮らしています。ベルーガが暮らす環境に合わせて水温は13~18℃に、そして日長も北極圏と同じように照明でコントロールしています。
- 2番目はペンギン水槽です。南極や周辺の島々で生活しているペンギンのために、1年を通して気温は-2℃、水温は8℃に設定されています。また、氷が定期的に落ちてくるシステムもあります。色々な種類のペンギンが飼育されています。
Q11.繁殖の取り組みでは、今までどんな成果をあげられてますか?
- 阿久根 水族館の役割の1つは種の保存に努めることです。飼育生物の生涯ライフサイクルを水族館内で完結できれば、その命を未来へとつないでいくことができます。
- 具体的な例としてバンドウイルカは、2018年に初めて人工授精で繁殖に成功しました(国内3例目)。光や水質の変化に弱いナンキョクオキアミの飼育において2000年に世界で初めて繁殖に成功しました(写真8)。
Q12.水族館の獣医師が加盟あるいは参加されている国内外の学会を教えてください。
- 神尾 国内では、日本野生動物医学会、日本獣医学会に参加しています。海外では、水棲生物を診療している獣医師の学会であるIAAAM(International Association for Aquatic Animal Medicine)に参加しています。
Q13.診療上、開発して欲しい医療器具、薬剤あるいは剤形、翻訳本、学術データなどはありますか?
- 小谷 鳥類や爬虫類のCBC(有核を検出できる)の測定できる機械を開発して欲しいです。ペンギンやウミガメに抗菌剤や抗真菌剤を投与した際の薬物の血中動態データが欲しいです。
- 神尾 4つあります。1番目は、麻酔拮抗薬のナルトレキソンを導入して欲しいです。また投与対象海獣動物が大きいので大容量サイズを希望します。2番目は、LHキットです。犬用のものをイルカの人工授精に使用するのですが、米国製のものを使用しており海外からの輸入が必要なため、容易に入手できる購入経路、あるいは日本で購入できる製品が欲しいです。3番目は、3mの内視鏡に使用できる長さの、ワイヤー鉗子をはじめとした各種鉗子が欲しいです。4番目は1回の投与量を少なくするため、注射薬や生体に悪影響が出ない範囲で高濃度のものが欲しいです。
Q14.名古屋港水族館に獣医職として就職を希望している学生へのアドバイスをお願いします。
- 阿久根 コミュニケーション能力は大事だと思います。バイトやサークルなどに参加していろいろな経験を積むことが良いと思います。また工作もできると良いと思います。水族館でいろいろなものを自分で作成する機会が多いからです。例えば内視鏡のワイヤーを自分で作成することがあります。
- 神尾 学生時代に勉強はちゃんとしていた方が良いと思います。また英語を勉強した方が良いと思います。
- 小谷 学生時代の実習は大事だと思います。またいろいろな経験をした方が良いと思います。水族館に就職するには、自動車運転免許、ダイビング、潜水士の免許を取得していた方が良いと思います。
Q15.先生方が目指すものを教えてください。
- 阿久根 動物飼育をしっかりと行い続けることです。飼育においても、獣医療においても動物をしっかり観察する目を持ち、適切な飼育管理を行っていくことです。技術の進化にもついていけるように努力していきます。
- 神尾 健康管理と研究活動を並行して行い、鯨類に対する診療技術の向上に貢献できる獣医師になりたいです。現在、罹患率/致死率が高いといわれる鯨類の呼吸器疾患を的確に診断するための、気管支鏡検査の方法・評価基準の確立を目指して研究を行っています。知り得た情報は論文報告や学会発表の形で公開しています。
Q16.国内外で参考にしたい、あるいは是非訪問してみたいと思われる水族館や動物園を教えてください。また、その水族館や動物園を選ばれた理由を教えてください。
- 阿久根 高知の桂浜水族館です。理由は面白い飼育管理やトレーニングを行っているからです。
- 小谷 沖縄美ら海水族館です。理由はウミガメのCT検査を実施しているからです。
編集後記
今回、名古屋港水族館を訪問しました。同館は、日本最大の屋外プールを備えており、シャチやベルーガなどの鯨類が主に生活している北館と名古屋港に係留されている「南極観測船ふじ」(写真9)が南極へと向かった際に通ったコースを、5つの水域から再現した南館の2館で構成されているのが、とても印象的でした。
中でも極地に生息している貴重な飼育動物として「ナンキョクオキアミ」、「エンペラーペンギン」「ベルーガ」などが見ることができます。
また、数多くの骨格標本や化石のレプリカが並ぶ「進化の海」はまさに鯨の博物館であり、鯨の進化を学べる貴重な展示もあります。
3種類のウミガメが暮らすウミガメ回遊水槽は、ウミガメの飼育を考慮した設計になっており、アカウミガメの繁殖や回遊経路を解明する調査・研究など、様々な分野で多くの大学や研究機関と協力しながら、研究活動を進めているのが特徴的ではないかと思いました。
夕方になるとライトアップされて、また名古屋港水族館の素敵な一面を楽しめます(写真10)。
動物医療発明研究会は、会員を募集しています。入会を希望される方は、「動物医療発明研究会」まで。
シリーズ「獣医師の眼から見た水族館と動物園の魅力」
- (1) 四国水族館
- (2) 仙台うみの杜水族館
- (3) NIPPURA株式会社-前編
- (4) NIPPURA株式会社-後編
- (5) átoa
- (6) アドベンチャーワールド
- (7) AOAO SAPPORO
- (8) 沖縄美ら海水族館-前編
- (9) 沖縄美ら海水族館-後編
- (10) 大成建設株式会社
- (11) 新江ノ島水族館-前編
- (12) 新江ノ島水族館-後編
- (13) 旭川市旭山動物園編
- (14) 猛禽類医学研究所-前編
- (15) 猛禽類医学研究所-後編
- (16) NIFREL