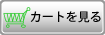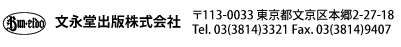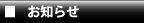
HOME >> 書 評 >> 農学
『動物の衛生 第2版』
2020年3月発行・A5判・312頁・定価 4,840円(税込)
『動物の衛生 第2版』に見えた動物衛生学領域の動向-遅ればせながらの書籍紹介を兼ね
動物と人と環境の健全性を一つのものと捉える理念「ワンヘルス」を大手文化センターで講ずる機会を得た(朝日カルチャーセンター 新宿教室「人・動物・環境から学ぶ感染症サバイバル」)。その講演の資料(底本と呼ぶ)となる北海道獣医師会誌に投稿した「“ワンヘルス/保全医学”を公共知とするために(その1~7).」の初校を読んでいる。
ところが、ここに来て動物衛生学(あるいは獣医衛生学・家畜衛生学等)側の言及が少なく慌てた。この科目は(も?)獣医大学の学部教育を受けた頃(1984年、積み上げ修士2期)には、公衆衛生学との区別すら出来ていなかった程の鬼門。だが、私だけではなく獣医大学のベテラン教員すら家畜保健衛生所のことを「家畜保健所」といって憚らない時代であった。言うまでもないが家畜保健衛生所は獣医衛生学の拠点。他人のことはどうでも良い。私は前述のごとく当該領域の最新知見を確認しないといけない!それも迅速に!幸い手元にあった『動物の衛生 第2版』はその条件を完全に満たした。積読状態であったこの書籍は新品同様状態であったが、約48時間で読み込み書き込みと下線ですっかり年季が入ったモノとなった。2001年に発行された初版『動物の衛生』で私は分担執筆(寄生虫・衛生動物化した野生動物の箇所)をしている。普通ならば情報がアップデートされた方を残し旧本は自動廃棄。だが、自身が関わったのでギリギリで思い留まった。でも全部は場所を取る。アップデート頁のみ差し替えすることにした。結果的に熟読し、加えて20年間で刷新された箇所も把握出来た。
第2版では「ワンヘルス」がコラム的に解説され(243頁)、参考になった。マンハッタン原則12条項がきれいに五つにまとめられ、これは前述の底本(浅川 2025/2026)執筆時に知りたかった(積読した奴が悪いのだが…)。特に目を引いたのは動物福祉(アニマルウェルフェア)関連の新規追加。その章のみならず、細かいことが気になる鳥好きは「強制換羽」が新語「換羽誘導」に変換され、かつストレスがかかる事実が明記されていた(13頁)。このように既存項目では多数箇所で動物福祉に配慮された記述がなされ、とても参考になった。
ただし、こういった新語を知らない古参は索引にそれが未掲載なので若手が宣う「換羽誘導」をきいても「?」的状態になる。幸い、索引当該箇所(287頁)の左隣にその新語を入れ込むだけで話は済むので(大きく影響は与えない形で)、追加可能だろう。ただし頁数には制限がある。例えば索引は、初版に比して余白・行間を狭め押し込めるなど、編集の苦労がみてとれる。またこのため、第2版では初版に比べて画像が少ないのかもしれない。一方で、有毒植物のカラー口絵は素晴らしい。初版『動物の衛生』で私が分担執筆した箇所では寄生虫や衛生動物化した野生動物の写真や生活史の図等を贅沢に掲載させて頂いた。スマホが普通となった当世、キーワードから検索すれば、いくらでも画像情報は得られる。そのためにも索引はきちんと網羅して頂きたい。
第2版の著者陣の中に、私のゼミ・研究施設(医動物・野生動物医学センター)で卒論研究した小林朋子先生(東京農業大学)の氏名があった。「農薬および動物用医薬品による中毒」(212~215頁)を執筆されている。小林先生は在学中に筆頭著者で国際誌に掲載された程の卓越した才能のある方で(Kobayashi et al. 2011)、卒業後、京都大学大学院へ進学しウイルス学で学位取得、現在も牛白血病ウイルス等で優れた多数業績をあげられている。小林先生には、改訂の際には追加検討して欲しい項目がある。
まず、有機リン系ではシアノフォスの解説が欲しい。第2版では初版と異なり、馬や犬、猫、さらに(先程の換羽で触れたように)家禽等も追加されている。シアノフォスは殺鳥剤としてもかなり有名な殺虫剤だ(いきもののわ「野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第1回】ある朝カラスの死体が累々:殺鳥剤という怖いワード」)。しかも、カラス等を勝手に殺す事例が全国各地で多発している(違法)。
もう一つは、家畜でも頻用される非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)のジクロフェナクNa(商品名「ボルタレン」)の記載である。これは鳥類に毒性がある。日本ではこの医薬品による野鳥大量死等は未報告だが、人の鎮痛剤として市販品が大量に流通しており、そのうち顕在化するだろう。
私は野生動物の法獣医学にも携わっているが(2021a)、その法獣医学的なことと関連する記述として264頁に死因解明の予防医学的重要性が記されていた。次の版では「法獣医学」という語も使用頂ければと思う。
ワンヘルスで肝心なのは何としても感染症系。まず、「監視伝染病」の節(160頁以降)には総論的説明が要るだろう。初版時に口蹄疫とBSEが発生、その後は高病原性鳥インフルエンザと豚熱が次々に起こり、まさに感染症の時代に突入した感がある。家畜伝染病予防法で規定される監視伝染病である「家畜伝染病」と「届出伝染病」、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に関わる動物の感染症、「狂犬病予防法」で規定される狂犬病など、「新興感染症」や「越境性動物感染症」を含めたその他に届出が必要な感染症の関係性は、図を用いて示すことが初学者にとっては親切だろう。これに比べればマイナーだが、各論枚挙は概して真菌が弱い。現状では仕方がないとは思うが、たとえば、みつばちのノゼマ病は届出伝染病で大事だ。ちなみにこの病原体は微胞子虫類で真菌とされるのが普通である。かつては原虫とされたが…(浅川 2024)。それと牛の乳房炎で新興的な病原体プロトテカ(原生生物のクロレラ)の収まるような場所がない。細菌を含め、先程の真菌や多様な寄生虫・衛生動物、さらに生物全ての系統を一目、一瞬に見渡せるような系統樹がウェブで示されたら便利だろう。感染症やワンヘルス理解ではこういったツールが必要で、そのため拙著(浅川 2021a, 2021b)ではそれぞれ掲載しているので、どうか、参照頂きたい。
畜舎・放牧地における鳥獣性の衛生動物については展示動物の節で記され(264頁)ているが、これは家畜家禽の飼育施設でも同様なので追加説明が要るだろう。初版のころはOSO 18のようなヒグマはいなかったが、今日、家畜への直接的な被害をもたらす衛生動物としての哺乳類の存在が外来種を含め普通になりつつある。第2版での野生動物では、当然、ジビエ処理に関し大変充実している(229頁)。なお一点、「と畜検査の対象にはならない」という記述だが野放し状態と誤解されないため、野生鳥獣は食品衛生法上、食肉処理業許可施設での解体等が謳われていたと思うので確認、必要なら追加を願いたい。
冒頭の「朝日カルチャーセンター」の筆者担当の講義については、JVM NEWS「【寄稿】文化としての獣医学!を再び」(2025-09-08)をご参考下さい。
引用文献
浅川満彦.2021a.野生動物の法獣医学-もの言わぬ死体の叫び,地人書館,254pp.
浅川満彦.2021b.野生動物医学への挑戦-寄生虫・感染症・ワンヘルス,東京大学出版会,196pp.
浅川満彦.2024.真菌としての微胞子虫およびその疾病に関する情報整理.北獣会誌,68: 391-396.
浅川満彦.2025/2026. “ワンヘルス/保全医学”を公共知とするために(その1~7).北獣会誌,68/69: 印刷中.
Kobayashi T, Kanai Y, Oku Y, Matoba Y, Katakura K, Asakawa M. 2011. Morphological and genetic characterization of sylvatic isolates of Trichinella T9 obtained from feral raccoons (Procyon lotor). Nematological Research, 41: 27-29.
2025年9月 掲載
『動物の飼料 第2版』
2017年10月発行・A5判・320頁・定価 4,840円(税込)
『動物の飼料 第2版』が文永堂出版より上梓された。A5判サイズ,約300頁のコンパクトな書籍ながら,その内容は,畜産農家はもとより研究者そして畜産学を学ぶ学生にとって知りたいことが網羅された,まさに,痒い所に手が届く解説書である。
本書のタイトル『動物の飼料』からは,さまざまな飼料の栄養成分や給与上の注意点に関する日本標準飼料成分表の解説書のような内容を連想したが,それは全く違う。初版の序に記されている通り「望ましい飼料とは嗜好性,利便性がよく,栄養素に富み,安全なもの」という,飼料が備えるべき基本的条件の説明から始まり,動物ごとの給与飼料の特徴,栄養価の評価方法,栄養特性,飼料の加工方法,さらに,今日の我が国の畜産が直面する課題,すなわち食品循環資源や農業生産副産物を原料とする飼料資材,そして家畜の健康と食の安全に関連する飼料由来の有害物質など,飼料に関係する多面的な情報が平易,かつ,明快に解説されている。
例えば,『飼料とは』では,飼料の条件として以下のように説明されている。1)嗜好性がよい~動物が食べてくれなければエサにはなりえないし,2)栄養素を含む~栄養がなければエサではない。また,3)消化される~当然ながら,消化吸収されなければエサではないし,4)利用される~栄養成分のバランスが適正でなければ体内でうまく利用できない。さらには,安全(動物と人)であることは言うまでもなく,取り扱いやすく,経済的で家畜の健康および環境にも優しいことと説明されている。
また,『飼料の加工および製造』においても,単なる加工方法の説明にとどまらず,上記の飼料に求められる条件に沿って,加工の目的として,嗜好性向上,消化管内での利用性向上,そして取り扱いのしやすさや貯蔵性向上など飼料が備えるべき本質的な要件を説明したうえで,個々の飼料について,加工・貯蔵方法の利点や欠点を解説するなど,初心者にとっては格好の入門書であり,実務者にとってはあらためて自身の飼料調製の適否を見直すきっかけになる書でもある。
『飼料の安全性』に関しては,食の安全性確保が求められる中,畜産物を介して人に健康被害をもたらす物質(BSEプリオン,アフラトキシンなど)から始まり,病原体・カビ毒・重金属汚染,さらに動物の微量元素欠乏症や過剰症,そして抗菌性飼料添加剤および関連法令など,極めて幅広い視点から飼料関連情報がコンパクトに解説されている。
なお,第2章以降には,各章に練習問題が配されており,読者自身で理解度を確認できるようになっている。動物の飼料に関わる者は,是非手元に置いておきたい一書である。
「獣医畜産新報」2018年2月号 掲載
『動物の飼育管理』
2017年8月発行・A5判・336頁・定価 4,840円(税込)
本書は1991年に出版された『家畜の管理』の後継本である。『家畜の管理』出版当時の畜産界は生産性の追求が最大のテーマであった。しかし,国際獣疫事務局(OIE:現・World Organisation for Animal Health)が2004年に採択した“動物福祉の原則に関する指針”において,“畜産動物の福祉の改善は生産性と食の安全を改善する可能性があり,したがって経済的な利益を生み出すことが可能である”と宣言されており,今日では動物(家畜)福祉が家畜飼育管理上の最大テーマとなってきている。そのような時代の流れの中での本書の登場は実にタイムリーである。
前半では気候への対応や畜舎構造などの環境管理,個体維持行動や社会行動,繁殖行動などの動物行動と飼育者や設備の関係,動物福祉の歴史・原則・評価法や環境エンリッチメント,消毒や防疫などの家畜衛生の総論が展開され,さらに現在大きな問題となっている畜産廃棄物と環境対策が具体的に記載されている。これらの記載は動物福祉をベースにしながら,法律関係にまで及んでいる。
後半では動物毎の管理が解説されている。取り上げられている動物は,牛・馬・豚・山羊・めん羊・鶏などの家畜にとどまらず,犬・猫・実験動物,さらには展示動物にまで及ぶ。動物毎に,その一生の概説から始まり,発育ステージ毎の基本的な飼養管理方法,畜舎や設備の解説,動物の行動と飼養者の関係など,今までの家畜管理関係の教科書とは異なった構成になっている。
本書は写真や図を多用して動物の飼育管理のポイントが非常にわかりやすくコンパクトにまとめられており,畜産系および獣医系の生徒・学生の教科書として必要十分条件を満たしている。さらに,現在動物を飼っている方々の参考書として,また,今から新たに動物を飼育しようとしている一般の方々の入門書としても最適な構成となっている。
「獣医畜産新報」2018年1月号 掲載
『畜産物利用学』
2011年1月発行・オールカラー、A5判・320頁・定価 5,280円(税込)
書名が『畜産物利用学』とあったので、硬い教科書として読み始めたが、一気に面白く読むことができた。本書の読者を畜産物の科学を基礎から学ぼうとする学生と技術者を対象として書かれたとある。しかし、畜産の専門以外の人たちが読んでも十分興味をそそる本である。それは、内容が最新の情報を組み込み、同時に簡潔な文章と分かりやすいカラー写真や図・表を随所に組み込んでいることによるものであり、これは、編集代表者の齋藤忠夫氏の意向が強く反映されたことにあると考える。
本書は、第1章「乳の科学」、第2章「肉の科学」、そして第3章「卵の科学」と日本の畜産物の利用動向と合わせたページ比率となっており、それぞれには、基礎と検査、製造技術、機能、そして健康への寄与とが具体的に記載されている。
その一端を紹介すると、第1章の7.「牛乳と発酵乳製品の機能性と健康への寄与」では、牛乳のタンパク質アミノ酸スコアは100と理想的であること、それらのアミノ酸が牛乳のカルシウムの吸収を促進させたり、血圧のホメオスタシスを担っていること、また、日常の牛乳摂取量が多い人ほど、体脂肪率が低くなっていることをカラーの図・表を基に説明している。第2章の8.2)「日本の食肉生産と消費動向」では、日本の食肉生産量は260万トン程度であり、そのほとんどが輸入に頼っていること、また、日本国民1人当たりの食肉消費量は世界の中では81番目と韓国(64番)や中国(68番)よりも少ないとするデータが興味深かった。その理由については言及していなかったが、健康を志向していく国民としては良いことのように思われた。第3章の9.3)「日本の鶏卵生産と消費および流通の特徴」では、鶏卵は新鮮卵需要が多く、非貿易商品であること、わが国の鶏卵消費量は量的規模において世界のトップクラスであること、しかし米国からの輸入飼料穀物によって支えられていることから大型タンカーの入港出来る地帯に主要な鶏卵産地が発達してきたことが述べられている。以上のように各章ごとに基礎科学と併せて日本の畜産物の現況を分かりやすく記載されてある。
さらに、最後には「最近のトピックスと諸問題」と題して、日本の畜産物の利用に関しての話題が分かりやすく載せてある。例えば、日本人とくに加齢に伴った「乳糖不耐症」の人にはヨーグルトやチーズの利用を進めている箇所や、卵のコレステロールの摂取が心臓病のリスクを高めるとした説は誤りであること、などを指摘している。
以上のように非常に理解しやすい構成となっているので、教科書としてだけでなく、畜産物を食品として扱っている料理研究家や栄養士の人たちにも読んで貰いたい1冊である。
「獣医畜産新報」2012年1月号 掲載
『“家畜”のサイエンス』
2002年1月発行・A5判・202頁・定価 3,740円(税込)
本書は家畜の動物学的側面に焦点を絞った読み物である。著者の一人は、過去に『畜産学』と『新版畜産学』の2冊を編集・執筆した経験に基づき、今回は畜産学の教科書ではなく啓蒙書として体系的記述を避け、話題形式とし各話題を見開き頁に納めることによって読みやすさを狙ったと序文で述べている。軽妙な装丁と画期的な企てを歓迎する。
評者は、この本を学生の副読本、あるいは一般の読者の啓蒙書として位置付け、話題の選択とそのタイトルがぴたりと記述内容を予測させるか、内容記述が取っ付きやすいか、すなわちよく消化されて、「お話し化」されているかの視点で通読してみた。読者サービスの新知見も折り込み、全体として著者の試みは概ね成功とみてよかろう。しかし、この企てが一般の書物にくらべていかに困難であるかも感じさせる。まず話題の選択は全般に適切と思われ、話題のタイトルも概ね可とするが、一部に包括的抽象的きらいのあるものがあった。記述の細部にわたって見ると、話題の抽出分野により、読みやすさの成功度に高低があることが伺われる。育種分野では、話題のタイトルが砕けている割に説明の内容が読者の生活用語に関係が薄いためか、お話し化に苦労の跡が伺われる。その点家畜栄養・畜産物分野では、日常生活用語に根ざすため、最もお話し化に成功している。生態・行動学分野もかなりに読み物化に成功している。
読者は啓蒙書として楽しく通読できるであろう。是非ご一読また学生諸君への推薦を提案する。
「獣医畜産新報」2002年5月号 掲載
『動物生産生命工学』
1996年1月発行・A5判・232頁・定価 4,400円(税込)
今世紀において最も発展し、さらに人類の生存に大きく影響するようになったサイエンスには二つある。生命現象を遺伝子のことばで解釈できるようにした分子生物学とコンピュータに代表される電子情報学である。このことは衆目の一致するところであろう。本書はこれらの分野の成果を理念としても、実際としても動物生産(畜産)学の中に位置づけようとした意欲的な教科書である。
動物生産学の対象とする動物が、近年、家畜(家禽)や実験動物のみならず、野生動物にまで広がってきているが、何を目的としてこれらの生産を行うかについても多様性がでてきている。遺伝子改変によるモデル動物の新規開発、希少動物種の保護、野生動物の管理を通した環境保全などが近年新たに動物生産学に期待される分野となってきているが、やはり食糧としての家畜(家禽)の生産が動物生産学の主目的であるのは変わらないであろう。食材としての畜産物は将来的には、栄養価の高い食品あるいは嗜好品としてよりも、「機能性食品」としての比重が高まるとも考えられるが、本書では、長期的展望として、さらに大胆に「食品というよりもむしろ医薬品としての生産」に動物生産の意義を求めている。
地球上の資源の限界が認識され、地球の人口の定員が議論されている。地球の定員論を前提として、多くの研究者により、人口増加の抑制、太陽エネルギーの利用効率の改善、食物連鎖の低位のものの食糧化などが提案され、その具体化が図られてきている。一部で論議されている食物連鎖の低位のものの食糧化は現在の動物生産学に対して深刻な課題を提起している。食物連鎖が上位へ行くほどエネルギーの損失が激しくなることを意識した論議であるが、このような論調が力を持てば家畜はエネルギー浪費型生産物として認識されるようになる。家畜の生産を維持するには、食物連鎖が上位へ行くほど大きくロスして行くエネルギーを補うだけの価値を家畜に見いだす必要がある。このような中で「動物生産を医薬品の生産」とする編集者の考えは一つの答えにもなるだろう。
執筆は農学分野にとどまらず、工学、医学、理学分野の第一線の研究者によって書かれているが、編集者の理念によって内容が統御され、目次をみるだけで従来の畜産学が新しい時代を迎えたことが実感できる。
第1章では動物生産生命工学とはなんであるかについて編集者の考えが述べられている。「動物生産(畜産)は、本質的にはエネルギーや物質の転換作業のことであり、その転換器として動物を利用しているに過ぎない」との考えをベースにして、動物生産業の継続、発展のため、今後数年をにらんだ短期的展望のみならず、「数十年をにらんだ中・長期的展望にたった新たな技術開発」が必要であると力説している。そして「動物生産の未来設計図」に必要と思われる「質的制御技術」と「量的制御技術」の構築の必要性を説いている。
第2章では「質的制御技術」の基礎が取り上げられている。動物生産物が将来的には食品というより医薬品として機能するようになる可能性を踏まえ、そのための動物生産技術の開発に寄与する基礎学としての遺伝子工学、発生工学、分子生物学について説明されている。動物細胞と遺伝子、遺伝子工学の基礎技術、培養動物細胞を用いた物質生産、局所的生体組織を用いた物質生産系、動物個体(トランスジェニック動物)を用いた物質生産系などが記述されている。
第3章では「質的制御技術」の応用と実際について述べられている。とくに培養細胞を用いた人工皮膚、人工血管、人工肝臓などの作製、遺伝子改変による昆虫や泌乳動物の有用物質生産、ウシやニワトリの胚操作や遺伝子導入、移植用代替動物の作出について概説されている。
第4章では「量的制御技術」について記述されている。今後数年間のうちに生産物の価値や生産方法が大幅に変わることはないと予想される。このような中でも、効率的生産系の構築を目指して、コンピュータシミュレーションを駆使したシステム分析が重要であると説明している。システム分析の実際、ニワトリ産卵モデルによる成績予測等の実際例についても記述されている。
3~5頁ごとに1頁を割き、内容を象徴的に示すトピック的な話題も記述されている。「バイオテクノロジーに託す夢」「スーパーヒツジバイオリアクター」など専門外の人達にも親しめるような配慮がなされている。
本書は遺伝子工学、発生工学あるいは細胞工学を含めた分子生物学の発展を動物生産分野の問題意識にたって再構築し、統合を図った書として高く評価されるだろう。読者層を広げ、動物生産学の案内書として広く読まれることを期待する。また、本書をもとに、次世代の動物産業のあり方について論議が湧くことも期待できる。いずれにせよ、動物生産の研究、教育の方向に一石を投じた書であり、学生教育、社会人教育に広く使われることを希望する。
「獣医畜産新報」1996年12月号 掲載
『動物生産学概論』
1996年1月発行・A5判・382頁・定価 4,400円(税込)
近年の科学技術の進歩は目ざましいものがあり、ことに遺伝子関連の学問の進展やそれに伴う学際領域の進歩には目をみはるものがある。
本書はこれらの学問分野の進展の現状をふまえて刊行されたもので、これまでの縦割の学問体系、すなわち畜産学、水産学などの境をとりはらって、遺伝子を構成する塩基配列を軸に、陸生動物および水生動物などの有用な資源動物を同じ生物としての視点から、横断的、統一的に理解し、生産学としてまとめたもので、全く新しい体系に基づくテキストである。そして、その方向は全国の農学系大学の学科再編の方向とも合致したものであって、誠に時宜にかなったものであるといえる。
20世紀後半の科学技術の著しい発展は人類に多大の恩恵を与えたが、一方21世紀に向けて、食糧問題をはじめ環境問題など、われわれの周囲には現在も解決すべき大きな課題が山積している。本書はこれらの問題をも視点に入れて、総合的な観点から書かれたもので、まさに画期的な意味を持つ教科書といえよう。
執筆は陸生動物および水生動物のそれぞれの分野の第一人者によって担当されており、しかも編集者の意図によって、これらがバラバラにではなく、それぞれが関連づけられ、さらに地球環境保全との関連も視野に入れて一定の思想のもとに統一され、大変調和された形であらわされている。第Ⅰ章では動物生産学の概念が述べられ、その中で動物生産と農業との関連、動物生産の重要性と課題、動物生産がもたらす植生の破壊や野生動物社会への攪乱の問題などが記述されている。第Ⅱ章では動物資源の分類と種類が、第Ⅲ、第Ⅳ、第Ⅴ章では動物生産の形態、環境、技術が、第Ⅵ章では生産物とその品質の問題が記述されている。第Ⅶ章では近年進展の著しい動物生産におけるバイオテクノロジーの領域がやさしく紹介されており、大変理解し易い。さらに、最終章の第Ⅷ章では動物資源の管理問題が記述されている。
本書は生物生産学系、生物資源学系、農学系の大学における動物生産学のテキストとして刊行されたもので、その目的である広い視野を持つ学生を育てるのに申し分のない教科書であるばかりでなく、現在すでに社会で活躍している人々にとっても大変有益な内容であり、座右に備えて活用すべき良書として推奨する。
「獣医畜産新報」1996年9月号 掲載