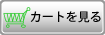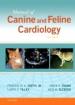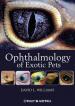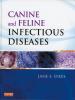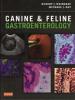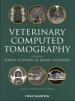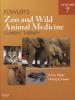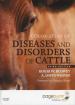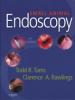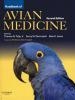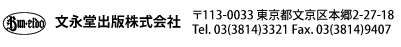HOME >> 書 評 >> 海外出版社刊 洋書
『Atlas of Small Animal Wound Management and Reconstructive Surgery, 5th Edition』
2025年・Wiley-Blackwell発行・¥42,790(税込)
本書は世界中の獣医師・外科医に長年愛用されてきたアトラスの最新版であり、小動物の再建外科手技を網羅した唯一無二の専門書である。著者 Michael M. Pavletic 氏は、ACVS(米国獣医外科専門医協会)の外科専門医として臨床の第一線に立ちながら、1990年に刊行した初版(約400頁)により獣医再建外科を体系化し、以後自らの手で改訂を重ねてきたこの分野の第一人者である。2018年の第4版(800頁超)以来7年ぶりに発刊された第5版は1000頁を超える大著となり、新たに30を超える術式が写真とイラストを用いて解説されている。
本書に関してはいくつかの先入観を解いておきたい。第一に「分厚い専門書は専門家向けで現場にはそぐわない」という思い込みである。実際には全体の大半が術式Plate(見開き2頁の構成で、左に簡潔な解説、右にカラーイラスト)とそれを補う症例写真から成り、版を重ねるたびに視覚的理解のしやすさが向上している。
第二に「読む暇がなければ本棚の飾りになる」という懸念であるが、195枚に及ぶ Plate をめくるのは楽しく、イメージは容易に記憶に残る。必要なときに該当箇所を再読すれば、即座に臨床に役立つテキストになるはずである。
第三に「分厚い本は電子書籍の方が便利」という考え方も注意すべきである。アトラスの強みは、ページを繰りながら大量の図版を一度に視覚に取り込める点にあり、この点は紙媒体のほうが優れている。
最後に「旧版でも情報は十分なので最新版は不要」という誤解である。評者も長年第3版(2010年、680頁)を活用してきたが、フルカラー化された最新版を一読して、その視認性、症例写真の豊富さ、新しい実践手技の多さに驚かされ、最新版を手元におく意義を痛感した。
本書の利用にあたっては注意点もある。美しいイラストを見るとどの方法も成功しそうに見えるが、実際の症例では成功率に差があり、本書ではそれをとらえにくい。しかし、Plate以外の文章パートのカラーBoxにおいて著者自身が問題点を強調しており、そこが極めて参考になる。私見が交えられている部分もあるが、実践家ならではの説得力があり、同時に最新文献も網羅されていて信頼性は高い。
最新版では新しい皮弁法に加え、臨床家が苦慮する口腔、鼻、耳、眼、包皮、肛門などの天然孔領域の再建手技が数多く追加された。今日では自然外傷よりも、これら部位の腫瘍切除後の欠損再建に直面する機会が増えており、本シリーズはそうした臨床現場の要望に応えて進化してきたことが実感できる。その完成形に近づいた最新版は、一次・二次診療を問わず、すべての獣医師に必携の「バイブル」と呼ぶにふさわしい名著である。
2025年9月 掲載
『Atlas of Small Animal Ultrasonography, 3rd Edition』
2025年・Wiley-Blackwell発行・¥38,500(税込)
「断層画像」といえば最初にCTやMRI検査を思い浮かべる人は少なくないと思いますが、忘れてはいけないのが超音波検査です。近年、我が国の小動物臨床においてはCTやMRI検査が急速に浸透していますが、X線、超音波検査、CT、MRIといった全ての画像診断機器の操作や読影に精通する画像診断を専門とした小動物臨床獣医師は極めて少数です。種々の画像診断機器を普段から扱い、各々の特性を知っている立場の獣医師が感じている共通意見ですが、多くの獣医師が抱くCT、MRI検査に対する期待は過大すぎますし、日常的に使われているX線や超音波検査は過小評価されすぎています。
例えば消化管などの管腔臓器を思い浮かべて下さい。粘膜、粘膜下組織、筋層、漿膜といった組織学的レベルまで断層で画像化できるのは超音波だけです。そして被曝することなく病変と針先の軌跡を確認しながら生検を行うことができるのも超音波にしかない特性です。より微小で詳細な病変の違いをリアルタイムに写し出す性能は身近にあります。超音波診断装置を自在に扱って様々な部位が見られるようになり、画像所見から的確でより具体的な鑑別診断が考えられるようになり、自在に超音波ガイド下生検ができれば、来院するほとんどの症例は今よりも自信を持って、次への筋道をたてられるようになります。自身がアップデートを行えば、CTを持っていればと思うことはほとんどなくなるはずなのです。
高画質で典型的な画像をふんだんに使用し解説される本書の特徴は初版時から変わらず継承され、最新の知見が所々で追加されています。また、CTや豊富なイラストが追加補足されることで、より超音波の断層画像が理解できるように改定されています。超音波で検査することが少ない四肢骨格、診断のみならず局所麻酔にも重要な末梢神経も詳細に取り上げられています。また、近年、救急救命時において胸腹部の緊急性の高い疾患を除外または発見することを目的に、限定した数か所のスキャンのみで診断していくFASTと呼ばれる超音波検査法が提唱されましたが、これは画像診断に精通していない救急医においても見落としなく診断するための簡易的な診断法であるため、より画像診断に精通した獣医師が行う検査法であるPOCUSの章が新しく追加され、日常の超音波診断においても非常に参考になります。
本書は最良の超音波診断学専門書の1つで、他の書籍よりも画像が豊富で、理路整然とした簡潔な解説が特徴です。全身の正常な状態から各種疾患までが網羅されていますので超音波診断の参考書として最初に購入して頂きたいお薦めのテキストです。
2025年8月 掲載
『Canine and Feline Respiratory Medicine, 3rd Edition』
2025年・Wiley-Blackwell発行・¥24,420(税込)
Dr. Lynelle Johnsonは動物呼吸器学の世界的権威であり、これまで多くの論文および著書を執筆しています。私も過去にDr. Johnsonの講演を聴き、その見識の深さや経験の多さについて驚き、感銘を受けたことを思い出します。
昨今、日本国内においても動物呼吸器学が少しずつ発展しています。このタイミングでの本書の発売は日本の獣医師にとっても有益であり、多くの獣医師が手に取るべき一冊でしょう。今回でthird editionとなり、新しい論文が引用されることによってアップデートされた内容になっています。
章の構成は、病状の局在の章にはじまり、診断の章、治療の章、そして各呼吸器疾患の章へと展開されます。治療については、単に薬剤の記載だけではなく、我々が日常的に実施しているネブライザーについても解説され、その疑問が解消されます。呼吸器感染症に対する抗菌剤は薬用量とともに表になっており、一目で確認ができます(p.49~)。
鼻腔内疾患、気道(気管・気管支)、肺実質、縦隔疾患については、とても詳細に記載されています。
また本書の特長と言えると思いますが、身体診察については実に丁寧に触れられています。私も呼吸器診療をしていく中で各疾患のシグナルメントを捉えることを重視しており、そこから各種画像診断に繋げていくようにしています。
気管支鏡は内視鏡画像とともに解説され(p.35~)、また気管支肺胞洗浄(BAL)についても説明されているため、日頃の診療の実際に役立ちます。Clinical caseとして実症例の記載があり、より理解しやすい工夫がなされています。
病態の解説についても触れておきます。多くの画像(特にCTや内視鏡画像)により、文章だけではイメージしにくい病態を把握しやすくなっています。また一般的な病態に加えて、寄生虫疾患など比較的まれな疾患についての解説もあります。
これから呼吸器診療を始めたい獣医師、すでに呼吸器診療を専科として行っている獣医師と様々なレベルの獣医師に参考にしていただきたい書籍です。ぜひ手に取ってご覧ください。
2025年5月 掲載
『Manual of Clinical Procedures in Pet Birds』
2025年・Wiley-Blackwell発行・¥13,640(税込)
米国の鳥とエキゾチック動物専門医による「ペットバードの臨床手技マニュアル」である。手に取りやすいコンパクトな版型だが、鳥診療に必要な項目を網羅している。全24章の目次は、ホームページ(Wiley-Blackwellまたは文永堂出版)を参照されたいが、いくつかピックアップすると、「保定」「採血」「注射」などの基本的な手技に始まり、「眼科検査」「鼻腔洗浄」「総排泄腔内視鏡検査」「腹腔穿刺」「ネブライザー」「卵塞処置」「循環器系検査」「輸血」「輸液療法」「不動化」などの項目が並ぶ。さらに、「気嚢挿管」では、気管挿管が困難な症例において気嚢を介して酸素吸入や吸入麻酔を行う救急処置が述べられており、鳥ならではのアプローチ方法に気づかされる。「心肺停止の蘇生救急」からは、心肺停止した鳥であっても適切な処置と訓練されたスタッフが揃えば、蘇生も一定の確率で可能であることが分かる。加えて、本邦ではまだ触れられることが少ない「安楽死」の章では、成鳥はもちろん、孵卵途中の胚に対する処置方法にまで言及していることに驚かされる。とにかく、保定用タオルの色に気を使う、声をかけながら鳥に接近する、など鳥にストレスをかけない診療心得が全編にわたり貫かれている。
各章は、処置の目的、準備する器具道具類、手技の手順、処置におけるコツや注意事項、参考文献などで構成されている。何より、簡潔な説明文と箇条書き、そして番号を振った処置手順でシンプルに記述されているため、長い英文には二の足を踏みがちな評者でも読みたい箇所に瞬時にたどり着くことができ、内容も理解しやすかった。図や表も多用されており、ほぼ全章でヨウムなどをモデルにしたカラー写真が掲載されている。また、小型種から大型種、あるいは種や体重ごとに、適切な器具類のサイズ、投薬量、強制給餌量や頻度、救急救命投薬量などが表にまとめられている。随所に挿入されたイラストは手描き感があふれており、著者の「伝えたい」という気持ちがにじみ出る。末尾には、参考書や雑誌、ウェブサイト、そしてエキゾチック獣医師によるフォーラム(Exotic DVM Forum)が紹介されているので、知見を深める参考になるだろう。
書籍の購入特典として動画をウェブで見ることができるのだが、原書の編集不備もあってサイトへのアクセス方法やパスワードが分かり難い*。ただ、基本的な手技の動画なので、日常的に鳥の診療をしている獣医師にはあまり価値がないかもしれない。
本邦にも日本人専門医によって書かれた優れた鳥の獣医学書があるが、多くは小型の鳥が主な対象であろう。小型から大型のペットバードまでカバーし、様々な診療手技が1冊にまとまった本書は、ペットバードに限らず様々な鳥類に応用できそうである。
*動画を見る手順:先ず、xxiページにあるURLにアクセス(Googleがアクセスしやすい)
スマートフォン☞直接Password挿入ページが開く
PC☞ページの一番下 Extraの太字URLをクリックすればPassword挿入欄が現れる
Passwordは、本書31ページ 上の図の最後の単語。
2025年4月 掲載
『Techniques in Small Animal Soft Tissue, Orthopedic, and Ophthalmic Surgery』
2024年・Wiley-Blackwell発行・¥25,630(税込)
今回、『Techniques in Small Animal Soft Tissue, Orthopedic, and Ophthalmic Surgery』の書評を依頼され、早速パラパラと読んでみて驚きました。自分がいつか書きまとめたいと強く思っていた内容でした。
一般開業医は日々様々な外科症例に遭遇します。手に負えない症例だと判断しても、その全てを二次診療施設へ紹介するのは、簡単ではありません。
一般開業医と専門医との大きな違いは、同じ症例の手術を毎日は行わないことです。同様の手術を1週間に1回は実施していない限り、手術に向かう状態はリセットされたものと言えます。
この参考書では眼科、軟部外科から整形外科へと多くの症例が記載されています。30数名の著名な先生方が数年かけて作成したとありました。やはりこれだけのボリューム(672頁)の本を発刊するまでには、多大な努力が必要なのが手に取るように実感できます。
記載されている症例のほとんどが、日々の診療の中で私が出会う症例でした。評者は殆どの症例の手術を自分自身で実施していますが、やはり術前に参考書で確認しておくことが重要です。多くの経験があっても術前の確認は必須です。
医療と比べると獣医療はまだまだ歴史も浅いのですが、多くの有能な獣医師が完全な術法を目指して改善を積み上げています。そのため、同様の手術であっても、術者によって手法が微妙に異なることになります。本参考書に記載された各項目の術式を読んでいくと、「成程、この様な手法をとれば早期治癒を目指すことができるのか」という手本もあり、また多少のその後の変化もあるという手法もあります。といっても想定内のもので、問題があるというものではありません。
日本では滅多に見ることのない地域性のある症例も載っています。例えば、Steatoma/Choesteaoma耳性真珠腫(105頁に掲載)で、日本では殆ど見ることがない症例です。評者は以前、アメリカの動物病院での研修で見る機会があり、驚いて早速、日本の著名な先生に連絡して教えを乞いた覚えがあります。世界中には知らない病気が多種多様にあります。そういった症例のことを知ることができるのも、この参考書の利点です。
とは言っても、やはり皆さんが日々遭遇する疾患が多種多様に記載されていることが、本参考書の最大の良いところです。間違いなく日常の診療に大いに役立つことは確実だと思います。
一般開業の外科医を表明する自分としては常にこの参考書を傍らに置き、術前には読み直して自分の知識と照らし合わせ、間違いないかを確認してから手術に向かいたいと思います。
持論ですが、元来、外科手術成功のカギは、方法を知るか知らないかの差であって、手術前からしっかりとした情報を取り入れて術前計画を行えば良い結果を得ることができるものです。この参考書では器具機材の紹介もあり、手技以外でも非常に参考になります。症例に対する適した器具機材の使用が、スムーズな進行と良い結果を生むということは経験上明確です。
いつもどんな時も準備以上の成果は無いと確信しています。この参考書を開業獣医師のバイブルとして皆さんのお手元に置いてください。
目次を別枠で検索できるようにして、症例が来院されたときに直ぐに参考になるよう準備しておいてください。皆さんの手術を成功に導くことを祈念しています。
2024年10月 掲載
『Pathology of Pet and Aviary Birds, 3rd Edition』
2024年・Wiley-Blackwell発行・¥34,210(税込)
本書のタイトルは『Pathology of Pet and Aviary Birds』である。書評の執筆にあたり「Aviary Birds」の意味が実はよく理解できなかったので、改めて辞書などでチェックすると同時に、本の内容をざっと確認してみたところ、どうも家庭で飼育されるペットの鳥類に加え、動物園などの大型ケージで飼育され、飛翔することが可能な鳥類を「Aviary Birds」は指しているようであった。このため、いわゆる獣医学の学部教育におけるコア科目に指定される家禽疾病学では紹介されないような疾患についても、豊富な写真とともにその病理学的特徴を解説してある。
本書は初版が2003年に出版されて以来、おおよそ10年おきに改訂され、今回はその第3版になる。手元にある第2版(全298頁)と比較すると2倍以上のボリューム(全740頁)になり、大幅に加筆されているのが手に取るだけで実感できる。
本の構成を確認してみると第2版が13章構成であったのに対し、第3版は19章構成になった。新しく章として追加された内容は、第1章の鳥類の解剖術式と検査方法、第15章から17章の鳥種別(ハト類、スズメ類、猛禽類)疾患、第18章の細胞診、および第19章の免疫染色や分子生物学的検査など特殊検査に関する解説である。全体を通じて第3版の写真は第2版と比較して、特にHE染色や免疫染色等の組織写真のコントラストが明瞭になり、非常に見やすく配慮されている印象を受ける。
また本書の第2版までは、著者としてScmidt RE、Reavill DR およびPhalen DNの3名がリストアップされており、実際すべての章がこの3名により記述されたようであるが、第3版では、従来の著者2名に、Reavill DRに代わってStruthers JDを新たに加えた3名で編集を担当し、執筆については章ごとにその分野の専門家が担当するスタイルに変更してある。これにより第2版と比較して、各章の内容が新しくかつ専門性の高い情報にアップデートされている。なお初版と第2版の執筆に尽力されたReavill DRについては、序文において2021年10月に天に召されたことが彼女の経歴とともに紹介され、第3版は彼女に捧げられたものであることが述べられている。
May her soul be “free as a bird.”
私も個人的に伴侶動物としての鳥類と、長い間一緒に暮らしてきたので、その病気に興味はあるものの、鳥類の病理組織観察については若干ながら苦手意識があった(核が多いので)。本書は様々な鳥類の疾患に興味のある獣医師および学生諸子に対して確実に強くお薦めできる1冊ではあるが、まずは自分自身でも改めて深く本書を熟読し、鳥類の病理学を学びなおしてみたいと思う。
2024年7月 掲載
『Pediatrics, An Issue of Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice, 1st Edition』
2024年・Elsevier発行・¥16,940(税込)
2024年4月発行の『Veterinary Clinics: Exotic Animal Practice』では、PEDIATRICS(小児科)をテーマにゲストエディターである経験豊富なジョアン・レモス・ブランダン博士とピーター・M・ディジェロニモ博士の両氏が、様々な動物種ごとにより詳しい著者をよりすぐり最新の研究を土台として膨大な小児科の専門知識を提供している。そして、著名なヨルグ、マイヤー氏がコンサルティング編集者としてとりまとめを行った。
今回のテーマは小児科にターゲットを絞り集中的に最新研究を含む診療ガイドラインなど必要十分な情報が盛り込まれた。動物種としてはフェレット、ウサギ、げっ歯類、ハリネズミ、フクロモモンガ、カンガルー類、オウム類、キジ類、カモ類の新生児ケア、鳩、猛禽類、爬虫類の最新情報、野生動物、そして、若齢動物の行動発達と条件付け、エキゾチックコンパニオンアニマルの幼弱動物の臨床栄養学について解説されている。
日本でもおそらく日常診察するエキゾチックアニマルのほとんどの動物種の情報が盛り込まれている。さらに鳥類や野生動物関連の記載や臨床栄養医学まで盛り込まれた実に便利な実用書である。
エキゾチックアニマルの小児科分野において、いまだかつてこのような書籍はなかったと思う。写真は少なめだが、ところどころに残念ながらQRコードではないが動画を視聴することができるURLがしるされている。各動物の小児科領域に関係する感染症や先天的奇形などの解説、治療に必要な具体的な薬剤、ワクチン、水鳥の脚の変形に関するスプリント固定など詳細に記されている。さらに、すべてにおいて参考文献が記されているため必要な部分はさらに文献を読み込み知識を深めることができるであろう。小児科分野の知識を必要とするエキゾチック動物臨床、鳥類臨床、動物園、水族館臨床、野生動物臨床現場などさまざまな臨床現場に従事される獣医師には必須の1冊となる事は間違いない。
動物種ごとに章立てがきっちりされているので世界最先端の知識を必要な動物の情報を選択して読み込むこともできるし、容易な英語で書かれているためどんどん読み進めていけるであろう。私も書籍が届いて1日1章ずつ読もうと読み始めたら非常に面白く3日で読み終わってしまった。エキゾチック動物の小児科だけでこれだけのボリュームを提供できるアメリカ獣医学の奥の深さに感動したのと、まだまだ知らないことも多い自分の知識のなさを恥じてまじめに勉強しようとおもった。
診療分野に携わる臨床医にとっては、小児科は避けることのできない分野である。エキゾチック動物に関する生態や医療に関する書籍収集マニアを自称する私もさまざまな成獣のエキゾチック動物に関係する成書は数多く収集しているが、エキゾチック動物の小児科だけをまとめた書籍を見たことがない。この1冊がこの価格でこのボリュームで手に入ると考えるなら出血大サービス、知識のバーゲンセールであり購入しないという選択はないと思われる。ぜひ購入して読み込んでいただきたい。
2024年6月 掲載
『Small Animal Thoracic Surgery』
2017年・Wiley-Blackwell発行・¥30,800(税込)
小動物における胸部外科学の専門書はほぼないと言ってもよいほど少ない。診療の中で胸部外科手術が必要となる症例が少ないことが主な要因と考えられる。しかし,いざ手術が必要となった場合には,他の軟部外科手術とは異なる知識やアプローチが必要となり,取っ付き難いことも現実として存在する。また,胸部外科手術は侵襲性が高いことが多く,1つ間違うと命に関わる点も敬遠されるポイントとして挙げられる。本書は,胸部外科手術の基本となるテクニックを詳細にまた多くの写真と図を交えて解説している。セクションIでは胸部外科手術を管理するにあたっての基本的事項が詳しく解説されている。心肺機能の生理学では,心拍数と血圧の関係,心拍出量と血管抵抗と心機能の関係などが図説されて詳細に記述されている。また,麻酔モニターにおける動・静脈の血圧測定法,不整脈や酸素飽和度の理解について重要なポイントが記述されている。さらに,胸部外科手術に必要な器具についてもその特徴及び選び方,使い方について参考になる記述となっている。セクションIIでは胸部外科手術に必要な開胸法の基礎的テクニックが解説されており,肋間切開および閉胸の手順が図説されている。また,胸骨縦切開についても胸骨切開および閉胸の手順が図説されて基礎的テクニックが解説されている。さらに胸腔鏡によるアプローチについても紹介されている。胸腔鏡では気腹して胸腔内を見やすくする必要があり,その方法と注意点が記述されている。機材の使用法の注意点については特に細かく記載されており,大変参考となる。セクションIIIでは胸腔穿刺と肋骨の補強,胸水および乳糜胸の管理について外科的アプローチと内科的管理についても解説されている。セクションⅣでは,胸腺腫瘍,食道外科,血管輪,気管,肺,横隔膜の手術について紹介されている。一般胸部外科の基本的なテクニックについて器具の使い方,各胸腔内の疾患別アプローチ法と手術法について解説されている。特に鉗子の使い方と周辺組織の利用の仕方について参考になる記述がある。セクションVでは,心膜,心臓へのアプローチ方が解説されている。心臓へのアプローチでは,心臓周辺の血管系のアプローチや人工心肺の原理と使い方が解説されている。特に心臓へのカニューレの設置法は他書ではみられない記述となっている。動脈管開存症では,神経や血管の扱い方および血管の結紮閉鎖の仕方について詳細に記述されている。肺動脈弁および動脈弁の項では通常の診療の中では行われないテクニックについて詳細に記述されている。三尖弁と僧帽弁へのアプローチについては弁置換術および弁修復術について解説されている。また,先天性心奇形に対するアプローチで人工心肺を用いた短絡孔の閉鎖法について詳細に記述されている。
本書は小動物における胸部外科手術を基本から理解することができ,また,すでにこれらの手術を手がけている獣医師にとっては通常の診療ではなかなか目にすることのできない外科的アプローチについて理解を深める1冊である。
「獣医畜産新報」2018年5月号 掲載
『Rebhun's Diseases of Dairy Cattle, 3/E』
2018年・Elsevier発行・¥29,920(税込)
『Rebhun's Diseases of Dairy Cattle』が10年ぶりに改訂された。本書は乳牛の疾患に特化した参考書であり,乳牛を主たる診療対象とする獣医師にとっては待望の書である。本書がカバーする内容は,乳牛の診断治療総論から始まり,各論には循環器,呼吸器,消化器,泌尿器,代謝性疾患といった内科的疾患や運動器,神経疾患などの外科系疾患はもちろんのこと,乳房疾患や繁殖障害,さらには眼科疾患や皮膚病など専門性の求められるものまで,広範囲にわたっている。また,臨床獣医師が日常的によく遭遇する疾患だけではなく,比較的稀有な疾患も多く記載されており,現場で診断に困った際にはまず手に取ってみたい本である。個々の疾患については,病因と疫学,臨床所見,検査所見,診断,治療および予防法が詳細に記載されている。なお,第3版では新たに種雄牛の疾患についても独立した章が設けられており,「乳牛」の教科書としてより完成に近い形となっている。
本書の特徴は,多くのカラー写真が効果的に用いられていることである。洋書を手に取るには語学の壁が邪魔をすることも多いが,本書にはカラーアトラスにも匹敵する豊富な写真データが掲載されている。症例の特徴的な所見,超音波画像,X線画像,病理学所見などがとてもわかりやすい。また第3版では,指定されたwebsiteから,コーネル大学提供の神経疾患,超音波画像,内視鏡などの動画データを閲覧することもできるようになっており,読み手の理解をいっそう助けてくれる。
もう1つの本書の特徴は,記載された情報が最新の学術論文の知見やエビデンスに基づいて裏付けされていることである。古い和書を教科書として学んだ獣医師には,目からウロコの発見があるかもしれない。なお,個々の疾患を深く勉強したい場合には,各章末に記載された推薦図書(suggested reading)を紐解いて勉強することが望まれる。臨床獣医師が乳牛の疾患について症例報告しようとする場合,まずは本書を参照することで,イントロダクションの部分はカバーできるように思われる。筆者も症例報告を執筆する際にはまず本書の記載を確認するようにしている。研究者及び獣医学教育関係者も必携の書である。日本でも本書のようなエビデンスベースの教科書・参考書の発刊が望まれる。
「獣医畜産新報」2018年5月号 掲載
『Slatter's Fundamentals of Veterinary Ophthalmology, 6/E』
2017年・Elsevier発行・¥24,750(税込)
本書は縁あって第4版と第5版の書評を筆者が書かせていただき,今回の改訂においてもその機会をいただくことになった。今回もこれまでと同様にその時代に合わせて内容が大きくアップデートされており,毎回編集作業を担当されている3名の獣医眼科専門医の先生方の努力には敬服するばかりである。
今回の改訂において大きく変わった点は,これまでにはなかった「馬の眼科学」,「家畜の眼科学」といった新しい章が加わり,さらにこれから眼科診療に力を入れようと考える臨床家にとって非常に参考になる「眼科手術の原則」という章も加わったことであろう。それによって本書がこれまで以上に多くの獣医師を対象にした成書になったと考える。内容の充実に伴い全体のページ数も60ページほど増えている。また前回の改訂において,図や写真がすべてカラーに変更されたが,今回の改訂ではさらに400点以上の写真が刷新されている。
内容でこれまでの版から大きく変わったことは,ほとんどのページにおいてみられる5種類に分類された囲み文である。これらはその内容によって色分けされており,記載内容に対して現在どのような論争があるかという「The Controversy Remains」,事実として受け入れられている関連事項を示す「Did you Know?」,本書内の別の箇所に書かれてある違った観点からの解説を参考にするための「Look Again」,記載された内容についてこれまでに報告されている調査や研究を簡潔に要約した「Show Me the Evidence」,そして記載内容の要点を簡潔にまとめた「Note」に分けられている。これは本書をクイックリファレンスとして参考にする場合には非常に役立つし,読書的にこれらの囲み文のみを読むだけでも非常に面白い。
前回の改訂で削除されてしまった参考文献が今回の改訂で復活し,さらにその内容が上記の「Show Me the Evidence」とリンクしていて,本書内でその要約が確認できることは,忙しく文献検索が苦手な臨床家(筆者も含め)にとって非常にありがたい改善であろう。そして60ページほどもの増量にもかかわらず,書籍の重量や厚みは前版と変わらないように工夫されているのも嬉しい。
「眼科を勉強するためにどのような成書を参考にすればよいでしょうか?」という質問はよく受けるが,そんな質問の回答として小動物臨床獣医師はもちろんのこと大動物臨床獣医師や獣医科学生に対しても推薦できる書籍の1つとして必ず挙げるべき1冊であると考える。
「獣医畜産新報」2018年1月号 掲載
『Pathology of Laboratory Rodents and Rabbits, 4/E』
2016年・Wiley-Blackwell発行・¥25,630(税込)
ネズミやドブネズミなどのげっ歯類に不意に出会った時の人間の一般的な反応は,ゴキブリの場合と大差ないものが多い。これらの小動物に対する恐怖心が,人間の本能あるいはDNAに刷り込まれ,脈々と受け継がれて来た本当の理由は定かではない。もしかしたら14世紀に大流行した黒死病(ペスト)を媒介する動物であったことが影響したのだろうか? 近年では,十分に管理された環境下で飼育される実験動物や愛玩等物として,これらに接することの方が多く,感染症を診断する機会は減少した。ただ,これらの動物を販売目的で多頭飼育している一般施設や野生環境下ではしばしば大きな問題となっている。
本書は,げっ歯類(マウス,ラット,ハムスター,スナネズミ,モルモット)とウサギの疾患について主にその病理学的特徴を解説したものであり,初版は1993年にPercy DH教授を中心に編集・発行された。今回はその第4版の発刊である。第3版からの相違点としては,近年の病理学関連の書籍同様,写真がすべてカラー化された点があげられる。これまでの版の内容を徹底的にリバイスし,第3版で使用されていた画像は,やや小型のカラー写真に修整された。改訂により追加された写真もある一方で,削除された白黒写真もある。全体としては今回のカラー化により近代的な書籍になった印象をうける。
本書の内容は,動物種別に1章から6章で構成され,特にマウス(第1章),ラット(第2章)およびウサギ(第6章)の疾患に関する記述が充実している。疾患分類としては,感染症に多くのページが割かれているのが本書の特徴である。逆にその他の疾患,例えば腫瘍疾患についての記述は極めて簡素である。マウスの特殊な系統,免疫不全マウスあるいは遺伝子改変マウスに関する記述もあるが,基本的にこれらの動物を用いた感染実験に関連する知見が多い。このように感染症に重点が置かれているのは,第4版の主な編集者であるBarthold SW教授(カリフォルニア大学デービス校)の専門がライム病に代表されるBorrelia感染症であることに起因すると思われる。
十分に衛生管理された動物飼育施設において,本書で扱われている疾患,特に感染症に遭遇する機会は,今後もますます減少するだろう。しかし,これらの知識は施設の管理運営に携わる研究者や技術者に求められる基本事項である。さらに,これらの情報は,エキゾチック動物あるいは展示動物として一般家庭や動物園等の施設で飼育されているげっ歯類やウサギに接する機会が多い獣医師や飼育関係者にとっても必要不可欠な知識である。このため本書は,このような分野を志す獣医師および学生諸子に特にお薦めできる1冊である。
「獣医畜産新報」2017年4月号 掲載
『Necropsy Guide for Dogs, Cats, and Small Mammals』
2017年・Wiley-Blackwell発行・¥12,870(税込)
本書は2017年に新刊として出版された書籍で,編集者は,いずれも米国コーネル大学獣医学部の現役教員である。本書のタイトルとコーネル大学というKeywordから,故John M. King教授の『The Necropsy Book』が連想された。獣医病理学の名物教授でもあったKing博士の本は,銀色の表紙にシンプルな文章と図で構成され,動物の解剖と検査方法を端的に解説したサイドブックだった。その本は獣医病理のレジデント全員に配布され,学部学生にも病理解剖実施の際に配布されていたかもしれない。市販されていることを知ったのは随分後のことである。『The Necropsy Book』を熱心に読みあさった記憶はなく,どちらかというと病理学の初学者向けという印象があった。
今回出版された『Necropsy Guide for Dogs, Cats, and Small Mammals』の編集者には,King博士の遺志を継承する思いがあり,その装丁や記載は,非常にコンパクトである。内容は大きく4つのパートから構成される。Part Iは,病理解剖の基礎事項であり,解剖前の準備と解剖術式が,鮮明なカラー写真とともに解説されている。Wiley-Blackwell社の本書WebsiteのResources欄をクリックすると解剖術式のビデオクリップにアクセスできる。なお日本では病理解剖した検体を整復して飼い主に返却することが少なくないが,米国の場合(個人的経験では),遺体返却を前提にした解剖は行っていなかったので,本書もこれに沿った術式を紹介している。この点に少し注意が必要かもしれない。Part IIは器官別の検査方法や代表的肉眼所見が解説される。本書では特にこの部分に多くのページが割り当てられている。Part IIIは,マウス,ラット,ウサギ,フェレット等の小型動物について,種特異性を念頭においた解剖時の留意点が解説される。Part IVは,解剖中あるいは解剖後の特殊検査(細胞診断,組織診断,微生物検査,毒物検査等)のための材料の処理方法を中心に解説される。
本書序文には“Internist know everything, and do nothing, Surgeon know nothing and do everything, Pathologist know everything and do everything, but it’s too late”という医学・獣医学の有名な格言(ジョーク?)が置かれている。本書の編集者同様,この格言に同意はしがたいが,序文の主なポイントは米国の獣医臨床領域で病理解剖率が激減している現状への憂いである。
コーネル大学留学中にBrian A. Summers教授を通じて教わった故John M. King教授の格言がある。「疾病診断にKissを忘れるな」というものだ。Kissはエモーショナルな意味ではなく,“Keep it simple, Stupid”の略で,要するに疾病の理解には多角的検証および思考が重要ということだ。“It’s very John, he is King.”彼らしいsimpleかつウィットに富む言葉と思う。動物疾病の診断において病理解剖が果たす役割はまだ非常に大きい。本書はむしろ臨床獣医師やこれを志す学生諸子に購読をお勧めしたい。
「獣医畜産新報」2017年4月号 掲載
『Veterinary Medicine, 11/E : A textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats - two-volume set』
2016年・Elsevier発行・¥39,160(税込)
『Veterinary Medicine』といえば,Blood & Hendersonが初版(1960)を担当した産業動物の標準的教科書として世界的に用いられている書籍である。我が国では,『臨床獣医学』(臼井和哉・本好茂一監訳,文永堂)として1981年に出版された第5版の翻訳本が知られており,産業動物の和書が少なかった当時,圧倒的に充実した内容を誇る参考書であった。その後,翻訳書の出版はないが,原書の充実ぶりは続いている。とにかく情報量が豊富で,牛・馬ばかりでなく,羊・山羊・豚の病気について,その病因,疫学,臨床所見,臨床病理,剖検所見,治療および予防がコンパクトに記載されているのが,以前からの本書の特徴である。本書を紐解けば一通りのことは理解できる。ただし,本体は分厚く重く,持ち歩きには不便であり,また机上で広げるにしても大判すぎて使いにくい一面があった。今回は,前回第10版の刊行から,実に10年ぶりの改訂である。この間,2名の編者が交代されており(第8~10版を担当されたRadostits先生は2006年に逝去,またGay先生は病気で引退),構成や内容に大幅な改定がみられる。
まず,新しい第11版の一番の特徴は,2分冊になって使いやすくなったことである。外見がスマートになったばかりでなく,構成も大きく変更されている。これまでの本書の印象としては,「字ばっかりの百科事典」であったが,第11版では,イラストが大幅に増えており,カラー写真もふんだんに使われていて,本文の理解を大きく助けてくれる。たとえば,留置針の設置法について,カラー写真付きで解説されており,これまでの本書の歴史からすると画期的な変化である。各章の要所に挿入されている表も,鑑別診断リストや治療薬情報(薬物名・投与量・コメント付き)など,実用的なものが格段に増えており,より現場に近いところで利用できる本になっている。全体的にみると,やはり字は小さいものの,対象の読者として臨床獣医師を意識していることが明らかである。
次の特徴は総論の充実である。本書の各論の情報量は以前から充実していたが,今回は個体診療の方法に加え,「群の診療」,「バイオセキュリティー」,「感染症コントロール」,「主な全身症状に対するアプローチ」,「輸液療法」,「抗菌薬治療の原則」についての記述が興味深い。最新の総説として勉強することも意義があることと思う。
日本では,複数種の動物を幅広く診察する獣医師は少ないかもしれないが,いずれの種に従事する獣医師にとっても,診療に出る前,あるいは戻ってきて,病気や治療に関して,曖昧な点や不明な点を調べるためには最適の参考書である。
「獣医畜産新報」2017年4月号 掲載
『Tumors in Domestic Animals, 5/E』
2016年・Wiley-Blackwell発行・¥42,020(税込)
腫瘍の獣医病理分野における必携の教科書『Tumors in Domestic Animals』の第5版が出版された。第4版に続きDr. Meuten, DJ (North Carolina State University)による編集である。初版から第3版まではDr. Moulton Jによる編集で,ある一定以上の年齢層の獣医病理学徒には,“Moutonの教科書”として親しまれた。今回の改訂では,これまでの本書の印象を一新する大幅な変更がなされた。まずイラストや写真は,すべてカラーに統一され,細胞診や免疫組織所見等を含む数種の組み写真が多く提示されている。全体のボリュームも4版の全788頁に対し,5版は全999頁で,しかもフォントが小さくなったため,従来版にくらべ2倍あるいはそれ以上の情報が込められたことになる。
第5版の大きな改訂として,まず第1章から3章の総論的部分がある。ここでは最新の腫瘍発生に関する分子生物学的知見や腫瘍診断技術に関する情報が,美しく分かりやすいイラストとともに掲載されている。特に第2章の腫瘍組織の採取方法に関するパートでは,印象的な3D合成イラストを用いて,臓器ごとに腫瘍組織の採材方法について解説されている。意外にこの点を強調する教科書はないので,病理診断学の入門編として必読箇所であろう。3章には免疫組織科学に関する情報が掲載され,表3.2として多彩な一次抗体(多くは人抗原由来)の動物種交差性に関する情報がまとめられている。この表で製造会社とその製品コード番号の情報も確認できる。特に犬に関する情報が網羅されているので,新規に抗体購入を予定される際には,まずこの表で確認されることをお勧めする。
各論部分では,特に「第6章 肥満細胞腫瘍」,「第7章 リンパ・造血器系腫瘍」,「第8章 組織球系腫瘍」の情報が充実している。これらの章は,各分野の第一人者であるDr. Kiupel M(第6章),Dr. Valli VEら(第7章),およびDr. Moore PF (第8章)により執筆され,各執筆者が個々にVeterinary Pathology誌でReviewした内容が忠実に反映されると同時に,それ以上の情報を含んだ内容になっている。また第17章の乳腺腫瘍はDr. Goldschmidt MらがVeterinary Pathology誌のReviewで紹介した,犬乳腺腫瘍の細分類に関する記述が詳細になされている。ただし,基本概念は第4版の同章と乳腺腫瘍のWHO腫瘍分類制定に尽力されたDr. Misdrop Wの考えを踏襲したものである。他章でも,それぞれ新しい概念が紹介されているので是非ご確認いただきたい。
第4版のDr. Meuten, DJのDedicationは,母親に捧げられた個人的なもので,その意図をよく理解できなかった。第5版のものは明快でDr. Moulton Jら先人への感謝が捧げられている。“This book is dedicated to mentors. They taught us and built the foundation of veterinary pathology. We are all indebted to their hard work, and their willingness to teach and create new information.”第5版ではこの言葉が強く実感できるので,是非多くの関係者にご購読いただきたいと思う。
「獣医畜産新報」2017年3月号 掲載
『Small Animal Dermatology: A Color Atlas and Therapeutic Guide, 4/E』
2016年・Elsevier発行・¥27,060(税込)
この教科書/アトラスの第4版が出版され,一通り第4版に目を通した後で,改めて自分の監訳した第2版と第3版を読み返してみた。最初に第2版の日本語訳を校了したのは2007年,第3版は2013年であった。したがって,第2版の翻訳が終了してからもう10年近くが経過している。その間に著者は初版から第2版まではLinda Medleau先生とKeith Hnilica先生であったが,第3版ではHnilica先生1人となり,この度第4版からは著者にAdam Patterson先生が加わった。著者の編成が変わるとともに内容も徐々に変化し,第2版では治療前後の臨床写真がまとめて200枚も掲載され,第3版からはエキゾチックアニマルの皮膚疾患の章が追加された。さらに今回の第4版では図や写真が一新され,特にアレルギー疾患に対する新たな治療法も加えられている。
もともとこのアトラスは,つとに有名な獣医小動物皮膚科教科書であるMuller and Kirkの『Small Animal Dermatology』のアトラス版として企画されたものであり,各疾患の病因,症状,疫学などについて詳細に記述するのが目的ではない。もし皮膚疾患の詳細な病因機序や皮膚の解剖,生理,生化学,細菌学,内分泌あるいは遺伝学のような基礎的なことについて興味のある方は,『Small Animal Dermatology』も併せて読まれることをお勧めする。この本はあくまで臨床家が,皮膚症状の外観やパターン,病歴あるいはシグナルメントを観察,聴取したのちに,考えられる診断を診察室あるいは治療室で視覚的に確認するものであろう。特に写真の美しさ,背景,角度,ポーズなどはカラーであるだけに他の教科書と比べてもクオリティーの高いものといえよう。
本書の特徴の1つとして“Author's Note”があり,私はこの部分を非常に興味深く読んでいる。このコメントは主に臨床上の“落とし穴”について触れていることが多く,特に「必要以上に診断されすぎている疾患」,「見過ごされていることが多い疾患」などの記述が出色である。特に最初の“Author's Note”はこの教科書を手元に置かれたら最初に目を通していただきたい部分である。正に本書は臨床家が診察室に置くに相応しい教科書であると感じている。
「獣医畜産新報」2017年2月号 掲載
『Canine Rehabilitation and Physical Therapy, 2/E』
2013年・Elsevier発行・¥21,890(税込)
本書は,小動物臨床におけるリハビリテーションの数少ない書籍のひとつであり,本領域の第一人者であるテネシー大学のMillis先生らのチームによって書かれた代表的な成書である。テネシー大学と言えば,世界的に有名な動物理学療法士の認定コースである「Certificate Program in Canine Physical Therapy」を主催している大学であり,そのチームによって書かれたことから,本書はリハビリテーション志す動物医療関係者にとってのバイブルとして確固たる地位を確立している。前版までは白黒であったが,第2版は全てがカラーで構成されており,より分かりやすい内容となっている。
本書は7章で構成されており,リハビリテーションを展開する上で重要な理論が詳述されている。第1章は,リハビリテーションの導入として,現在までの歴史,定義,分類,リハビリテーションの進め方について紹介されている。第2章では,リハビリテーションを行う者が知っておくべき,行動学,解剖,各々の組織の治癒形式などが書かれており,運動療法の種類や効果についても述べられている。各々の運動療法の効果については,多くの科学的データを基に説明がなされており非常に説得力がある内容となっている。また,組織そして分子レベルからも治療効果が説明されており,科学的なリハビリテーションを実践するために理解しておくべき事項が細かく記載されている。第3章は,リハビリテーションの計画を組んだり,治療効果を検証したりするために知っておくべき,整形外科学的検査や神経学的検査,客観的な運動解析法,疼痛の評価法が紹介されている。さらに,サプリメントの給与,術後の管理,運動補助のための装具についても多くの図や写真を基に説明がなされている。第4章と第5章は,各々の理学療法の目的,適応,治療根拠,方法,効能について述べられている。第4章は,温度療法,超音波療法,レーザー療法,体外衝撃波療法といった物理療法が概説されている。第5章は,運動療法,関節可動域訓練,ストレッチ,関節モビライゼーション,マッサージ療法,バランス運動,トッレドミル歩行,カバレッティレール,ハイドロセラピーなど多くの療法についてわかりやすく解説している。これらの内容は多くのページを割いて説明がなされており,本書の最も重要な部分である。第6章は,代表的な整形外科疾患や神経疾患の診断方法やリハビリテーションの適用方法について書かれており,実践的な内容になっている。第7章は,リハビリテーション施設の設立方法や規模,そして運営の仕方までビジネスの視点から述べられている。
このように,本書は小動物臨床におけるリハビリテーションのまさに1から10までがわかる内容になっている。犬や猫のリハビリテーションは多くの施設で行われ始め,ブームにもなりつつある。しかし,独学になりがちで,わが国においてはリハビリテーションについて体系づけて学べる機会は少ない。私の知る限り,リハビリテーションの全てを学べる本は世界でも本書のみであり,これからリハビリテーションについて学びたい方にとって本書は必携の書となるであろう。獣医師,動物看護師,そして学生の誰にとってもわかりやすい内容となっているので,是非ともひとりでも多くの方々に読んで頂きたい良書である。
「獣医畜産新報」2016年10月号 掲載
『Farm Animal Surgery, 2/E』
2016年・Elsevier発行・¥35,750(税込)
『Farm Animal Surgery』が初版発行から12年ぶりに改訂された。“Farm Animal”の名前の通り,牛を中心としながらも,豚や羊,山羊など様々な家畜の最新の外科治療が記載されている。
“Surgery”のイメージからすると“外科手術書”ととられる向きも多いと思う。日本の家畜,特に牛の獣医療の世界では外科手術の適用されるケースが非常に少なくなってきており,本書の必要性に疑義を呈する方もおられるかもしれない。しかし本書の内容は,家畜独特の保定法や注射法などから始まる“家畜の外科治療”全般の教科書である。教科書と言っても通り一遍の一般論の展開ではなく,疾病毎に診断と治療の手順について,必要なことを網羅しながらも簡潔丁寧に記されている。
Part1の前半では,ロープワーク,保定法,診断法,薬剤や補液を含む治療法,麻酔法,画像診断法,注射法,術後管理法などの概論があり,学生教育にも理解しやすく,外科治療を得意としない臨床家の皆様にとっても大いに役立ちそうである。Part1の後半では家畜に共通の腫瘍,眼科治療,歯科治療などに関する詳細な記載がある。Part2以降では,牛,子牛,羊と山羊,豚と,動物毎に外科治療法が記載されている。このなかで最も重点の置かれている牛(Part2)では,体表の外科,呼吸器系と循環器系の外科,消化器系の外科,骨格筋系の外科,繁殖系と尿路系の外科に分けて,本書の半分以上を費やして記載している。それに続くPart3の子牛の項では,子牛特有の消化器系の外科,骨格筋系の外科,臍と耳の外科などが記載されている。
本書の特徴はカラー写真の多さである。それも疾患そのもののピンポイントの写真のみではなく,カラー図,解剖写真,骨標本写真,X線画像,超音波画像,内視鏡画像,CT画像などを組み合わせ,患部の状態把握,診断,処置あるいは手術の方法を,これでもかというくらい懇切丁寧に解説している。処置や手術に用いる器具や道具に関しても写真を交えながら丁寧に記載しており,本書1冊さえあれば外科系の診断と治療には困らない内容になっている。
図や写真だけを追っていくだけでも十分に勉強になり,学生の外科学の勉強にも有効であるが,臨床家が常に手元に置く座右の書として,本書は最適のものと思われる。
「獣医畜産新報」2016年9月号 掲載
『Guide to the Dissection of the Dog, 8/E』
2016年・Elsevier発行・¥15,180(税込)
犬の解剖学を詳細に調査・分析した今の時代の解剖書
犬の身体の構造は昔も今も同じである。だから,犬の解剖学の解説書に改訂など必要あるのか!? …という乱暴な批判が成立するのかも知れない。しかし,私にはそうは思えないのである。
犬の身体構造は昔も今も同じだろうが,その解説書を利用する人々,つまり獣医学を学ぶ学生は昔と今とでは異なるからである。獣医学に限らず,教育にはその時代にマッチした教授法が必要であり,それに伴って教科書を含む教育ツールも進化する必要があると思う。
そして,歴史ある解剖学書が今の時代にマッチした形にブラッシアップされて登場してくれたのである。
本書の初版は1971年に発行され,以降,時代にニーズに合わせて改訂を繰り返してきた。そしてこの度,第8版が発行された。
本書のタイトルにdissectionという一語が含まれている。ご存じのように,この言葉には切開,解剖,解体と言った意味があるのは周知の通りだが,もう1つ「詳細な調査・分析」という意味もあるのだ。本書は,1964年に初版が発行され2013年に第4版が発行された『Miller’s Anatomy of the Dog』という犬の解剖学専門書のコンパクト版に位置づけることができる。Miller’s…は850頁およぶ膨大な書籍であるのに対し,本書は327頁と確かにコンパクトになっている。
解剖図は一部を除いてカラーのイラストである。これらのイラストは全てMiller’s…からの抜粋だが,イラストによってはMiller’s…のそれよりも大きく掲載されている。今の時代の解剖書としては当たり前だが,本書でもMRI画像が掲載されている。また,随所で触診との関連性に言及している点は,臨床教育に携わる者として非常に好感を持つ。
その昔,白黒のイラストで解剖学を学んだ世代の方々には,「今の時代にマッチした解剖学書」である本書を楽しめると思う。また,私の印象では,本書は特に運動器系および末梢神経系の記載が充実しているように感じられる。すなわち,整形外科および神経病の基礎を復習したいとお考えの先生にも恰好の書だと確信する。
本書は,これから解剖学実習を受ける学生が,実習前後に効率よく予習・復習するための参考書としてそもそも作られた。このため,Miller’s…と比較してコンパクトであって良いのだろうが,それでも本格的な犬の解剖学の解説書と筆者には思えるのである。そして,本書の著者も同じようなお気持ちでいらっしゃるのでは,と私には思えるのである。そう思う理由は,著者陣はこのコンパクトな解説書にあえてdissectionという一語を与えているからである。無論,このdissectionは「詳細な調査・分析」という意味に取りたい。
「獣医畜産新報」2016年9月号 掲載
『Atlas of Small Animal Ultrasonography, 2/E』
2015年・Wiley-Blackwell発行・¥34,210(税込)
超音波検査では内部構造の観察が手軽にできる。X線CT検査は断層画像を得ることで内部構造の観察が可能である。それぞれに特長があるが,超音波検査の場合,無麻酔で行えるということが大きなメリットである。ただし,麻酔薬の安全性や麻酔技術が飛躍的に向上したことから,「麻酔の必要がない」ということのメリットは以前に比べ薄れた感は拭えない。また,X線CT装置は低価格化などが要因となって,小動物診療を目的としたCT装置は確実に国内に増加している。
しかし,超音波検査はその手軽さから,X線検査とともに一般の動物病院で欠かせないことは間違いない。CT装置があまねく普及するとも思えない。
さて,そこで問題は,超音波検査は自ら臓器や病変を描出しなければならないため検査技術を要し,全体像を想像するのが難しいということである。存分に使いこなすには,努力して技術を習得しなければならない。
小動物の開業獣医師や勤務獣医師を対象とした超音波実習を20年近く行ってきて感じるのは,参加してくれている方々の検査技術はかつてと比較し,間違いなく向上していることである。臨床家であるならばぜひともその技術を得て欲しいものである。超音波検査に対して得意不得意が二極化するようなことがないようであって欲しい。
本書は2000枚以上におよぶ詳細な超音波画像によって,正常像から各疾患における特徴的な所見までを解説している。超音波診断装置は,常に様々な画像処理が改良または開発され,年々マイナーチェンジが施されている現状にあり,同一機種であっても製造年度の新しいものは画質が改善されている。このような時代に即した明確な画像が新しく追加されていることはもちろん,内容についても各章新しい著者が加わり,最新の知見が追加されている。また,従来通り,基礎から診断,さらには超音波造影剤の応用までと充実している。
第1版が2008年に出版され,監訳者としてその翻訳出版に携わり,2009年には日本語版を出すことができた(文永堂出版発行)。その作業過程で第1版は4回以上は目を通し,精読し,その内容の充実さを実感した。この第2版はさらに内容が充実しているのは前述の通りである。本書は超音波検査が得意な人にも,不得意な人にも,さらには学生にとっても現在において最良の超音波診断書である。
「獣医畜産新報」2016年7月号 掲載
『The Illustrated Horse's Foot: A comprehensive guide』
2015年・Elsevier発行・¥30,800(税込)
日本の獣医教育では動物種ごとの専門教育も行われているが,馬については,生産頭数の減少や,その飼養目的がスポーツやレジャーなど高いパフォーマンス能力を必要とするため,獣医大学在学中に十分な専門教育を受ける機会が少ない。さらに,馬にとっての「蹄」は,パフォーマンスや跛行の原因として重要な器官であるにもかかわらず,大学教育の中での学習優先順位は低い傾向にある。そのため,馬の診療現場では,護蹄管理を専門に行う認定装蹄師と臨床獣医師との間で,運動器疾患の診断や装蹄療法の方針について,意見が相違することが少なくない。
本書は,既存の獣医解剖学や臨床関係の書籍では不足している馬の蹄の複雑な構造と機能,代表的な蹄病(下肢部の疾患)などについて詳細に解説した「馬の蹄」の専門書で,馬の護蹄管理に必要な基礎的知識を得られるように配慮されている。旧版に相当する『Color Atlas of the Horse’s Foot』(1975年)と同様に,多数のカラー写真と図が使用されているが,本書では,これらに加えて,鮮明な光学・電子顕微鏡写真や血管造影写真もふんだんに盛り込まれている。また,最も大きな特徴は,書名にあえて“Illustrated”という用語を使用した理由にもなっているが,蹄を様々な方向から割断した写真とCTやMRIのデーターを基に3Dモデルを作成し,複雑な蹄の内部構造や病態変化を立体的にイメージできるようにしたところである。構成は大きく2つのセクションに分けられている。セクション1の「蹄の構造と機能」では,蹄鞘,知覚部,骨,関節,脈管系など,蹄を構成する項目ごとに解説されている。これに加え,X線像や組織構造,蹄骨懸垂機構についても別項目で説明し,馬にとっての蹄が,角質器としての役割に止まらず,体重を支持する重要な器官であることが理解できるよう構成されている。また,セクション2の「蹄疾患」では,蹄葉炎,ナビキュラー病,蹄尖の裂蹄,白帯病,蹄軟骨化骨症など,臨床現場で遭遇する主な蹄病の原因と症状,装蹄療法が明瞭に説明されている。特に,蹄葉炎については,ステージごとに肉眼写真や血管造影を含めたX線像,組織写真などを多数使用して,その多彩な病態変化とそれに合わせた装蹄療法理論を解説している。
この書籍は,馬の臨床獣医師や教員などの指導者だけではなく,これから馬の獣医師を目指す学生にも大いに推奨される1冊である。また,獣医師・認定装蹄師・馬管理者・オーナーなど,馬関係者どうしの相互理解と協力体制を構築するための有用な資料としても活用できることだろう。
「獣医畜産新報」2016年6月号 掲載
『Avian Medicine, 3/E』
2015年・Elsevier発行・¥29,700(税込)
本年(2016年)に出版されたDr.Jaime Samourによる『Avian Medicine』第3版は,2000年の初版,2008年の第2版につづく最新版である。本書で私が注目した4つの特徴について以下に紹介したいと思う。
1.タイトルに「The color atlas of~」と冠しても良いほど,鮮やかなカラー写真を900点以上も盛り込んだ著書である。また,表やイラストも多用しており,読者が視覚的に理解しやすい工夫と試みが随所にみられる。
2.多くの鳥医学書がオウム・インコ類を中心に書かれているのに対し,本書ではノガン類と猛禽類が主役に据えられている。これはサウジアラビアを拠点におく著者ならではの視点なのであろう。したがって,本書は,猛禽類の診療施設はもちろん,鳥類飼育展示施設や野生鳥獣保護施設においても必携の書であることに疑いの余地はないが,オウム・インコ類やフィンチ類といった一般的な飼い鳥を診療対象とする臨床医にとっては,多少の物足りなさを感じるかも知れない。それでも,血液検査や外科的手技を取り上げる章は,鳥種の垣根を越えた実践的で有用な内容が非常に多く,巻末の90頁超にわたる膨大な参考資料も多くの鳥種をカバーしている。
3.感染症の章では,ウイルス(19頁)や細菌(9頁),真菌(20頁)と比較して,寄生虫に割いている紙面が43頁(表11点,写真94点)と異常に多い。これは他の鳥医学書ではまずみられない大きな特徴であり,寄生虫好きの臨床医や研究者には垂涎の章となるに違いない。この傾向も著者が研究対象としているフィールドにおいては必然なのかも知れない。
4.臨床視点で書かれた「実践的な総合医学書」であることが本書の最大の特徴である。しかし,2000年の初版本に対する当時の私の印象はそれとは大きく異なっており,“偏った内容の変わった鳥医学書だな~”というものであった。8年ごとに2度の改訂を経てきた最新版は,果たして目を見張るほどの進化を成し遂げたのである。ちなみに,章構成は①収容,環境および国民意識,②鳥の知能,臨床行動および福祉,③栄養と栄養学的看護,④捕獲とハンドリング,⑤臨床検査,⑥臨床および検査室での診断検査,⑦麻酔と鎮痛,⑧医療,看護およびコスメティックの手順,⑨外傷に関連した病状,⑩飼育管理に関連した病状,⑪軟部組織の外科,⑫整形外科,⑬全身性疾患,⑭感染症,⑮繁殖,⑯死後の病理検査,⑰鳥類医学における法医学検査,と広範囲に及んでいる。
最後に,この名著が1人でも多くの臨床医と研究者に読まれるためにも,日本語での翻訳本が早期に出版されることを強く望むものである。
「獣医畜産新報」2016年6月号 掲載
『Current Therapy in Exotic Pet Practice』
2016年・Elsevier発行・¥18,590(税込)
本書を和訳すると『エキゾチックペット臨床における最新治療』ということになるだろうか。Elsevier社からのCurrent Therapy シリーズには小動物(犬・猫におけるKirk's Current Veterinary Therapyは有名で,すでに15版になっている)のほかに馬や鳥類,爬虫類が出版されており,この度エキゾチックペットがそのラインナップに加わった。わが国では,エキゾチックペット臨床に関する情報はまだまだ十分とは言い難い感がぬぐいきれないが,本書の刊行は欧米諸国においては,エキゾチックペットが獣医臨床の現場においても欠かせない一分野として認識されている証でもあるのだろう。
本シリーズはタイトルに違わずその分野の最新の知見をもとに編集されている(言い換えれば,すでに周知されているような基本的な情報は詳しくは述べられていない)。手前味噌ながら,筆者は恐らく入手可能なエキゾチックペット医学に関する書籍のほとんどを入手している(全て読んでいるかは別にして)と自負できるが,それらの中には,残念ながら孫引きや過去に出版された情報の単に寄せ集め的な書籍も存在する。しかし,このシリーズの初版ということもあるだろうが,過去に見たことがないオリジナルの解剖生理学的なカラーイラストをふんだんに用いて詳細に解説されている。
エキゾチックペットという多種を扱う教科書というと,どうしても広く浅くなってしまう感が否めないが,誤解を恐れず言うと本書は,狭く深くという表現にピッタリな構成となっている。したがって,既存の情報だけでは飽き足らない獣医師が細かな部分を検索する辞典代わりとして使うことも可能である。また,この手の多くの書籍は動物種別に解説されているが,本書は動物種で分けるのではなく,各器官別に編纂されているところも特徴である。その構成内容は外皮系,呼吸器系,循環器系,消化器系,内分泌系,骨格筋系,中枢神経系,眼科,生殖器系,泌尿器系となっている。さらに特筆すべき点は,非常に多種多様なエキゾチック動物を含んでおり,哺乳類,鳥類,爬虫類に留まらず,両生類,魚類,無脊椎動物(タランチュラやカニ!)にまで及ぶ。日本における実際の臨床現場で,両生類,魚類,無脊椎動物まで診療対象とする獣医師は極めて少ないと思われるが,一部のコアな開業医やむろん動物園水族館の獣医師にとって非常に有用な情報を提供してくれるだろう。
ただ,この分野の初学者の方にとって重要な飼育技術や栄養学に関しての記載は一切ないため,そのような情報が必要であれば,エキゾチックペット臨床の教科書ともいえるKatherine Quesenberry らの編集による『Ferrets, Rabbits, and Rodents: Clinical Medicine and Surgery』第3版を手元に置き,本書を更なる情報の検索として活用していただければ,より確かな知識が身に付くだろう。
「獣医畜産新報」2016年5月号 掲載
『Joint Disease in the Horse, 2/E』
2015年・Elsevier発行・¥33,220(税込)
この本は馬の関節病の病態生物学的最新情報とその臨床応用法(とくに治療法)を馬の臨床家に向けて書いたものの第2版である。第1版は1996年に出版されているので,この新版にはその後19年間の進歩と変化が加えられている。旧版と同様,新版も馬の関節病の主流である発育性関節疾患および外傷性関節疾患の記述が中心であるが,これらに関する再定義や特定の病態生物学的・生体力学的メディエーターを目標とした新しい治療法も記載されている。また旧版では人や実験動物の理論を馬に外挿したところも随所にあったが,新版では馬自体のエビデンスを主体にした内容になっている。
章の構成内容も大きく変えられた。第1章は関節病の一般原理と関節の生理機能を扱っている。関節の解剖,生理,生体力学を基にして外傷性関節炎から,さらに離断性骨軟骨症,感染性関節炎まで要領よく記載されている。第2章は診断と治療の一般原理となっているが,その内容は画像診断および関節液と血清中のバイオマーカー診断の総説である。ここでの治療というのは治療経過や治療に対する反応の診断評価のことを指している。第2章の末尾には馬の全関節のX線解剖参照像が付録として44頁のスペースを取って掲載されているが,これらはX線や画像を扱った他書に譲ってもよかったかもしれない。第3章では外傷性関節炎および骨関節炎の薬物別の治療法とその効果に関する最新の馬のエビデンスが中心的に記載されている。旧版の薬物中心の薬理学的記述が,新版では現存する製品を重視した内容になり,実務家には有難いだろう。しかし馬用に製品化されていない薬物の情報は省略されていて日本で製品が入手できない場合はお手上げになることもあり得る。新版でこの章に付け加えられたものは生物学的治療法および幹細胞を用いた治療である。さらに人でも盛んに宣伝されている関節疾患に対する経口サプリメントについても付け加えられている。その他,リハビリと理学療法もこの章に詳細な記述として収められている。第4章は新しく加えられた馬の関節疾患の各論の章で,関節ごとに解剖学的特徴,臨床診断法,あらゆる種類の画像診断法とその画像,治療法が詳細に記載されており,図像も多用されていて極めて理解しやすい。最後の第5章は付録的な章で,馬の関節病の現在と未来の研究方向について書かれており,早期診断,関節軟骨の修復,運動による関節外傷などが略記されている。
この本は競走馬や競技馬を多く診る馬の臨床家にとって,これ1冊で馬の関節疾患の最新知識と情報が得られ,関節病を診れて・語れる獣医師になる有難い1冊でもある。
「獣医畜産新報」2016年3月号 掲載
『Current Therapy in Avian Medicine and Surgery』
2015年・Elsevier発行・¥28,270(税込)
タイトルに冠せられた”Current Therapy”の2語が示すとおり,鳥類医学分野の最新情報が掲載された書である。これまでに出版された多くの鳥類医学書のつもりで手に取ると戸惑うかもしれない。実際,私は各項目を読み進めるにつれ「おや?」とか「あれ?」とか感じた。鳥の診療に必要な一般的情報の多くが欠けていたからである。反対に初めて目にする病名や病原体名や治療名が少なくなかった。勉強不足を露呈するようで恥ずかしいが,若い動物園獣医師の幾人かにそれらの名称を問い合わせても同様であったので,大勢は変わらないだろうと勝手に安堵している。
本書の緒言には,常に新しい鳥類医学の情報を提供していきたいという編者の意気込みが書かれているので,今後,シリーズ本として数年毎もしくは毎年出版されるのかもしれない。最初に出版計画が立てられたのは2013年1月だから,すでに3年分の新たな知見が蓄積されているに違いないと思う。
この大著を開いてまず驚いたのは,全908頁に挿入された多数の写真や図表がフルカラーであることだ。比較する意味はあまりないだろうが,40年以上前に使っていた獣医学の教科書とは隔世の感がある。本書は,4章と3つの別表で構成されている。各章は,1. 鳥類医学の発展,2. 麻酔・鎮痛・外科手術の発展,3. 動物福祉・保全・飼育管理の発展そして4. 地域別観点からの鳥類医学から構成され,章全体には25の項目(節)が含まれている。その概要を以下に記すと,1) 鳥類医学の歴史,2) 感染症,3) 腫瘍性疾患,4) 栄養学と栄養学的治療の発展,5) 行動,6) 心臓病学,7, 8) 下部臓器と胸部臓器の治療的特徴,9) 神経学と神経解剖学,10) 内分泌学,11) 免疫学,12) 繁殖学,13) 臨床病理学と診断医学,14) 画像診断学,15) 鶏病学,16) 走鳥類の医学,17) 救命救急診療,18) 毒物学,19) 麻酔,20) 疼痛管理,21) 外科手術,22) 鳥類の動物福祉,23) 鳥類の保全,24) 危機管理,25) 地域別による鳥類医学など多岐にわたる。 別表は,一般的薬剤リストと容量,臨床病理学的データ,生理値である。この項目名を眺めるだけでも,本書の新規性が理解できるであろう。
本書を執筆したのは優に80名を超える。知っている名前も散見されるが,ほとんどが新進気鋭の研究者や臨床家のようだ。いつも感じることだが,欧米先進国における鳥類医学や野生動物医学の発展に追いつくのは容易なことではない。せめて,このような最新図書を読んで遅れないようにしておきたい。
「獣医畜産新報」2016年3月号 掲載
『August's Consultations in Feline Internal Medicine, Volume 7』
2015年・Elsevier発行・¥28,930(税込)
これまでJohn R. Augustの編集によるシリーズとしてほぼ3年毎に1巻ずつ追加され,6巻まででほぼ完成をみていた猫の内科学全書ともいえるシリーズ刊行本であるが,今回からはAAFP(米国猫臨床医協会)会長のSusan Littleの編集による,全く新しい本ともいえるものに発展した。これまでのシリーズは1冊で完結するものではなく,前々からの知識の積み重ねで学ぶようになっていたが,今回はこれまでの多くの記述を新たにリセットして,これ1冊でも猫の内科学全書として通用するような充実した内容になっている。そのため頁数は圧倒的に増え,ハードカバー1061頁の堂々たる単行本に仕上がっている。編集の手法はこれまで通り,系統別セクション毎に,その分野全体に精通したセクションエディターを置き,その中の個々の項目を比較的若い専門家を中心に執筆させている。
今回は,感染症,消化器病,内分泌/代謝性疾患,皮膚病,心臓病/呼吸器病,泌尿器疾患,腫瘍,栄養,ポピュレーションメディスン,救急医療,行動治療,小児科疾患/老齢疾患という猫の内科学を十分網羅する12のセクションに分け,それぞれの中で興味深い平均7~8項目について記載があり,合計103の項目からなっている。ただしこれらの項目は最新の記述が必要な項目であり,昔からあまり変わっていない項目については本書では触れられていない。したがって,本書で一から猫の内科学を勉強するというものでもなく,これまでの猫の内科学に関する基本的な知識は必要である。そのような意味では,猫の内科学を一から網羅した本として,同じSusan Littleの編集による『The Cat』(Elsevier,2012)を手元に置いておくとよい。したがって,『The Cat』の内容を基本に,最新のアップデートを記述したのが本書であると理解すればよい。
本書に書かれた数々の興味深い新知見を拾ってみると,複数の病態に対する幹細胞移植療法,インスリン休薬に持ち込める糖尿病,インスリン抵抗性および不安定な糖尿病,甲状腺機能亢進症と慢性腎臓病の併行治療,甲状腺機能亢進症の再発,内臓疾患と皮膚病,猫におけるシクロスポリンの使用法,心臓関連の血液検査の解釈,心臓病と栄養管理,大動脈血栓症の治療と予防,猫の軟部組織肉腫,プラズマ細胞腫瘍,猫の栄養における炭水化物,クリティカルケアーにおける栄養,シェルターにおける感染症の予防,凝固亢進状態の診断と治療,血液製剤の選択と使用法,猫のCPRに関するエビデンス,線維性胸膜炎,多頭飼育家庭における猫同士の調和を作る方法,老齢猫の筋肉減少と体重減少,老齢期の免疫低下への対処,心臓と腎臓の問題の同時発生,猫の認知症などなど多数ある。
「獣医畜産新報」2016年3月号 掲載
『Small Animal Clinical Techniques, 2/E』
2015年・Elsevier発行・¥12,980(税込)
学会展示場の文永堂出版のブースで,夫婦合作の本『快適な動物診療』のサイン会をしていたら…「ちょっとためになる本があるので,書評をお願いできますか?」と見せていただいたのが,この本です。(わっ,英語だ! 無理でしょ!?)と一瞬思ったのですが,めくってみると見やすいレイアウトに写真やイラストがいっぱいです。
血液検査や尿道カテーテル導入を行う時の保定のコツ,耳介での血糖値測定法,筋注のポイント,皮下注射の基本,留置針の取れにくいつけ方,耳・目・鼻・歯・肺・気管の検査も出ています。鼻カテーテルのつけ方など,ちょっとしたアイデア,臨床で役立つ手技が豊富に記載されています。本を購入するとネットでさらに勉強ができます。
私達がなるほど! と感心した1つに,ノミやツメダニの検出に,吸引式の掃除機を使う方法です。吸引ホースの継ぎ目にフィルターをつけて,被毛部分を吸引して検出するという裏技でした。
皮膚(パンチ)バイオプシーでは,浸潤麻酔法の具体的な手順や生検後の皮膚縫合法が,わかりやすいイラストと写真の組み合わせで説明されています。
基本的なことはもちろん,関節や神経などほとんどの組織の検査および検査時の保定まで,ていねいに記載されています。エキゾチックアニマルの髄内留置法も含まれていました。
「この頃の若い先生は,検査や画像診断は得意だけど,肛門腺しぼりは苦手みたい」という飼い主さんの声も聞きます。この本には,爪切りや肛門嚢の圧迫法のコツもわかりやすく出ています。高度なことができても,飼い主さんには理解しにくいことも多いので,誰にでもわかることやできることを,誰にもできないくらいていねいに行うことで,飼い主さんの心をつかめそう! と思いました。

この本のもう1つの使い方として,図がきれいでわかりやすいので,検査や処置の前に,飼い主さんにこの本で説明して納得してもらいます。説明文は英語ですがシンプルで,飼い主さんも横文字のアカデミックさに「あ,この先生や看護師さん,勉強好きで頼りになりそう?」と思ってくれるいう効果もあります。私達も専門用語の勉強と思って,日頃から英文に触れていると,自己のレベルアップにもつながります。
待合室の飼い主さんにもよく見える所に立てかけて,獣医師だけでなく看護師さんにも活用していただけると,インターナショナルな空間となり,向上心旺盛の病院の雰囲気になることまちがいなし! の1冊でした。
「獣医畜産新報」2016年2月号 掲載
『Feline Behavioral Health and Welfare』
2015年・Elsevier発行・¥17,050(税込)
行動学関連の専門書は,いまだに十分揃っているとはいい難く,獣医学生や獣医師に適切な情報が広がりにくいという歯がゆい思いがある。猫に関する専門書となるとなおさら不足感が否めない。
そんななかで手にした本書は,その構成が画期的だ。具体的には次の通りである。
①行動学をベースに理論および現場での応用に言及している。
②20人にわたる執筆者は半数が行動学専門家,残りの半数が猫専門の臨床医(5人),神経学専門医(1人), 麻酔専門医(1人),内科医(1人),および動物の福祉専門家(2人)で構成されており,それに伴って監修者も行動学専門医と猫専門の臨床医の2人である。
③執筆者はアメリカ,ヨーロッパ,オーストラリアと国際色豊かなため,文化や生活様式の違いにとらわれない知識を得ることができる。
本文の内容を少し紹介すると,猫の移動,診察,保定,入院時の扱いといった具体的なノウハウはもとより猫のストレス,肥満,疼痛,が与える行動上の変化とその対処法などが含まれているのだ。このようなユニークな構成による全8章(以下に列挙)には, 正常な行動から問題となる行動,異常行動まで多岐にわたり, 網羅されている。加えて後半には一般臨床でよく話題になる30項目の飼い主向けハンドアウトも補足されているので,日本語に訳せば日常診療にもすぐに役立つはずだ。行動学と獣医学の融合が随所に述べられている本書は,猫の診察に携わるすべての臨床家の必読書といえるだろう。
1章:はじめに(臨床現場における猫の行動学の重要性と動物の福祉)
2章:猫の正常な行動
3章:問題行動の予防(家庭編)
4章:問題行動の予防(動物病院編)
5章:疾患と行動の変化の関係
6章:問題行動の治療と管理
7章:動物病院で問題となる行動の対処法
8章:家庭で問題となる行動の対処法
「獣医畜産新報」2016年1月号 掲載
『Clinical Equine Oncology』
2015年・Elsevier発行・¥29,040(税込)
日本の近代獣医学史に馬科学が重要な位置を占めることは良く知られているが,1980年代に教育を受けた自分にその実感はなかった。馬を特別な存在と認識したのは,英国の獣医系大学を視察し,さらに米国で病理研修医として修学した時だった。欧米と日本では,馬と人間の関係は大きく異なる。英米の馬は,基本的に伴侶動物であり,その疾患や治療法の研究も盛んである。本書の筆頭著者であるKnottenbelt教授は,英国グラスゴー大学とリバプール大学に籍をおき,多数の学術論文を執筆されている馬内科学の世界的権威である。英国王室よりOBEを叙勲されたのもこれらの業績が高く評価されたのであろう。
本書は馬の臨床腫瘍学を,大きく3つのセクションに区分して解説している。第1セクションは,腫瘍学総論であり,9章で構成される。個人的には,本書の白眉はこのセクションと感じた。内容は最新の知見を反映し,獣医学を学ぶすべての人に有用な「動物腫瘍学」の教科書となるものである。加えて本セクションでは,多数のイラスト,表,肉眼および組織写真が使用され,その理解を手助けしてくれる。しかもいずれも実に美しい。特に肉眼写真や組織写真は,その鮮明さや色合いなど,素晴らしいものばかりであり,病理学のカラーアトラスとしての役割も兼ね備えている。第2セクションと第3セクションは,馬の腫瘍学各論に相当し,それぞれ17章,11章で構成される。まず第2セクションでは,腫瘍の病理像が細胞・組織分類ごとに紹介される。ここで特筆すべき点は,馬ザルコイドと黒色腫関連の病変に関する学術情報が極めて豊富であることである。特に馬ザルコイドに関する引用文献量の多さには圧倒される。この章は,馬を専門とする獣医師にも読み応えがあると思う。第3セクションでは,臓器別に腫瘍の肉眼像,診断,治療および予後が簡潔に述べられている。このセクションは実際に腫瘍に罹患した馬に対し,獣医師がいかに対応するべきかを導く,実用書としての価値が高い。
本を楽曲にたとえると,本書のトーンを決定しているのは,Knottenbelt教授の英国紳士らしいウイットと馬への愛情である。教授のウイットは,イラストのさりげない隠し味として顔をのぞかせており,それに気づくと思わず笑みがこぼれる。本書の冒頭には,アルベール・カミュの言葉とともに,本書は馬,ロバ,ラバに捧げたものである旨のDedicationが配されている。短いながらもその言葉には,馬への愛情があふれている。本書のこのような世界を充実した内容とともに是非手にとって感じていただきたいと思う。
「獣医畜産新報」2015年12月号 掲載
『Manual of Canine and Feline Cardiology, 5/E』
2015年・Elsevier発行・¥23,100(税込)
本書は1985年に初版が発行され,7年ぶりに改訂された第5版である。
心臓病学に限らず,獣医学は日々発展を遂げている。そのことから,広い臨床分野において,各領域の最新情報を常に取り入れることはなかなか困難である。本書が対象としている主な読者は,臨床家や学生である。その内容は心臓病学の基礎に加えて,臨床的に重要な最新情報をわかりやすく効率的に提供することに重点が置かれている。多くの書籍は版を重ねるごとに内容量が増加していくのが普通である。本書における索引を含めた総ページ数は,第3版が443ページ,そして第4版は455ページであることから,ページ数からするとその内容量はそれほど増加していない。また,本書のサイズは旧版と同じ小型なサイズ(B5判大)であることから,コンパクトに最新情報を提供するという発刊の方針は守られている。
ページをめくると旧版と比較してより多色刷りとなり,見やすくなった。内容的には,旧版と同様な構成であり,随所に「KEY POINT」という囲いの小項目が設けられ,それぞれの疾患の診断や治療等に対する重要点や勘所が記載されている。このKEY POINTのみを拾い読みしても循環器に対する理解を深めることに役立つ。また,FAQ(よくある質問)が各章の最後に設けられ,専門書としては形式にとらわれない解説がなされている。本書は一見すると第4版と同様に見えるが,両版を比較すると,随所に加筆修正されていることに容易に気が付く。治療薬については,新旧の薬物の入れ替わりがあったり,薬用量が変更されている。新薬については,ある薬は第4版から記述が増えているが,他の薬では減っていたり,場合によっては割愛されていたりする。このように治療薬の解説を読んでいくと,その薬物の臨床的研究の進捗状況や最新知見がわかる。深読みすれば,それぞれの著者の観点から,薬物の実際の使用感が推測出来るようで大変に興味深い。
旧版にない章としては,診断から「遺伝子診断とバイオマーカー」が独立し,さらに「心臓病の栄養管理」が新しい項目として設けられた。第5版で著者が交代した章は,「猫の心筋症」,「心膜疾患と心臓腫瘍」であり,内容が大幅に変更されている。「先天性心疾患」,「不整脈の治療」,「心肺蘇生」,および「緊急治療」については,著者の一部が変更となった。このことにともなって,文章だけではなく,図表が非常に古いものから新しいものに差し替えられていることは好印象である(特に心エコー図)。
以上,本書は初版から30年を経ているが,コンパクトであり続けながら,最新の知見を加え,発展を続けている良書と考えられる。
「獣医畜産新報」2015年10月号 掲載
『Clinical Echocardiography of the Dog and Cat』
2015年・Elsevier発行・¥29,920(税込)
あのDr. Chetboulによる心エコー図検査の解説書が発行!!
本書は3名のフランス人小動物心臓病学者による合作である。3名のリーダーはあのDr. Chetboulである。彼女は獣医心臓病学者の間では有名な先生のお一人である。私の知る限り,彼女のグループは100を超える研究論文を発表してきており,その大部分は2003~2010年という限られた期間に集中して公開されている。そして,これらの論文の中には,我々にとって基本文献に位置づけられるものが少なくない。
短期間で大量の論文を執筆・発行することが,彼女達にとって心労になっているのではと思い,数年前にDr. Chetboulにそのことを直接伺ったことがある。彼女の答えは「論文を書くことが楽しくて仕方ない」だった。
さて,今年になってDr. Chetboulらは『Clinical Echocardiography of the Dog and Cat』という心エコー図検査の解説書を発行した。かねてから彼女の仕事ぶりに興味(というか尊敬の念)を持っていた私は,本書の発行を心から待ち望んでいた。
本書は5つのパートから構成されている。最初に,正常なエコー図像の描出法,見え方,測定値が解説されている。次のパートでは組織ドプラ法,経食道心エコー図検査,3次元心エコー図検査など新規の検査法が扱われている。パート3では,心室の収縮能および拡張能を中心とする血行動態の評価法が述べられている。パート4および5は様々な後天性および先天性心臓病が解説されている。
通読して,本書には2つの特徴があることに気づいた。
第一に,心エコー図検査の学習に不可欠な動画ファイル(ビデオ)が,webサイトで閲覧できることである。その数,なんと91である。無論,読者が納得するまで繰り返し閲覧できる。加えて,約400の写真が約340頁の本書に掲載されており,視覚を通じて理解を深めることができる。
第二に,心エコー図検査の誤差に言及していることである。これは,パート1の中の独立した章で扱われている。どんなに機械が優れていても,動いている心臓を相手に人間がプローブ(探触子)を操作して,心臓の各部位のサイズや血流速を測定するため,測定値に誤差が含まれるのは当然のことである。しかし,医学領域を含めこれまでに発行されてきた心エコー図検査の解説書で,この誤差の問題が取り上げられたことは全くといって良いほどなかった。本書が誤差の問題を扱ったことは,画期的だと私は思う。
本書は単なる検査所見の解説に留まらず,随所に血行動態との関連性に言及している。心エコー図検査の学習に役立つばかりか,各種心臓病の病態を深く理解する上でも恰好の書と確信する。
「獣医畜産新報」2015年8月号 掲載
『Atlas of Small Animal CT and MRI』
2015年・Wiley-Blackwell発行・¥30,800(税込)
ついに待望のCT,MRIの教科書が出版された。
米国の放射線科専門医を目指すレジデントにとっても,CT,MRIを導入した開業の先生にとっても,強力な読影の手助けとなる実践書である。
University of California Davisの教育病院では,CT検査が毎年1000件以上,MRI検査が750件,(X線検査 8000件,超音波検査 6500件)実施されている。その中から著者のWisner先生が15年間にわたり収集した厳選700症例が掲載されており,われわれがCTやMRI検査で遭遇する症例が全てカバーされている。放射線科は表舞台に出ることのない縁の下の力持ちの診療科であるが,UC Davisの放射線科は,他の診療科と連携をとり,画像診断結果の裏付けがとれるシステムが構築されている。何より本書の特筆すべき点は,病理検査や臨床検査によって症例の最終診断が得られている点である。それゆえ,画像の説明にも説得力がある。
本書には「裏付けのとれた最終診断名」が,図のタイトルとして記載されており,目当ての症例を探しやすい。画像の直下に「CTかMRIか」,「撮像方法」,「造影」,「撮像断面」の情報と,「症例の動物種,年齢,臨床症状」が記載されており,続いて読影所見が述べられている。
ここでは,私の本書の使い方を紹介したい。まず,自分の症例の鑑別診断リストに挙げた疾患名を,索引で調べる。例えば,「脈絡叢癌」を索引で調べると掲載されているページが見つかる。 脈絡叢癌のページには,典型的な画像と読影所見が記載されている。その前のページに目をやると,脳室に発生する腫瘍に上衣腫が鑑別診断リストに挙がることがわかる。そして,脈絡叢癌は造影効果が均一で,上衣腫は造影効果が不均一との説明に,「あっ,そうだったのか」と納得する。また,脈絡叢癌と脈絡叢乳頭腫は,画像では区別できないことを読むと「あっ,そうだったのか」と再び納得する。さらに前のページの希突起神経膠腫を読むと,腫瘍の発生部位が異なることがわかる。こうして,芋づる式に知識がつながる。
今年の後期からは,本書を私の研究室のゼミの教材として使用する予定である。本文を一字一句訳すのは気が遠くなるので,付図説明を画像と照らし合わせながら訳していくことにした。画像と付図説明だけの輪読でも,この教科書を1冊読破したときにCTとMRI読影の全体像が見えてくるはずだ。また,読影所見を一度に覚えられなくても,特徴のある症例に遭遇したとき,この教科書に載っていたことを思い出せば,調べることができる。
最後に,私が留学中にお世話になった著者のWisner先生を紹介したい。Wisner先生は,UC Davisの放射線科,9名の教員,7名のレジデント,9名のテクニシャンの大所帯をまとめる大ボスで,米国獣医放射線学会の会長やVeterinary Radiology and Ultrasound誌の編集委員も務めた経歴がある。華やかな経歴にもかかわらず,人柄は温厚誠実で,放射線科のみならず他の診療科,事務職員も含めて,UC Davisで最も人望の厚い先生と言っても過言ではない。膨大な画像データと裏付けの写真を見てみると,この教科書の出版はWisner先生だからこそできた偉業とつくづく感じている。
「獣医畜産新報」2015年7月号 掲載
『Feline Medicine - Review and Test』
2014年・Elsevier発行・¥10,890(税込)
この本はソフトカバーで白衣のポケットにも入るハンディーなサイズで,しかも内容は豊富なカラー写真やデータもあり,持ち歩いて読むのに楽しそうである。
内容は症例に沿った診断アプローチのテストであり,第1章から9章まで,器官別,カテゴリー別の厳選された症例が示されている。器官別では,皮膚,消化器/肝臓,血液,呼吸器,泌尿器,内分泌,神経系,そしてカテゴリー別には中毒,創傷,その他の疾患というように分けられている。
各症例では,最初に患者プロフィール,ヒストリーが示され,次に身体検査所見が写真と共に提示される。ここから設問がはじまり,問題点の特定,鑑別診断リスト,イニシャルプランニングという順番で診断に向かってガイドされていく。診断が確定すると,次に治療に関する設問があり,最後に転帰や経過が説明されて1症例が終わる。
これはまさに欧米の大学病院における臨床教育を紙上で再現したものであり,診断の過程はともすればもたつくようなことはあっても,鑑別診断リストの中から追加検査によって絞り込むといった,決めつけ診断を許さない論理的なアプローチが教えられている。したがって,本書の意図する教育効果とは,POMRに沿ったアプローチを学ぶこと,そして猫の臨床で遭遇するやや難しい症例に触れることができる,といったものであろう。
内容は難しいと思うが,初心者を導く方法で記述されているため,英語能力さえあればついて行けるだろう。
「獣医畜産新報」2015年5月号 掲載
『Handbook of Veterinary Pain Management, 3/E』
2014年・Elsevier発行・¥13,200(税込)
獣医療において,内・外科を問わずもっとも重要な事項の1つが疼痛管理であることには異論はないだろう。しかし,重要であることが認識されているにもかかわらず,臨床現場で十分・適切な管理が行われているとは言えない状況にある。その理由は,この動物はいったい痛がっているのか具合が悪いのかよく分からないとか,いったい何をどうやってどのくらいの期間投与すればいいのか分からないとか,何度か鎮痛剤を投与したけど効いたかどうかよく分からなかった,などなど“よく分からない”ということが大きいと思う。今回第3版が出版された本書は,このもやもやに十分に答えてくれる完成度の高い教科書である。さらに本書は,痛みの基本についてより深く知りたいと考えている人たちにも十分答えてくれる最新の情報も満載している。
本書は携帯も可能なコンパクトなものであるが,その内容は驚くほど濃い。全体で28章から成っているが,最初の6章は痛みの基礎的な側面について述べられている。臨床的には,痛みの評価法について,様々な手法が詳しく述べられている章が大いに役立つだろう。一方で,痛みのメカニズムの最新情報がかなり詳細に述べられていたり,ストレスとの関係などについて記述されている章もあり,痛みの研究をやっている人あるいはこれらに興味がある人に貴重な情報を与えてくれる。
次の11章は疼痛管理に用いられる鎮痛薬あるいは鎮痛補助薬について述べられているが,これも他に類を見ないほど詳細で最新の情報が満載であり,効果,使用法だけでなく副作用やそれに対する対策もわかりやすい。驚くことに薬物動態学および薬物の相互作用についてもそれぞれ1つの章が割かれており,より深い理解に役立っている。この他レーザーや変動電磁場を用いた鎮痛についても書かれた章があり興味深い。
最後の11章は,鎮痛法の実際について述べられており,ここには鍼や運動療法/リハビリテーションについても触れられている。この部分においても漫然と鎮痛法が書かれているのではなく,いかに理論的により良い鎮痛に導くのかというコンセプトが生かされている。またケーススタディーを多用して読者の理解を深めようという努力がなされているし,犬,猫のみならずウサギ,フェレット,鳥,爬虫類,実験動物の鎮痛についてもそれぞれ章を割いて記載する力の入れようである。最後に多くの薬剤の投与経路や推奨投与量について表にまとめられており,これも大いに役立つだろう。ぜひこの1冊を手元に置いて頂いて,痛みに苦しむ動物たちが1頭でも減ることを願っている。
「獣医畜産新報」2015年4月号 掲載
『Canine and Feline Endocrinology, 4/E』
2014年・Elsevier発行・¥23,760(税込)
内科学全般の学習にも適した小動物内分泌病学のバイブル
常に手許に最新版を置いておくべき専門書を我々は尊敬の意を込めてバイブルと呼ぶ。他の領域と同様,獣医学にも数多くのバイブルが存在する。獣医内科学全般ではSJ Ettinger先生の『Textbook of Veterinary Internal Medicine』(現在,第7版)やRW Nelson先生およびCG Couto先生による『Small Animal Internal Medicine』(同じく第5版)は誰しもがバイブルと認めるはずである。そして,小動物内分泌病学のバイブルと言えば,世界中の誰もが本書を思い浮かべるに違いない。
本書の初版は1987年に発行され,今年に入って第4版が出版された。約30年の歴史をもつ本書の編集方針は一貫しており,それは内分泌疾患を網羅的に解説せず,小動物の医療現場で問題になることが多い。換言すると多発疾患に限定して解説していることである。具体的には,第1章では下垂体疾患のうち,特に水代謝および成長ホルモンの異常が扱われている。第2章は甲状腺疾患(亢進症および低下症)を,第3章は内分泌臓器としての膵臓の疾患(糖尿病とこれに続発するケトアシドーシス,インスリノーマ)を,第4章は副腎疾患(特に亢進症および低下症),そして最後の第5章は上皮小体疾患(亢進症および低下症)を扱っている。このように本書は小動物で頻発している内分泌疾患の理解に最適だと断言できる。本書の愛読者の1人としてもう1つ感じることは,内科学の広い理解にも本書は適しているということだ。例えば,第1章では水代謝が解説されているが,これは輸液療法の基礎になる。第4章ではステロイド剤療法が独立したセクションとして扱われている。そして,第5章ではカルシウム代謝の異常,つまり高カルシウム血症および低カルシウム血症が解説されている。これらは,いずれも臨床獣医師にとっては必須の情報・知識である。
本書は索引を含めると約650頁という大著なので,読み返しながら読破するのに相当な時間と労力を要すると思われる。以前なら翻訳出版が計画されたであろうが,出版作業に要する時間を考慮すると,情報が古くなる可能性が高い。そろそろ我々獣医師は,翻訳書に頼らずに英語の専門書を読みこなさなければならない時期に来ているのではなかろうか。
他のバイブルと同様,改訂を重ねるに伴って図表や写真は益々洗練されたものになっている。特に内分泌疾患では,外貌が特徴的な所見を示すことが多く,本書でもこのことを意識して症例の外貌の写真が多く掲載されている。最近,図表や写真はカラーになり,講義用にこれらの図版を利用するためのCD-ROMが添付されるのが当たり前になりつつあるが,本書では今回の改訂でもこの種の対応は施されていなかった。この点を些か残念に思うが,基礎的な整理事項に引き続き,各疾患の病態,診断および治療が丁寧に解説されている素晴らしい解説書であることに変わりはない。無論,愛読者の1人として本書の今後の改訂版の登場を楽しみにしている。

最後に,添付させて頂いた写真は2008年に開催された日本臨床獣医学フォーラム年次大会で講演するために来日・講演されたEC Feldman先生(中央)との写真である(右が石田卓夫先生,左が筆者)。この大会では,Feldman先生はスライドを使わず,会場を歩き回りながら,ホワイトボードを使いながら講義されていた。自身の講演の合間に私も参加させて頂いたが,この「昔はよくあった」スタイルのセミナーにとても新鮮な印象を持ったことを覚えている。加えて,スライドを駆使した今風のセミナーでは再現できない,心地の良い緊張感をもって参加者は勉強していたことが忘れられない。「素晴らしいテキストを編纂する専門家は良い講義をする。素晴らしい講義をする専門家は良いテキストを出版する」と,かつて私は師匠である本好茂一先生(日本獣医生命科学大学名誉教授)から伺ったことがある。Feldman先生はこのお言葉を見事に証明するお1人なのである。
「獣医畜産新報」2015年3月号 掲載
『Robinson's Current Therapy in Equine Medicine, 7th ed.』
2014年・Elsevier発行・¥30,910(税込)
日本では戦後馬の生産頭数の激減に伴い,馬の教育および研究の場が減少してきたが,サラブレッドに関しては生産頭数が世界第5番目のいわばサラブレッド生産大国とも言える。北海道の馬生産地や,本州の競走馬トレーニングセンター周辺,さらには全国の乗馬クラブ,等を対象とする馬獣医師の重要性は依然として高い。これら馬の使役目的や飼養場所が変わると,馬臨床獣医師が直面する病気や診療の種類も千差万別となり,対処方法も多種多様である。馬の繁殖等に関する臨床業務や,若馬の消化管疾患,呼吸器疾患等を身近に経験する環境もあれば,競走馬を対象とした独特のスポーツ医学,整形外科学,呼吸循環器病学等の幅広い知識が獣医師に要求されることもある。さらに,慢性的な病気に見舞われた愛馬の疼痛をコントロールし,最善の福祉を重視した治療の必要性もあろう。
1983年に初版が発刊され,今回で7回目の改定版となる本書は,馬の臨床家,研究者からなる200名近くの分担共著者が,日ごろの馬臨床現場で遭遇する種々の症状や疾患等について専門家の立場から診断,治療および対処方法をわかりやすく紹介した馬臨床学の総合書である。過去5年以内の最新の報告や知見,情報を含め,病気の診断・治療について全18章,212項目に分類して紹介している。馬の代表的な疾患である外傷,上部下部気道疾患,跛行,疝痛は元より,疼痛管理や鞍の選び方,病院におけるバイオセキュリティなど臨床現場に付随した重要となる項目が平素な単語を用いて具体的に説明されている,馬臨床獣医師必見の実用的臨床テキストといって過言ではない。付録頁には,薬物の投与量,投与方法が一目でわかる一覧表が簡潔に記載されているため,忙しい臨床家が短時間に鎮静薬,鎮痛薬,抗菌剤等の投与量を検索したい場合にはたいへん便利である。また,索引には病名のほかに,一般的な臨床症状や器官名も多く記載されており,臨床症状や器官名から病状や診断法を参照,検索できるように工夫されている点もありがたい。各項目では,疾患の原因や症状,診断法,治療法が簡潔に記載されているほか,深く検討したい読者のために参照すべき文献suggested Readingsを紹介することにより,限られた紙面を有効利用しながらも読者に優しい1冊となっている。
日本の獣医系各大学では,欧米に比肩する新しい獣医学教育体制の構築をめざし,欧米基準に則った馬臨床学の教育方法を確立することが喫緊の課題となっている。本書は,現役の馬臨床獣医師だけでなく,獣医系大学の臨床担当教員や馬に興味を持つ獣医系学生にも大いに推奨される。
「獣医畜産新報」2014年10月号 掲載
『Diagnostic and Surgical Arthroscopy in the Horse 4th ed.』
2014年・Elsevier発行・¥46,200(税込)
本書は馬の内視鏡診断と手術の第4版である。第3版が出版されたのは2005年であるから本書には馬内視鏡手術9年間の進歩と発展が含まれている。むろん変わらない内視鏡手術の基本はそのままに記載されているが,テクニックはより分かりやすく,写真と図は改善され,エビデンスが付加されている。
章立ては,内視鏡手術機器,内視鏡診断テクニックの総論に続いて,本書の主体である手根関節,球節関節,膝関節,足根関節,肩関節,肘関節,股関節,趾(指)節間関節の関節内視鏡手術の各論になっている。各論では診断のための関節への複数のアプローチ法,各アプローチからの病変別の手術法がすべてカラーの内視鏡像と図版およびX線像で解説されている。さらに各論では腱,滑液嚢などの軟部組織の内視手術,感染性関節と軟部組織の内視鏡,内視鏡による関節軟骨の修復法の章がある。全体のページのおよそ6~7割は写真と図版で占められている。本文は簡潔で読みやすいが,ややフォントサイズが小さく詰まっているので見にくいのが難である。写真と図をふんだんに盛り込み,450頁あまりのそう分厚くない本書に収めるためにはいたしかたないだろう。第4版では新しく内視鏡手術後の管理・補助治療・リハビリが最終章として付け加えられている。その記述はとくに手術後の長期的管理に向けられているが,わずか5頁の情報の羅列なので臨床的評価やエビデンスなどの科学的評価には至っていない。今後,この領域の進展に期待するべきだろう。
人と同じように,馬の内視鏡医学の目覚ましい進歩は運動器病医療をより非侵襲的なものに大きく変えたばかりか,新しい病変,病態の発見と考え,そして各部位の内視鏡治療が次々と実現し,エビデンスが蓄積され… というふうに進行形であることもよくわかる。人では整形外科疾病の診断は内視鏡よりCTやMRIに移ったが,馬では関節だけでなく軟部組織をも含んだ内視鏡診断・治療の医療革命の時代である。内視鏡による詳細で新しい画像診断が進み,普及してくることは獣医師にとっても馬のオーナーにとってもすばらしいことではあるが,功罪共にあることも,そのオーバーユーズゆえに指摘されている。内視鏡手術適応例を適切に選ぶ診断の重要性,テクニック失宜,医療費の高騰,罹患予防への関心低下問題などもあろう。とはいえ,内視鏡診断・手術は様々な意味において医療をさらにポジティブなものに変えて行くだろう。本書は新しいを超えた進歩を示していて,見て・読んで楽しい。本書購入者はインターネットからアクセスして,内視鏡手術のビデオクリップを閲覧することができる。
「獣医畜産新報」2014年9月号 掲載
『Fowler's Zoo and Wild Animal Medicine, Vol. 8』
2014年・Elsevier発行・¥31,130(税込)
野生動物医学や動物園医学の分野では,よく知られている専門書の新版である。第1版と第5版の翻訳書は,『野生動物の獣医学』(1984年)と『野生動物の医学』(2007年)の邦題で文永堂出版から発行されている。これまで本タイトルの書は,野生動物と動物園動物の医学に関する包括的な内容の版と今日的な獣医学治療のトピック情報を集めた版が,数年毎に交代で出版されてきた。この新刊書は,前者にあたる第8版である。第1版が1978年発刊だから,4年半の間隔でほぼ定期的に刊行されていることになる。しかしこの第8版には,単に定期出版物だけではない特別な意味合いがある。それは,書名にも冠されているDr. Fowlerが編集された,おそらく最後の書であることだ。野生動物医学の権威であった Dr. Murray E. Fowler は,2014年5月18日に惜しくも亡くなられた。彼が残した多くの業績については,すでに学術誌上やネット上などに記されているので省くが,もっとも大きな業績のひとつが本書の出版であり,その名を世界中の野生動物医学関係者に広めるきっかけにもなった。
このようにDr. Fowlerを知る者にとって特別な1冊であるが,野生動物の獣医学や生物学に関する最新情報を詳細に紹介するという,これまでの方針は踏襲されている。第6版からのカラー印刷も継承されている。序文にも書かれているとおり,野生動物医学の問題は地域や国境を越えたグローバルなものであるため,15か国の動物園や研究機関から執筆者が選ばれている。アジアからは,台北市立動物園の金仕謙園長が選出され,センザンコウ目(Pholidota)の記事を担当している。
包括的な内容であると冒頭に記したが,本書の項目は動物分類の網(Class)別に分けられている。すなわち,Part Iでは両生網の医学,以下Part II から IVで爬虫網,鳥網,哺乳網の医学,そして最終章のPart Vでは一般的な野生動物医学に関する最新情報が提供されている。各網別の章は,さらに動物分類の目(Order)別に新知見が記載されている。たとえばコウノトリ目の項を例に挙げると,包括的な前書である第5版とは執筆者が異なり,内容も引用文献も大幅に更新されている。とくに最終章では,近年発展が著しい臨床技術やネット情報も含め,診断・治療に役立つ最新情報が紹介されている。日進月歩の野生動物医学に関わる獣医師や研究者は,数年ごとに繰り返される出費が辛いかもしれないが,本シリーズの最新刊を購読して,そこに記されている知見を野生動物保全のための臨床や研究に活かすべきだと思う。
「獣医畜産新報」2014年9月号 掲載
『Current Therapy in Reptile Medicine and Surgery』
2013年・Elsevier発行・¥25,960(税込)
本書は,2006年に刊行された『Reptile Medicine and Surgery』の第2版(獣医畜産新報2006年6月号に書評掲載)のcurrent edition,すなわち”現行版“である。
『Reptile Medicine and Surgery』は,1996年に初版が発行され,このときもすでに500頁を超えていたが,第2版は1242頁にも及ぶ大部の書となっている。飛躍的に発展した爬虫類の獣医学の発展を盛り込んだ成果である。この第2版は,爬虫類の生物学や飼育法,解剖学,生理学,行動学から臨床検査,各種の疾病への対応まで,まさに爬虫類に関する獣医学の集大成といえるものであった。
ここで,この『Reptile Medicine and Surgery』について改めて述べておきたい。現生の爬虫類はカメ目と有鱗目(トカゲ亜目とヘビ亜目),ワニ目,ムカシトカゲ目の4つの目(order)に分けられている。このなかで診療の対象になるのは主にカメ目と有鱗目であろう。そのため,爬虫類に関する獣医学書は,カメ類,トカゲ類,ヘビ類と分けて記載していることが多い。しかし,この書物では,動物のグループごとの記載を避け,爬虫類を全体としてとらえ,たとえば循環器疾患,皮膚疾患,感染症というように,疾病ごとの記載が中心になっている。しいていえば,哺乳類の獣医学として一括して扱っているようなものである。この点からすると,いささか乱暴な,といえなくもないのだが,爬虫類の獣医学の入門としてはこうした記載が好ましいのかもしれない。『Reptile Medicine and Surgery』は大冊であり,詳細に記載されてはいるが,位置づけは入門書であると私は思っている。
さて,今回の”現行版“であるが,第2版出版以降の新たな知見を加えたほか,両生類についても詳述され,さらに保護などに関してもページを割き,新知見をもって書き直したというよりも,第2版の”補遺“としての色彩が強くなっている。
本書は4部からなる。第1部は爬虫類の獣医学,第2部は麻酔法と外科的処置,鎮痛法,第3部は両生類の獣医学,そして,第4部は爬虫類と両生類の生物学と保護,法令,研究について,それぞれ最新の情報を記載している。CT検査やMRI検査,超音波検査,内視鏡を用いての検査や処置など,臨床に直結する内容も多いが,第1部には「爬虫類の進化に関する臨床的側面」という章も設けられていて,基礎の研究者にとっても興味深いものになっている。さらに付録もあり,爬虫類に関する原著論文をいかに評価するかという,少し変わった内容の記事や,爬虫類を宿主とするウイルスの一覧,薬用量,臨床検査値の基準値などが掲載されている。
この”現行版“,やや高度で難解な部分もあるが,とてもよい書物であると思う。先の第2版とあわせて,爬虫類と両生類の診療に役立てていただきたい。
「獣医畜産新報」2014年5月号 掲載
『Piermattei's Atlas of Surgical Approaches to the Bones and Joints of the Dog and Cat 5th ed.』
2014年・Elsevier発行・¥23,100(税込)
本書は犬と猫の骨関節外科手術(骨関節外科,脊椎外科)に必要なアプローチ法を網羅した極めて臨床に即したハンドブックである。本書の特徴は,それぞれのアプローチ法について,患者の手術台への固定法,切皮部位を図示し,筋肉の切開,切離部位を骨との位置関係,周囲の血管,神経の走行などの重要な局所解剖を含めた詳細なイラストを用いて,骨関節に到達するまでの過程を段階的に示している。
本書は1996年にDonald L. Piermatteiが初版を発刊して以来,獣医整形外科の進歩と共に少しずつ改定されてきた。第5版ではDonald L. Piermatteiは退き,2004年の第4版から共著者として加わったKenneth A .Johnsonが著者となった。本のタイトルには『Piermattei’s Atlas of Surgical Approached to the Bone and Joints of the Dog and Cat』と名前が刻まれ,初版の発行以来,第4版まで40年以上にわたり本書籍の内容を発展させてきたPiermatteiへの強い敬意が伺える。Kenneth A .Johnson はとりわけ整形外科分野で高く評価されるACVSおよびECVSの専門医であり,近年はVeterinary Surgery誌と並び,獣医整形外科分野で最も権威のあるジャーナルであるVCOT(Veterinary and Comparative Orthopedics and Traumatology)誌の主任査読者を務めている。
第5版の内容をみると,第4版からの変更点として,第3~6頸椎への側方アプローチ法,腰仙椎椎間板への経腸骨骨切り術による側方アプローチ法,肩関節へ内方アプローチ法,上腕骨内側顆および内側鈎上突起への筋間アプローチ法,膝関節内尾側および内側側副靱帯へのアプローチ法など,近年実施されるようになった新治療法に必要なアプローチについての詳細なイラストが追加された。また,近年一部の整形外科医により開発,推奨されている脛骨,上腕骨,大腿骨の骨幹部骨折に対する最小限侵襲による骨接合法(minimally invasive osteosynthesis of diaphyseal fractures)に使用されるアプローチ法を紹介していて,整形外科医の間で評価の分かれる本手術法が一定のお墨付きを得たとの印象を受ける。さらに猫の上腕骨外側顆,股関節,大腿骨等へのアプローチ法が追加され,猫と犬の局所解剖について,僅かであるが厳密な違いが詳細に説明されている。
本書は初版から多くの整形外科医に愛用され,本書を持たない獣医整形外科専門医はいないといっても過言ではなく,必須の書籍である。私自身,アプローチ法を再確認する際や若手スタッフの指導の際に頻繁に本書を愛用している。
「獣医畜産新報」2014年4月号 掲載
『Kirk's Current Veterinary Therapy XV』
2014年・Elsevier発行・¥26,180(税込)
最新版のバイブルで知識の更新を
その分野に従事する者が絶対に手許に置かねばならない書籍のことを我々はバイブルと呼ぶ。
私が高校生の頃(昭和54年),近所の動物病院にお邪魔した際に,話し好きの院長先生が「僕らはね,こんな分厚い本を夜中まで必死に読んで勉強しているんだ」とぼろぼろになった本を見せて下さった。それが『Current Veterinary Therapy』 (CVT)の翻訳書である『小動物臨床の実際』だったことを知ったのは,数年後に私が日獣大に入学して直ぐのことだった。
Dr. Ettingerの『Textbook of Veterinary Internal Medicine』,Dr. Slatterの『Textbook of Small Animal Surgery』とならんで, CVTも伴侶動物医療の世界ではバイブルである。
2009年に発行されたCVT14から5年ぶりとなる今年になってCVT15が発行された。寄稿者数は約400名である。日本人獣医師にとっては,この中に3名の日本人獣医学者が含まれていることは非常に名誉なことである。
CVT15はこれまでと同様,クリティカル・ケア,中毒,内分泌・代謝性疾患,腫瘍・血液病,皮膚病,胃腸疾患,呼吸器疾患,心疾患,泌尿器疾患,生殖器疾患,神経疾患,眼科疾患,感染症という13のセクションに分けて記載されている。
このうち,筆者の目を引いた中毒のセクションでは,一般家庭でよく見られる有毒植物トップ10という章 (chapter 28) があり,それによると,アロイド(サトイモ科)は口腔刺激,カランコエ,シャクナゲ,セイヨウキョウチクトウおよびイチイは心毒性を,ユリおよびブドウ(レーズンを含む)は腎毒性を,そしてイヌサフラン(別名コルチカム),ヒマの種およびサゴ草は重篤な胃腸または肝障害を引き起こすと記載されている。また,別の章 (chapter 29) ではハーブの有害事象が扱われている。
言うまでもなく,伴侶動物医療は急速に進歩している。小動物臨床獣医師は情報に溺れていると言った方が正確かもしれない。このような状況にあって,その分野のエキスパートが平均して4~5頁で各章を要領よく解説するという,本書の編集方針はこのCVT15でも引き継がれていることは,多忙を極める臨床家にとって有り難いことである。内容が内科疾患に偏っている傾向があるように感じられるが,ベテランであろうがルーキーであろうが,獣医師である以上,本書を常に手許におき,必要な箇所や興味のある章から読み進めることで,正確な知識を効率よく追加・更新するのに格好の書である。ご一読を強くお勧めしたい。
「獣医畜産新報」2014年4月号 掲載
『Equine Infectious Diseases 2nd ed.』
2014年・Elsevier発行・¥28,710(税込)
世界的に見ると馬は主要な家畜のひとつであるが,日本では,馬の飼養総数は8万頭程度にすぎず,馬の感染症の専門家も数少ない。2007年に出版された第1版を手にしたとき,馬の感染症に特化した成書が600頁もあることにまず驚かされた。第2版では著者が一部変更されているが,全体のボリュームや構成は第1版をほぼ踏襲している。
本書は6節と付録で構成されている。第1節は,呼吸器,消化管,中枢神経系,生殖器系など部位別の感染症の解説9章と,炎症反応と子馬の敗血症の計11章から構成されている。この節は,臨床獣医師が馬の感染症の知識を得ようする場合に役に立つ項目であろう。第2から第5節は,それぞれウイルス,細菌,真菌,寄生虫(外部寄生虫も含む)の馬感染症の病原体別の各論である。各節の最初の章には,その節の病原体の実験室内診断法に関する記載があり,その後に個別の感染症の章が続いている。主要な感染症では,多くのカラー図版を含む10数頁にもおよぶ詳細な記述がなされている。第6節は,疫学総論,馬の感染症の予防,管理,治療に関する章から成っている。付録には症状別の感染症一覧,診断機関一覧(残念ながら米国のみである),抗菌薬の処方などが記載されている。
本書には文献リストは掲載されていない。Elsevierが最近発行している他の専門書と同様に,購読者は本書のWEBサイトにアクセスして,本書の文献リストを見ることができる。数え間違えていなければ全部で7,800件近い文献がリストアップされており,それぞれPubMedの文献情報にリンクしている。また本書に掲載されている574ものカラー図版と付録もWEBサイトでみることができる。最近はこのような形式が普通なのであろう。ちなみに前版ではCD-ROMが付録としてついていた。
本書には,およそ馬の感染症の原因として知られている病原体は網羅されており(もちろん個々の記述量には大きな違いがあるが),獣医系大学の学生だけではなく,研究者や臨床獣医師など,馬の感染症について何か調べようとする全ての者に役に立つであろう1冊である。
「獣医畜産新報」2014年3月号 掲載
『Ophthalmology of Exotic Pets』
2012年・Wiley-Blackwell発行・¥17,050(税込)
動物医療における診療科には,内科や外科,眼科,皮膚科など,医療の場合と同様の区分のほか,猫の診療とか,エキゾチックアニマルの診療あるいはウサギの診療,鳥の診療というような分け方も成立する。ただし,この2つの観点からの分け方が併用されることは少ない。たとえば,「猫の病院」はあるし,「(動物の)眼科の病院」もありうるとしても,「猫の眼科の病院」は成り立ちにくい。これは,それだけの社会的な要求(いいかえれば市場)がないからにほかならない。
ここに紹介する『Ophthalmology of Exotic Pets』は,邦訳すれば『エキゾチックペットの眼科学』ということになろうか。従来,獣医学領域の眼科に関する書物もエキゾチックアニマルの診療に関する書物も,数多くが出版されているが,エキゾチックアニマルに関してここまで細分化された書籍は,本書のほかには,『Skin Diseases of Exotic Pets』(Peterson S,Wiley-Blackwell,2006)〔邦訳『エキゾチックペットの皮膚疾患』(小方宗次 監訳,文永堂出版,2008)〕など,ごくわずかである。だが,こうした書籍が上梓されるということは,エキゾチックアニマルの診療が確固たる地位を占めてきたことを感じさせる。
さて,本書の内容であるが,比較眼科学の歴史とエキゾチックアニマルの眼科学に関する総論的事項に続いて,その後は動物の種ないしはグループごとの眼の解剖学と生理学,視覚の特性,そしていくつかの疾病に関する臨床的な解説となっている。取り上げられた動物は,掲載順にいうと,ウサギ,モルモット,フェレット,ラットとマウス,その他の哺乳類(ハムスター類,スナネズミ,チンチラ,デグー,ハリネズミ類,霊長類),鳥類,爬虫類,両生類,魚類であり,脊椎動物が広く扱われている。
だが,この書物を読んでも,それだけでは,エキゾチックアニマルの眼科診療を十分に理解できるまでには至らないように思われる。前もって眼科に関する基礎知識を有する必要がある。本書は,眼科にある程度は精通した獣医師が読者であることを想定しているのではないだろうか。つまり,この書物は,眼科の診療を中心に行っている獣医師がエキゾチックアニマルについても診療の領域を広げたいときには有用であろうが,エキゾチックアニマルの全科診療を行っている獣医師が得意とする領域を眼科にも広げるために読むとすれば,眼科に関する一般的な(つまり犬と猫の眼科学に関する)書物と併読する必要があろう。
だが,本書には,診療と離れて,もう1つの価値がある。動物の眼や視覚について進化と関連して系統的な理解を得たいとき,本書は優れた参考書になるにちがいない。この意味で,動物の眼の進化について興味深い記述がある『The eyes』(堀内二彦,創英社/三省堂書店)と併せて読まれることをお奨めしたい。
「獣医畜産新報」2014年3月号 掲載
『Essentials of Tortoise Medicine and Surgery』
2013年・Wiley-Blackwell発行・¥11,770(税込)
カメ類は,爬虫綱のなかで1つの目を形成する。その最大の特徴は甲羅を発達させたことであろう。およそ300種があるといわれるカメ類のすべてが甲羅を有している。だが,こうした共通の特徴があるとはいえ,それらの生活の場は様々で,水・陸両方の多岐にわたり,ひとくちにカメといっても色々である。
さて,こうしたカメ類の呼称だが,日本語ではカメ(亀)といい,例外としてスッポン(鼈)だけは別になっている。スッポンは甲の表面が滑らかなため,他のカメ類とは異なる動物だと思われたにちがいない。一方,英語では,水棲ないし半陸棲のカメ類をturtleといい,その一部の種はterrapinと称し,また,陸棲のカメ類をtortoiseという。日本語でtortoiseに相当する言葉が生まれなかったのは,日本には陸棲のカメが分布していなかったからである。英語でtortoiseといわれるカメ類は,現在,日本語ではリクガメといわれている。
では,本書『Essentials of Tortoise Medicine Surgery』を紹介したい。書名のとおり,この書物はtortoise,すなわちリクガメ類の臨床に関するものである。内容は2部の構成になっており,第1部は,リクガメ類の生物学や飼育法,診療を行うために必要な準備,血液学的検査や血液生化学的検査,寄生虫の検査などの種々の検体検査のほか,画像診断,麻酔法,その他を簡単に解説している。また,第2部は,各種の疾病への対応についての記載だが,主に症状ごとにまとめられていて,食欲低下,下痢,呼吸の異常,というふうに各項目が続いている。
これまでにも,カメ類の臨床に関する多くの獣医学書が上梓されている。ただし,ほとんどは,エキゾチックアニマルないしは爬虫類に関する書物のなかでの記載である。カメ類だけを扱った書物もあるが,それらもある特定のグループに限ったものではなかった。これに対して,本書はリクガメ類だけに焦点をあて,その診療に際して必要なことを簡単にまとめている。
完全な水棲のカメと半陸棲のカメ,陸棲のカメでは,飼育法がまったく異なり,好発する疾病や基本的な診療手技も大きく異なっている。したがって,陸棲のカメの診療を行うにあたっては,それに応じた方法によらなければならない。もちろん,『Medicine and Surgery of Tortoise and Turtles』(McArthur S, Wilkinson R and Meyer J,Wiley-Blackwell,2004)のような大部の書物をみれば,リクガメ類に関しても詳述されているのだが,簡単に済ませたいときには,どうしても簡略に書かれている書物を読みたいと思うものである。とりあえずリクガメ類の診療を行いたいが,あまり詳細な書物は読みたくない,といってカメ類の全体について略述している書物では不十分,リクガメ類だけに限って基礎的な知識を得たい,というようなときに本書が役に立つと思う。
「獣医畜産新報」2014年3月号 掲載
『Clinical Veterinary Advisor: Birds and Exotic Pets』
2012年・Elsevier発行・¥17,490(税込)
エキゾチックペットの診療について記した750頁以上に及ぶ大冊である。収載されている動物は,掲載順にあげれば,無脊椎動物,魚類,両生類,爬虫類,鳥類,小型哺乳類〔ラット,モルモット,ハムスター類,スナネズミ,チンチラ,プレーリードッグ(オグロプレーリードッグか?),デグー,ハリネズミ類,フクロモモンガ〕,そしてウサギ,フェレットと,まさにエキゾチックペットといわれる動物をほぼ網羅している。ただ,リス類に関する記載がないが,これはこの動物が海外ではペットとして一般的ではないからだろう。
内容は6つの部分からなり,第一に,上記の各々の種ないしはグループの動物にみられる各種の疾病が概説されている。疾病によって記載に軽重はあるが,原因から診断,治療,予後など,一般的な事項はおおよそ網羅されているといえる。この部分は,頁数でいえばおよそ500頁,この書物のおよそ2/3を占め,本書の中核をなしている。
この後は,動物種またはグループごとの検査法や処置法,鑑別診断,臨床検査(検体検査),いくつかの動物種とグループに関して各症状への対応のアルゴリズム(手順),人と動物の感染症と,5つの項が続いている。
ここで,対応のアルゴリズムの項について簡単に説明しておくと,たとえば小型哺乳類の慢性的な体重の減少というところでは,まず初めに,慢性的な体重の減少がみられた場合の食餌摂取量を減少,増加,不変の3つに分け,続いてその3つのそれぞれに関して所見を分けていく操作をフローチャート様の図で示している。こうして診断に至ることができればよいということだろうが,しかし,実際はそれほど単純ではない。この項は,実際の症例の個々の診断に役立てるというよりは,診療の流れを考えるために活用するのがよいと思う。
さて,この書物の特徴は箇条書きで記載されていることである。本書は,判型がA4判と大きく,頁数も多く,文字もそれなりに小さいのだが,箇条書きであるために比較的読みやすくなっている。だが,このことは逆に,エキゾチックアニマルの診療を基礎から理解するためには不向きともいえるかもしれない。エキゾチックアニマルの診療について定評のある書物,たとえば『Ferrets, Rabbits, and Rodents: Clinical Medicine and Surgery 3rd ed.』(Quesenberry KE and Carpenter JW, Elsevier,2012)などを読み,ある程度の基礎的な知識を得たうえで本書を用いてその知識を整理するのがよいのではないだろうか。
なお,本書にはそれなりの数の写真が収載されているが,すべてモノクロ印刷なのが残念である。しかし,この大きさの書物の価格を抑えるためには,いたしかたのないところでもあろう。
「獣医畜産新報」2014年3月号 掲載
『Atlas of Canine and Feline Peripheral Blood Smears』
2014年・Elsevier発行・¥13,970(税込)
本書は,臨床獣医師が犬猫の血液塗抹を観察する際,顕微鏡の傍らにおいて必要に応じて参照することを念頭に作られたアトラスである。本書を利用するにつれ,その目的を達するために非常に良く考えて作られていると感心する。まず頁をめくって驚くのがその写真の豊富さである。本は片手で持てるB5版ぐらいのサイズであるが,1頁につき最大8枚の写真が載っており,本全体では1000枚以上の写真が掲載されている。その写真のクオリティーはどれも高い。特記すべきは,写真毎の注釈がない。これは臨床現場で日々使うことを考慮しているためと思われる。忙しい現場ではいちいち写真の注釈など読んでいる暇はない。
本書では大抵見開きで1トピックを扱っており,左頁の最初の部分で詳しいながらも非常に要点を得た説明がなされている。大赤血球症の項目を例に挙げれば,まず大赤血球症を見分けるための特徴が短い一文で定義され,次の段ではどのような診断意義があるかを説明している。さらにこの本でユニークなのが,大赤血球と判断したら次に臨床獣医師がするべきことを解説している。この解説は非常に実践的で臨床現場で重宝されるであろう。このような文字による解説は左頁の上部で終わり,あとは残りの1頁半をフルに利用して関連写真が掲載されている。大赤血球症の項目なら大赤血球の例として10の写真が載っている。これは大赤血球を見慣れない者にとっては非常にありがたい。よくある血液のアトラスで例として挙げられる写真は1枚か多くてもせいぜい数枚程度である。この場合,自分が実際に見ている像が写真と若干違ってみえると確信をもって判断ができない。同じ像であっても多数の異なる細胞の写真をみることでバリエーションの範囲を理解し,経験不足からくる判断の迷いを少なくできる。また,項目によっては,慣れないと判断を迷う像の比較写真が載っており(例えば小リンパ球と有核赤血球など),これもこの本の大きな特徴となっている。
この本で解説されるトッピックは非常に細かく多岐に渡る。血液の異常所見だけでなく,正常像,血液塗抹を観察するときのポイント,あらゆるアーティファクトも取り上げており,かゆいところに手が届く感じである。血液学を学びはじめの頃にこの本に出合っていればどれほど楽だったかと思い,これからこの本を手にする獣医学生に嫉妬する。
本は見開きでそのまま置けるリングバインダー式で,頁はめくりやすく,多少濡れてもすぐに拭けば良い素材を採用している。また裏表紙の余白部分が折り返されていて,しおりの代わりになるような工夫もされている。臨床現場で活躍することは間違いない本である。
「獣医畜産新報」2014年2月号 掲載
『Feline Soft Tissue and General Surgery』
2013年・Elsevier発行・¥23,210(税込)
最近外科関係の教科書で,小動物の軟部組織外科だけを扱うものが次々と出版されているが,中には腹部だけのものや,腹部をさらに部位ごとに分けたものも含まれている。獣医療の専門化が急速に進んでいる中で当然の流れと言えるが,これらの本には原則犬と猫の両方が含まれている。これまでも猫に特化した教科書は数冊出版されているが,猫の軟部組織外科だけに限ったものは,知る限りでは本書が初めてである。犬と猫の両者を扱う外科の本では,どうしても手術数の多い犬が主体となり,猫に関してはおまけ程度という場合も少なくない。しかし,よく言われるように猫は小さな犬ではない。もちろん基本的なところは共通している部分も多いが,取り扱いや評価法はずいぶん異なるし,解剖や生理も異なる点が数多くある。また,猫に特徴的な疾患の手術もある。さらに最近では猫の飼育頭数の割合が増えてきており,猫で行われる手術数も大幅に増えていくものと思われる。このような状況下で,猫に特化した軟部組織外科の書が出されたのは世の必然と言えるかもしれない。
本書は2009年に出版された『Feline Orthopedic Surgery and Musculoskeletal Disease』と同じ出版社から出された本で,ヨーロッパテイスト溢れる大変魅力的な1冊である。編者の3人は英国人(英国の機関所属),著者もヨーロッパ人が主体で,これに米国人が加わった陣容となっている。本書を開いてみるとまず目に付くのが,ふんだんに用いられているカラーのイラストや写真である。もちろん術式の写真もたくさんあるのだが(術式を主に写真で説明するのはヨーロッパの本に多いようだ),猫の描画や写真がたくさんある。これが,猫の性格やしぐさをよく捉えたもので,猫好きにはたまらない。とくに描画は秀逸のものが多く,編者や筆者たちの猫への愛情がよく出ている。
本書は700頁を超える,ボリュームのある1冊で,特殊なものを除いて必要な軟部組織外科手術がほぼ網羅されている(脳外科も含まれているので,特殊なものも含まれていると言ってよいかもしれない。とくに経蝶形骨洞下垂体摘出術まで載っているのには驚いた)。本書は7つの章に分かれ,第1章では周術期管理すなわち術前評価に始まり,麻酔・鎮痛,術後管理,栄養管理,輸血について,第2章では猫への対応法(待合室や入院室のこと扱い方など),画像診断や内視鏡検査,手術に必要な器具,用具,消耗品などについて,3章では腫瘍外科と補助療法について述べられており,それに引き続き4章から7章で皮膚や皮膚付属器官の手術(注射部位肉腫含む),腹部手術(開腹術,内視鏡手術,ヘルニア,消化管,肝臓,内分泌器官,泌尿生殖器の手術),胸部手術(開胸術,内視鏡手術,胸壁,横隔膜,呼吸器,心臓の手術),頭頸部の手術(耳,咽喉頭,甲状腺,鼻,口蓋,上・下顎,眼瞼・眼窩,脳の手術)について詳細に述べられている。これらすべてが猫に特化したものであり,その情報量は驚くべきものがある。ぜひ手元に置いて日々の診療・手術に役立てたい。獣医療にまた1つ新しい幕が上がったという感を強くさせる1冊である。
「獣医畜産新報」2014年2月号 掲載
『Llama and Alpaca Care
Medicine, Surgery, Reproduction, Nutrition, and Herd Health』
2014年・Elsevier発行・¥25,960(税込)
本書は,ラクダ科の動物であるラマとアルパカに関する獣医学書である。どうして,これら南米産の野生動物を対象とした獣医学的専門書が発刊され,その書評が国内の獣医学誌で紹介されるのかと訝しく思われる読者も少なくないと思う。しかし,ラマやアルパカは世界中で家畜として広く利用され,動物園や観光牧場では展示動物として飼育されている。国内の動物園でも,かれらの姿を見ることはそれほど難しくなく,ラマは33動物園に170頭が,アルパカは9動物園に28頭が飼育されている(2012年末現在)。その他にも全国各地のふれあい牧場やアルパカ牧場などで飼育されていているから,その数を合せると優に1,000頭を超えるかもしれない。とくにアルパカはインターネットで検索すればすぐに分るだろうが,子どもたちのみならず大人にも人気の動物になっている。このような現状であるから,いつ何時,ラマやアルパカに関する動物相談が寄せられるかもしれないし,診療を依頼されるかもしれない。実際すでに診療に携わっている開業獣医師や動物園獣医師がいる。そのような訳で,本書が国内で販売されることは全く可笑しくないし,反対に関係者にとってはとても有難いことである。
最初に獣医学書と記したが,本書の第1章(Part1)では7節(Chapter)にわたり飼育管理方法や保定方法や捕食者への対応策などが解説され,第2章では6節にわたり栄養学に関する解説がなされている。さらに第3章では,繁殖に関する解説が16節にわたり解説され,全頁の35%を占める277頁が充てられている。このことからも,家畜としての本種の重要性が理解できるであろう。第4章から第7章までは,獣医学的健康指針,疾病学,麻酔学そして外科学について解説されている。つまりこの1冊を読めば,ラマとアルパカの飼育や健康管理の全体が十分に把握できるようになっている。しかも,ほとんど全ての図版がカラーであり,各タイトル文字も色分けされ読みやすくレイアウトされている。40年以上前にモノクロの獣医学書で学んだ筆者には隔世の感がある。これまで,牛の医学書を参考にして治療にあたっていた獣医師が本書を読めば,ラマとアルパカの獣医療に対する考え方が大きく変わるかもしれない。
本書の執筆に関わった獣医師や研究者は53名である。海外における野生動物や動物園動物分野の研究者層の厚みに驚きを感じずにいられない。翻って我が国を眺めると,日本産野生動物の一種に特化して789頁ものボリュームある本書のような獣医学書が出版できる現状ではない。動物園動物や野生動物の医学を,国内でさらに発展させる必要があると,本書を手に取り改めて痛感した。
「獣医畜産新報」2014年2月号 掲載
『Clinical Veterinary Microbiology 2nd ed.』
2013年・Elsevier発行・¥21,670(税込)
1994年の初版から19年を経て第2版が完成した。全6節69章で構成される901頁に,獣医領域において問題となる重要な感染症の基礎,臨床症状や診断法などが,網羅的かつ詳細にまとめられている。
第1節(1~6章)は,総論的な内容であり,診断用サンプルの採取方法から,病原体の培養・分離方法,それらの生化学的,血清学的,遺伝学的同定方法について記載される。細菌病原体に対する染色法や培地の選択,同定のための生化学試験などの鮮明な写真資料,診断フローチャート図など大学での獣医微生物・伝染病学の講義や実習,また研究・行政機関での教育にぜひ活用すべきである。さらに,遺伝学的診断法や抗菌薬に関する最新情報は,実際の病性鑑定や治療に携わる獣医師にも高く貢献するであろう。
細菌感染症に関する第2節(7~36章)では,主に病原細菌種毎の章立てからなる。各章とも,各細菌種の基礎性状や病原性因子についての最新知見から,病原体の同定・診断法の解説という流れで構成されるが,その教科書レベルを超える充実した内容はアドバンス教育や研究者の興味にも対応できる。マイコプラズマ,クラミジア,リケッチア感染症もこの節に含まれる。
第3節(37~44章)は真菌感染症,第4節(45~67章)はウイルス感染症に関する解説である。真菌の形態学的検査法では豊富な写真や図が理解をサポートし,実際の診断時における利用価値は高いであろう。ウイルスの節では,ウイルス科毎に章立てされそれぞれ獣医領域で問題となる感染症を網羅する。各感染症は,概説から始まり,病原性そして診断法という共通した項目で記載される。一部の感染症ではウイルス学的性状についての踏み込んだ記載も見られるが,あくまで診断法をメインにコンパクトにまとめられており,臨床診断の場のみならず,講義のための教科書的な使用にも最適である。プリオン病もこの節に含まれる。
第5節(68章)は人獣共通感染症という括りでウイルス,細菌感染症などを非常にわかりやすく表にまとめてある。また,原虫感染症についての附表もあり,獣医師が扱う広い範囲の人獣共通感染症について俯瞰し,理解することが可能である。第6節(69章)では,感染症を動物(家畜)毎にまとめた表で構成される。全て病変や症状から想定される病原体とその診断法をウイルス,細菌を問わずまとめており,鑑別診断に大いに役立つ内容である。
以上,本書の構成,特徴をまとめたが,教育の場,臨床・病性鑑定の場,あるいは研究の基礎資料などいろいろなシーンでの活用が予想される。総じて,本書に匹敵する既存の和書は存在せず,英文も平易であるのでぜひとも推薦したい1冊である。
「獣医畜産新報」2014年2月号 掲載
『Veterinary Anaesthesia 11th ed.』
2014年・Elsevier発行・¥20,020(税込)
Hall & Clarkeの『Veterinary Anaesthsesia』が最新の情報を伴い11版となって帰ってきた。第10版の出版が2000年だったので,すでに13年が経過したことになる。ちなみに9版はその9年前の1991年,第8版は1983年の出版なので,改版の間隔はそこそこ長く,初版からは相当な年数が経過しているに違いない。そう考えると本書は,綿々と受け継がれてきた近代獣医麻酔学の伝統を汲む本と言ってよいのだろう。何と言っても本書はAnaesthesiaでありAnesthesiaではない。
本書の編者は上記2名にもう1人Dr. Trimも加えた3名だが,ついつい9版までのHall & Clarkeで呼んでしまう。麻酔の教科書として双璧をなす『Lumb & Jones’ Veterinary Anesthesia and Analgesia』と区別するためでもある(残念ながら1927年生まれのDr. Hallは2010年に亡くなっている)。本書は,麻酔・鎮痛学を学ぶ獣医学生に向けて書かれたものであり,また日々麻酔を行っている臨床獣医師あるいは動物実験に携わる人の参考図書として,またより専門的な道を目指す人のきっかけを作る書として工夫されている。獣医学生にとっては麻酔のコンセプトを分かりやすく理解でき,またどのように麻酔をすればいいのかを明確に学ぶことができる。臨床医や実験動物学者には,麻酔や鎮痛に関わるエビデンスだけでなく,筆者らの数多くの経験も提供してくれる。
本書は,3つのセクションに分かれており,最初のセクションでは麻酔や鎮痛に必要な基本的な知識について書かれており,麻酔理論に始まり臨床薬理学の基礎,麻酔モニター法,鎮痛法,鎮静薬・注射麻酔薬・吸入麻酔薬・筋弛緩薬の薬理,麻酔に用いる器具,および呼吸生理学と人工呼吸までエビデンスにもとづいた記載が分かりやすくなされている。2つ目のセクションは,各種動物の麻酔について,それぞれの動物種ごとに書かれている。ここには犬,猫だけでなく馬,牛,羊,山羊,豚の他エキゾチックアニマル,野生動物,動物園動物,魚類など幅広い種にわたって詳細な記述がなされている。とくに愛玩動物や産業動物以外の種の記述は新版で新たに加わった部分である。最後のセクションは特殊な状況の麻酔,麻酔合併症およびこれも新たに加わった心肺蘇生の項から成っており,どの部分をとっても興味深く読むことができる。
麻酔や鎮痛の知識や技術は,目覚ましく進歩している。我々が相手にする動物たちがより安全で快適に麻酔を受け,またより痛みから解放されるとしたらそれは素晴らしいことではないだろうか。机のすぐわきに備えておくべき麻酔書としてお勧めする。
「獣医畜産新報」2013年11月号 掲載
『Equine Locomotion 2nd ed.』
2013年・Elsevier発行・¥26,840(税込)
この本は馬の運動科学の本である。馬は5,000~6,000年前に家畜化され,移動や運搬手段となり,さらに戦争手段からスポーツパートナーとなる現在に至っている。これらはすべて馬の運動能力に依拠するもので,他の動物の家畜化過程とは決定的に異なる。現代の馬の運動科学は馬のパフォーマンスを改善し,怪我を予防し,怪我をすれば治療を成功させること,総じて馬の福祉に利益をもたらすことを目的としている。本書では馬のパフォーマンスにおける運動シグナル測定,運動の神経生物学,前肢と後肢の様機能,蹄と蹄鉄,跛行の運動学,頚と背の機能,体型の影響,遺伝的影響,筋骨系構造への運動効果,競争・競技パフォーマンス,馬と騎手との相互関係,馬の行動学と福祉,馬のスポーツ医学,馬の代謝エネルギー論,力学解析法などの順に章立てされている。いずれも基本的な説明に多くのページが割かれており,馬の運動科学とは何かということを最新の切り口からよく理解できるようになっている。むろん従来の獣医学,馬学,運動器学,装蹄学を凌駕する,あるいは解体・統合するもので馬の運動科学がここまで研究され,論理的に構成されたテキストブックになっていることに驚かされる。このことは日本の日常ではもうあまり経験することがなくなってしまった馬と人間の関係の深さを改めて想起させる。やはり人間にとって馬は特別な動物なのである。
たとえば基礎的な事項である馬の歩行と走行の種類と肢の出る順番,リズム,速度,歩幅についてどれだけの人が知っているだろうか? 飛節の関節運動が伸長-屈曲だけでなく,内転-外転,内旋-外旋の三次元運動で,互いにどのような関係になっているか知っているだろうか?跛行の運動学や動力学の章は獣医師のみならず,馬の飼養者,管理者,育成者に必須の知識だろう。また頚や背と運動能の関係における構造,生体力学,機能不全などの総合的記述は乗馬経験のないものにはわかりにくいが,「馬ならでは」で興味深い。
競馬馬券の売り上げが低迷しているのも景気の問題ばかりでなく,本書のような馬の運動科学に基づいた情報が少なく,馬の配当金がいくらかの話題ばかりだからかもしれない。馬の運動科学的視点から競技予想や内容が専門家によって解説されれば馬のスポーツ競技はもっと一般的に楽しめるものになるだろう。楽しいものでなくても,人の「ロコモ症候群」がワイドショーで取り上げられ,誰もが知るようになったように。
日本でもこの本に触発され,馬の運動科学の専門化が多く輩出されることを望んでいる。そんなことも思わせるマニアックで馬関係者のみならず馬好きには興味の尽きない科学書である。
「獣医畜産新報」2013年11月号 掲載
『Canine and Feline Infectious Diseases』
2014年・Elsevier発行・¥18,480(税込)
本書は一言で表現すると「犬と猫の感染症に関する臨床獣医師の,臨床獣医師による,臨床獣医師のための教科書」である。もちろん学生にも使えるように企画されている。
犬と猫の感染症に関する書籍としてはすでに4版を重ねているCraig E. Greeneの『Infectious Diseases of the Dog and Cat』が世界的に有名で百科事典的である。探しているものはほぼなんでも見つかる。一方,本書は,出版社も同じであることから,手にする前は,Greeneさんの本を臨床獣医師が使い勝手が良いように編集し直したのかなと先入観を持った。Sykesさんはカリフォルニア大学デービス校の獣医臨床系教授で,正直なところあまり存じ上げていなかった。もちろん小生も一昔前の世代であるからして,デービスと聞けばNiels PedersenだとかFrederick Murphyなどのbig nameに馴染みがある。本書はその大部分をSykesさんが執筆している。そしておそらく自身の経験の少ないところはより経験のある方に共著ないし執筆を依頼しているように見受けられる。しかも著者の選定には「感染症の診断と治療に造詣があり臨床経験豊富な獣医師」にこだわっている。
正直なところこの類いの書は誰が執筆や編集をしても似たり寄ったりになるのは避けられない。最初に診断や治療,管理の総論,続いて臨床頻度の高い代表的なウイルス,細菌,真菌と藻類,そして原虫類が原因となる感染症,最後に器官・臓器単位の感染症について解説している。もちろん最近の書籍に共通しているように,「直ぐに知りたいことが見つかります」と図表や写真を多用している。特に新鮮で好印象を受けたのは各感染症の最後に載っている「Case Example(症例)」である。著者の実例が詳細(病歴,理学的検査,CBCなどの検査,画像検査,細胞診,微生物学検査,診断結果,実際の加療内容と結果,獣医師のコメント)に記載されている。
実際に野外で起きている感染症は,おそらくほとんどの場合,教科書に書いてあるようには起きていない。教科書には宿主と寄生体が1:1の関係にある時について,あるいは多くの野外例の断片的な病徴的所見があたかも1頭の患者に全てが出てくるように若干デフォルメされて書かれていることが多い。臨床が不得手の感染症の専門家は直ぐにPCRで診断するという。確かに病原学的検査法は金科玉条的で,感染症を診断する上でその結果は重い。しかし検査と診断は違う。木を見て森を見ずではいけない。感染症の診断と治療の場合も良い書籍に出会うこと以上に,臨床経験がものをいうのであろう。その意味で,症例紹介の最後にある担当獣医師のコメントは新米の獣医師や学生には大いに役立つに違いない。
「獣医畜産新報」2013年10月号 掲載
『Clinical Veterinary Language』
2013年・Elsevier発行・¥12,430(税込)
事物を確定して、名称を付すことは、認識の基本であり、相互の意思疎通の根幹であり、社会成立の基盤でもある。科学においても用語の存在意義は極めて重要で、用語の種類とその定義がその領域の進歩発展の指標でもある。獣医学にあっても、また獣医臨床においても、このことは厳然たる事実である。そこには現在に至る歴史と未来への萌芽が窺知される。
近代ヨーロッパに勃興して発展し続けている科学の濫觴はギリシャ・ローマにあることから、その用語の語源はギリシャ語やラテン語の場合が多い。ところが、欧米においてもギリシャ語やラテン語の教育が等閑視されている傾向にあり、獣医師を志す学生の古典の教養も希薄化しているものと推測される。
このような問題は我が国にも認められ、先人の常識であった漢籍の素養が欠落して、徒に意味不明の片仮名が横行して混乱を極めている。例えば菌種名が片仮名で記載されているが、経文と同様で読むにも記憶するのも困難で、なぜ片仮名かと理解に苦しむ状況にある。このような現状を踏まえ、米国ではこの度紹介するような言語学的情報を基にした書籍が出版されているものと推察される。
本書は、解剖や生理に関する用語のみならず、臨床も含め獣医学を修学する人が知っておかなければならない用語・言語についての解説書と言うべきものである。用語の構成は勿論発音(英語式:ラテン語の発音方式は多々あるが、独自に読むことが許されている)などについても詳細に記述されている。
第1編の1章から3章は獣医臨床に不可欠な用語の説明で、第2編は4章から15章で、臓器系統別に用語を取り上げて詳述している。また、テスト形式を導入して、記憶を明確にして確認できるように工夫されている。付録としても4種類の項目があって、付録Aでは、6頁以上にわたり用語の語源をアルファベット順に並べてその意味、発音、用語例、参照する章が示されている。また付録Bでは、用語の意味を順に並べてその用語の中心部分、発音、用語例および参照すべき章が14頁にわたり記されている。付録Cは2段組み2頁の略語の解説である。さらに付録Dでは、分解分析できない用語についての10頁にもわたる解説である。これら付録を見ているだけで興味がそそられる。最後の索引も丁寧に作られていて利用価値が高いと思われる。
いずれにしても、外国語である英語の獣医学用語を能率良く修得するには言語学的素養を身に着けながら学習することは重要なことであると考えられる。したがって本書を獣医学の指導的立場にある人には勿論のこと、獣医学、獣医臨床の関係者には1人でも多く座右において参照して頂きたいものである。
「獣医畜産新報」2013年9月号 掲載
『The Athletic Horse Principles and Practice of Equine Sports Medicine 2nd ed. 』
2013年・Elsevier発行・¥27,720(税込)
『The Athletic Horse Principles and Practice of Equine Sports Medicine 2nd ed. 』は、馬の運動生理学に関する最新の書籍である。本書は馬のプアーパフォーマンスとバイオメカニクスの2点に焦点をあてて、乗馬関係者、競馬関係者、獣医師、運動科学の専門家、生理学者、学生など幅広い読者を対象に執筆されている。
1994年に初版が出版されてから約20年ぶりの改訂版となり、これまでに蓄積されたデーターがカラー写真や図表として掲載されており、運動生理学に関する知見が幅広く整理されている。
一般に、プアーパフォーマンスとは、「馬が体の何らかの原因によりその走行能力を充分に発揮できない状態」を指し示す。競走馬では筋骨格系の異常(跛行)が最も多く、次いで呼吸器系の異常が多いとされる。通常は微妙な変化しか認められず、原因を確定することは容易ではないことが多く、場合により運動負荷試験を必要とすることがある。プアーパフォーマンスの診断では、もともと運動能力が低い個体との鑑別が重要であり、多角的な知識が必要とされる。本書では、運動生理学の基礎として栄養学、血液代謝、呼吸器の解剖と生理、循環器の解剖と生理、筋骨格の解剖と生理、年齢による影響をとりあげ、わかりやすく解説している。
バイオメカニクス(biomechanics、生体力学)とは、生物の構造や運動を力学的に研究する学問領域であり、これまで個々の経験や理論に頼ってきた馬の調教プログラムや跛行診断の領域に科学的な視点を与えてきた。本書ではサラブレッド競走馬、ジャンプ競技馬、エンデュランス競技馬などのトレーニング時における生理学的変化や運動器への負荷などについてわかりやすく解説している。特に、体骨格の関節の可動領域に関する記載は、乗馬関係者に役立つ情報と思われる。
本書は馬のスポーツ医学の原理と実際について最新の知見が記載されており、多くの読者に役立つことが期待される。近年、科学技術の発展にともない馬の運動生理学に関する実用面での研究が進展しており、今後のさらなる飛躍を予感させる1冊である。
「獣医畜産新報」2013年9月号 掲載
『Equine Behavior A Guide for Veterinarians and Equine Scientists 2nd ed.』
2012年・Elsevier発行・¥22,220(税込)
本書は馬の行動について、カラー図版や写真を多用してわかりやすく記載された、獣医師や馬関係者向けの書籍である.著者はオーストラリアのシドニー大学教授で動物行動学とアニマルウェルフェアを担当している.また同時に、著者は長い乗馬の経験も有している.
馬の行動学の教科書といえばG.H.Waringによる『Horse Behavior』が有名だが、本書がWaringの本と異なる点は、記述された内容が、実際に馬に乗ったり調教したりするときに直接応用できるような配慮が随所になされている点であろう.たとえば馬の感覚機能を解説した章では、生理学的に検証されている馬の視覚特性から、現に馬たちが目にしているであろう風景を大胆に推測して提示している.なぜ馬が特定のものを怖がるのか、障害飛越をさせようとするときに、馬の姿勢によって障害がどのように異なって見えているのか.こうしたことを知ることは、馬を取り扱ったり管理したりする際に有用であるばかりでなく、騎乗者および馬の安全にもつながるものと考えられる.
研究者であると同時に長い乗馬経験を有している著者ならではであり、いわば本書のきもともいえる章は、「乗馬の科学」と題された第13章であろう.この章で著者は、動物を対象とした心理学、行動学的研究の成果にもとづき、馬の調教の基本について詳述するとともに、調教する際の留意点を理論的かつ具体的に記述している.乗馬の調教法については、いわゆる馬術家の手になる英文の書籍がたくさん出版されている.そうした本は自らの長い間の乗馬経験に即して書かれたもので、技術の向上に有用な場合は多い.しかし時として思い入れが強かったり、感覚的な記述に終始するばかりで、体系的、論理的な面ではものたりないという場合も多く、応用がききにくいケースもある.本章で述べられている調教方法は、その記述の背景に科学的に検証された動物の学習理論があるため、汎用性が高く、さまざまな場面で応用がきくものと思われる.
現在のところ日本語で読める本で、本書に類似した書籍は存在しない.翻訳出版されれば日本の獣医師ばかりでなく、広く馬関係者の意識や技術の向上に大いに役立つと思われる.ただし商業的にペイできるかどうかは保証しかねる.
「獣医畜産新報」2013年7月号 掲載
『Equine Medicine,Surgery and Reproduction 2nd ed.』
2013年・Elsevier発行・¥26,730(税込)
本書はいわゆる「馬の臨床」あるいは「馬の診療」といった本で、内科、外科、繁殖あるいはもっと細分化された専門科の本ではないが、全体は26章に分けられ600ページに及ぶ.各章は基本的には臓器器官系別(例えば消化器では上部消化器、胃腸病と疝痛、肝臓・腸管疾病、腹腔の疾病)となっており、その他、耳鼻咽喉科、呼吸器系、泌尿器系、免疫系、内分泌系、神経系、眼科、皮膚科となっている.また整形外科分野では跛行、蹄、肢近位、背と骨盤の4章にわかれ、別章として筋疾患も扱っている.感染・寄生虫病、代謝病、子馬疾病などの内科系疾病、外傷、鎮静・麻酔、画像、救急治療などの外科系疾病を扱った章も設けられている.繁殖の章は120ページあり、産科疾患、繁殖管理、雄馬の疾患にまとめられている.
すなわちこの本は馬の臨床で一般的に遭遇する疾病のほとんどについて体系的に記述されている.各臓器器官系の章では、まずその器官系の検査法が解剖・生理学的背景とともに記述され、大きな概念からむようになっている.そしてこれに続く、個々の疾病の記述では病因、臨床症状、診断法、治療法、予後などについて番号がふられて、あるいは箇条書きを含めた様式となっていて分かりやすい.もちろん美しい図と写真、診断画像などはふんだんに加えられていて、理解を助ける.臨床に関する獣医学雑誌では常に新規性が求められるので、掲載される論文は新しいことがらを含むとはいえ必ずしも毎日の診療に直接寄与しないだろう.その点、本書のような普通の疾病をきちんと教えてくれるものは、実は臨床家にとって最も有り難い.また馬の疾病について知識や経験が乏しいものにとっても決して程度を下げた説明ではないながら取つきやすく、全体像を理解しやすい.
すなわち本書は現在のところ、馬の臨床医療においてもっともよく使える本といってよいだろう.馬の臨床の初学者や経験の少ない臨床家ばかりでなく、馬の臨床の経験者にとっても診療内容の精査だけでなく最先端の臨床知識の整理に役立つ.このような本で学びながら馬の臨床の謎解きをできるのは本当に楽しい仕事だろう.毎日が自分にとって新しい発見の日になるだろうし、畜主への説得力も増すだろう.最終的に本当に新しいことや考えを得るに至れば本書の目的以上のことが達せられることになるに違いない.
「獣医畜産新報」2013年7月号 掲載
『Clinical Procedures in Small Animal Veterinary Practice』
2013年・Elsevier発行・¥14,740(税込)
スポーツにしても診療にしても、基礎を忘れたり無視することほど怖いものはない.基礎を忘れたスポーツは怪我の原因にも、上達の障害にもなる.基礎から外れた診療は誤診の原因になり、最悪の場合には動物を死に至らしめることにも発展する.ルーキーだろうがベテランだろうが、とにかく我々は基礎を大切にすべきである.
診療行為の基礎と言うと、立場(獣医師・動物看護師)によってその範疇が異なるかも知れない.しかし、少なくとも経験年数には左右される性質のものではないであろう.
この意味において、基本事項にこだわったテキストはその時代に見合ったスタイルで発行され続けるべきだと筆者は考えている.
ご紹介する『Clinical Procedures in Small Animal Veterinary Practice』はそんなテキストの1つである.本書は動物の保定法、取り扱い法、投薬法、救急療法、包帯法、画像診断を含む各種検査法、内科疾患の診断および治療法、麻酔法、滅菌法、縫合法、一般的な外科的手法が数多くの、そして最近では当たり前になったカラーのイラストや写真と共に簡潔よく述べられている.扱われている動物種は犬および猫は当然のこと、ウサギ、鳥類にまで及んでいる.
本書では、Prefaceでも著者らが断言しているとおり、日常的な診療での診断・治療に関する各種テクニックのみが扱われている.言わば診療の「いろは(基礎の基礎)」と言って良いだろう.このため、これから本格的な臨床教育を受ける3~4年生には格好の参考書になるであろう.一通りの教育を受けた6年生にとっては復習する際の役立つと思われる.同時に、動物看護師の方々にとっても、知識を整理したり、動物の取り扱い法、各種機材の使用法、検査の実施方を見直す際の格好のテキストになると思われる.本書は「いろは」に内容を限定しているため、ベテラン獣医師にとっては不要の書に見えるかも知れない.しかし、本書を利用して、日頃の様々な診療行為に本当に誤りや無駄がないかどうかを一通り点検し直すことは有意義なのではなかろうか.
たまには基礎をじっくりと見直し点検する… このような行為も診療のレベルアップにがると確信する.
「獣医畜産新報」2013年7月号 掲載
『Equine Applied and Clinical Nutrition Health, Welfare and Performance』
2013年・Elsevier発行・¥27,830(税込)
とても美しい装丁の本だ。背表紙、裏表紙はゴールドで、白い表紙には葦毛馬のシュールな写真が用いられている。誇らしげに英国アン王女による序文が掲げられている。
馬の栄養学の本は今までもあり、版を重ねている本もある。しかし、本書はまったく新しく計画されていて、馬の栄養学の分野を基礎からすべて網羅し、なおかつ実践的な飼料給与に役立つこと、さらには病気との関係まで詳述することを目的としている。「栄養学の基礎」「ライフステージ、飼養目的別の栄養」「応用栄養学-飼料給餌」「応用栄養学」「臨床栄養学」の5つのセクションから構成されている。
思えば人の健康問題でも一番注目を浴びているのは遺伝素因と生活習慣かもしれない。馬、とくにサラブレッドは遺伝素因については競走成績だけで選抜されていて、あとは、飼養管理が強い馬づくりのために熱心に取り組まれている。育成馬では速く大きく成長させること、競走馬では故障せずに速く走れること、繁殖馬では繁殖成績を向上させることが栄養管理に求められている。栄養補助食品、サプリメントが大はやりなのは人と同じで、飼料計算や牧草の成分分析、コンサルタントによる栄養管理指導も行われている。しかしそれは、馬の飼養や、故障の予防や、障害の治療の上で、栄養管理が重要だと認識されていながら、理想に近い飼料給与の実現が難しいことの裏返しかもしれない。実践的に、飼料給餌を実現するための情報が本書には記載されている。
私は臨床家で、どうしても病気との関係に興味が行く。「臨床栄養学」の章では、蹄葉炎(18)、病的肥満(16)、痩せた・飢えた馬の給餌(9)、高脂血症(9)、運動に関連した筋障害(15)、成長期の整形外科的疾患(13)、骨関節症の治療における経口関節サプリメント(9)、胃潰瘍(10)、消化器疾患(14)、泌尿器疾患(10)、肝障害(5)、グラスシックネス、ボツリヌス症、馬モーターニューロン病、馬退行性脳脊髄症(10)、手術前後の給餌管理(11)、孤児子馬と病気の子馬の給餌(10)、経腸・非経腸補助給餌(10)について()内に示したページ数だけの記述がある。どの項目も馬臨床家にとってたいへん興味深い。
文章のみの本になりがちだと思うのに、本書はすべてカラーページで、見やすい表とグラフ、新たに描かれたイラストが多く含まれている。各記述の重要項目は「キーポイント」としてまとめられ、速読にも対応している。
多くの馬臨床獣医師、馬飼養者、調教師、乗馬関係者、そのほか馬に関わる方々におすすめしたい。
「獣医畜産新報」2013年6月号 掲載
『Emergency Procedures for the Small Animal Veterinarian 3rd ed.』
2013年・Elsevier発行・¥16,720(税込)
受験生を抱えた家庭では「滑る・落ちる」、結婚披露宴の挨拶では「切れる・別れる」は今でも御法度である。このことは現代を生きる我々日本人が古代人から「言霊信仰」、つまり「言葉に出したことは現実となる」という信仰を引き継いでいる証拠である。だからこそ「専門家ですら想定できなかった規模の地震」を政治家や自治体が想定すると、「巨大地震が本当に来てしまう。だからそんなことは考えない、言わない方が良い」と思い、我々は防災に対する徹底的な準備を放棄してきた側面があるように個人的に思う。少なくとも人命に直結するのであれば、我々は「危機管理」を言霊信仰から切り離して考えなければならない。 自然災害と救急医療は全く別物だが、それでも関連する最新の知識を持ち、日頃から訓練を重ねる必要がある点は共通している。 さて、小動物の救急医療と言えば、1969年に初版が発行された『Kirk and Bistner’s Handbook of Veterinary Procedures & Emergency Treatment』が有名である(現在は第9版が出版されている)。ここにご紹介する『Emergency Procedure for the Small Animal Veterinarian』の初版は1993年に発行されており、いわば「新参者」と言える。しかし、本書の第3版は支持療法、ショックの管理に続いて、心臓、呼吸器、外傷、皮膚、血液、胃腸、代謝・内分泌、泌尿器、繁殖、神経、眼、中毒に関連する緊急的対処法が箇条書きで丁寧に解説されており、Kirk and Bistnerと堂々と渡り合える素晴らしいテキストに仕上がっている。ご家族から電話で問い合わせがあった場合、ご家族に指示すべき処置にも言及されており、実用面で参考になる部分が少なくない。当然のこと、エキゾチック動物の救急療法も扱われている。 本書は約900頁の大著だが、そのおよそ3割弱を中毒時の緊急療法に割いている。この点が本書の最大の特徴かもしれない。また、巻末には有毒植物、妊娠動物に有害・安全な薬剤、重篤な腎不全で使用すべきでない薬剤などのリストが掲載されている。蛇足ながら、アボガド(アボカド)が犬および猫では胃腸炎を、鳥類では急性心不全を引き起こすことを筆者は本書を手にとって初めて知ったことを告白しておこう。 緊急療法を要する動物のトラブルは多種多様で、同時に場所と時間を選ばない。万全を期した準備が必要なのは当然である。我が国の危機管理にも、そして動物医療にも「言霊信仰」はあってはならないのだ。
「獣医畜産新報」2013年4月号 掲載
『Small Animal Toxicology 3rd ed.』
2012年・Elsevier発行・¥17,490(税込)
本書の初版は2001年に、第2版は2006年に、そしてこの第3版が2013年に出版されていることからも解るように、着実に改訂が行われている。お恥ずかしいことに、筆者は本書の初版および第2版を見たことがないので、第3版の改訂内容を指摘することはできない。しかし、いくつかの特徴は直ぐに解った。
910頁からなる本書の内容に筆者はある種の迫力のようなものを感じる。
最初のセクションでは中毒の一般的な診断法と治療法が述べられている。これまでにpharmacokineticsに関する複数の論文を執筆・発表してきた筆者としては、次のセクションは非常に興味深い。性別でみた各種有毒物質の繁殖毒性、妊娠および泌乳への影響、幼齢動物および老齢動物での有害物質の体内動態などの記載は今までになかった新しい概念と言える。これらの記載は、より適切な薬物療法のヒントになり得るであろう。加えて、は虫類、小型ほ乳類および鳥類での中毒の問題点も解説されている。本書のタイトルにあるSmall Animalは犬・猫のみを指すのではなく、人が一緒に暮らすであろう全ての小型動物を視野に入れようとする意気込みが感じられる。3番目のセクションでは最近はやりのハーブや自然製剤に関連する危険性、観葉植物、室内の有毒物質などが解説されている。特にハーブに関する記載は新しい情報と言えるであろう。
最後のセクションでは当然のこと、各種有毒な物質や植物、あるいは薬剤、科学物質による中毒が記載されている。アセトアミノフェン、アミトラズ、殺鼠剤、抗痙攣薬、イベルメクチンなどの医薬品、ヒ素、鉛、鉄、水銀などの金属、パラコート、プロピレングリコール、有機リン系殺虫剤などの「中毒の定番」とも言うべき有毒物質、さらにはユリ、マカデミアンナッツ、メタノール、マッシュルーム、ブドウ、キシリトールなど「我々を楽しませてくれるもの」も取り上げられている。このセクションで扱われているのは55項目である。有毒植物はカラー写真で説明されていて、植物になじみのない読者に配慮している。
本書には動物と暮らすご家族にとって重要な情報が満載されていると言える。英語で記載されているために、ちょっと取っつきにくいかも知れないが、必要な箇所だけ辞書を片手に頑張って見ては如何であろう。新たな発見が必ずあるに違いない。その発見を通じて、通院されるご家族に提供できる情報の質がアップすると確信する。
「獣医畜産新報」2013年2月号 掲載
『Muller & Kirk's Small Animal Dermatology 7th ed.』
2013年・Elsevier発行・¥32,450(税込)
今から24年も前の話である。私にとってはじめての海外渡航が米国コーネル大学への皮膚科研修であった。この地を訪れたのは、『Small Animal Dermatology』のオリジナル著者のお1人であるRobert Kirk先生が設立した獣医皮膚科があり、さらに当時出版された本書第4版の主たる執筆をしていたDanny Scott先生がその教授を勤めていたからである。わずか1年しか滞在できなかったが、この間に本書を2回精読したことを覚えている。本書は版を替えるごとに執筆者が代わり、第5版ではオリジナル著者のお2人が退かれ、同じコーネル大学のWilliam Miller Jr.先生と同大卒のCraig Griffin先生が参加、そして今回出版された第7版ではDanny Scott先生が退かれ、初めての女性著者としてイリノイ大学のKaren Cambell先生が招聘された。これまで約5年の周期で改訂されてきた本書は獣医皮膚科学のバイブルと呼ばれ、常に最新の情報が満載されてきた。ところが2001年の第6版以降、なんと11年も沈黙があり、その歳月を経てこの度まったく新しいバイブルが生み出された。これまでは3名の著者により執筆されていたが、今回は3名の監修のもと合計17名の著者によって執筆されている。また出版社はELSEVIERとなり、膨大なボリュームを効率よくカバーすべく実に無駄のないレイアウトとなって、読みやすさに配慮し各章には付箋が添えられ、驚くなかれ全ページカラー印刷で仕上がっている。コンテンツは従来の流れに準じ21章で構成され、しかも図表の質がこれまでと比べて格段に向上し、皮膚科の醍醐味である臨床や病理のカラー写真が1,300以上も掲載されている。もちろんバイブルの本質である文献の網羅的収集は本書でも遺憾なく発揮され、国内外ジャーナルに留まらず、興味深い学会抄録も拾い上げられている。当然のことながら皮膚臨床に関わる獣医師や皮膚科学を学ぶ学生の必読書であり、さらに皮膚科研究者にもなくてはならない1冊である。本書が届いてまだ1週間、多くを語るには十分といえないが、全938ページを誰よりも早く読破したいと息を巻いている。
最後に、本書のオリジナル著者であるRobert Kirk 先生、そして獣医皮膚科の父と言われているGeorge Muller 先生が、一昨年ご一緒に他界されたことに触れておきたい。1969年に初版が刊行され、43年の長い歴史をもって本書が今年刷新されたのは、彼らの魂が乗り移ったからなのでろうか。この場をお借りしてお2人に改めて敬意を表すとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。平成24年12月31日ASCにて
「獣医畜産新報」2013年2月号 掲載
『Veterinary Euthanasia Techniques A Practical Guide』
2012年・Wiley-Blackwell発行・¥11,330(税込)
この本は、タイトルにもあるように動物の安楽死に関する実践書である。動物の安楽死に関する記述は、麻酔の教科書を中心に結構数多くあるが、多くは概念的なもので安楽死を具体的にどう行うべきかにつての情報は十分ではなかった。動物の安楽死のガイドラインとしてAVMA(American Veterinary Medical Association、数年おきに改定されている)が出したものがあり、広範囲な動物種について推奨される安楽死法や使用する薬剤などの記載がある。しかし、これにも具体的な実施方法までは記されていない。本書は、安楽死を動物の飼い主とどのよう決めていくのか、必要な器具、保定法、安楽死前の鎮静・麻酔、具体的な安楽死の方法、遺体の処理法の順で構成されており安楽死を適切に行う実際を細かく知ることができる。ちなみに筆者の1人のDr. Cooneyは、安楽死の専門機関のオーナーと記されており、豊富な経験をもとに書かれたものと推察される。ただし本書はエキゾチックアニマルを含めたペットと生産動物を中心に扱っており、実験動物の安楽死についてはあまり記載がないので注意が必要である。
以前の調査で、日本の獣医師の大部分が安楽死を経験しており、安楽死を行うことは正当な医療行為であると考えている。一方で、安楽死に対して抵抗感が強く、自分から患者の安楽死を申し出る獣医師の数は少なく、また安楽死の際には飼い主が同席することを求めるものが多いことも報告されている。日本では安楽死の話は出ていても、飼い主が実際に安楽死を選択することはあまり多くない。お互いに精神的な緊張感が高い中で行われる安楽死に対しては、決定に至る思考回路をしっかり構築することが重要であり、またより適切な方法でなされる必要性も高い。
獣医師、獣医学生、看護師を始めとする動物の安楽死を行う、あるいはそれを補助する人にとってとても参考になる1冊である。個人で買いそろえる必要はあまりないと思うが、病院に置いておきたい1冊である。
「獣医畜産新報」2012年12月号 掲載
『Canine & Feline Gastroenterology』
2012年・Elsevier発行・¥27,720(税込)
本書は、肝胆道系、膵臓を含む消化器病学の集大成ともいえる本である。Robert J. WashabauとMichael J. Dayが17か国85人の消化器病のスペシャリストを招集し、消化器疾患の基礎的な解剖や生理から、内視鏡、腹腔鏡に至るまで事細かに記載してある秀逸の教科書といえる。
本書の特徴としては、臨床家が今すぐ知りたい内容を探せるように、各種のアプローチ法が事細かに分類されていることである。例えば、腹痛を示す消化器疾患へのアプローチ、栄養学的アプローチ、画像診断のアプローチ、薬理学的アプローチなど知りたいと思う項目が一目でわかるつくりになっている。中でも、病理組織学の解説では豊富な組織写真が、非常に分かりやすく解説してある。
肝胆膵を含む消化器疾患を理解するうえでは、病態生理や薬理学はもちろんであるが、病理学の知識がかなり必要となる。病理組織学的な知識があると、その疾患の全体像が把握でき、なおかつ治療方針も明確に決めやすくなる。しかし、従来の消化器病の教科書や参考書は、白黒で印刷されており、お世辞にも見やすい内容ではなかった。本書は、カラーで印刷されており、また画像やイラストも上質である。また、知りたい内容を調べる上でも、疾患名がわからず臨床症状だけだとなかなか教科書で調べることは困難であったが、本書はいろいろな角度からのアプローチ法が記載されているので、この本を開けば、答えがある可能性は高いといえる1冊である。
また本書は、臨床家が経験ではなんとなく理解しているようなことが、理論的にイラストや写真で図解してある(これには、本当に驚かされた!例えば、消化管壁がレントゲンで分厚く映るのは、なぜか?など)。この本で、何気なく目の前にいる消化器疾患の患者について調べだしたら、次から次へとページをめくっていくに違いない。そして、知りたいことが分かった時には、その疾患のスペシャリストになれるかもしれない。
知りたい内容を調べた後は、病態生理の項目も是非一読していただきたい。分子生物学的知識や免疫学的知識がないと、読み進めるのは少し根気がいると思われるが、豊富なイラストに助けられながら読み進めることで、消化器疾患の全体像が理解しやすくなる。治療法や投薬の項目だけではなく、なぜその薬が必要なのか?どうやって作用しているのか?どのようなデータがあるので、こんな治療法が選択されているのか?などもコンパクトに記載してある。
本書は本棚に飾るものではなく、診察室に置いて常に参考にするべき1冊であり、明日からの消化器疾患の診療に必ず役に立つと思われる。
「獣医畜産新報」2012年10月号 掲載
『Veterinary Echocardiography 2nd ed.』
2011年・Wiley-Blackwell発行・¥32,340(税込)
第1版は1998年に発刊され、各断層像の描出方法や評価ポイント、心機能評価および臨床例など写真や図を用いて具体的に解説されており、犬猫および馬の心エコー図法のバイブル的書籍であった。そして、その後約10年の間に、獣医学領域での心エコーは、超音波診断装置の技術的進歩および普及によりめざましい発展を遂げている。その約10年間に蓄積されたデータや新しい技術を踏まえ、2011年に本書第2版が発刊されている。
第2版では、超音波の原理から始まり、断層心エコー検査で必要な各断層像を描出するための、プローブ走査をより理解しやすく解説している。特に、各断層像の見え方および描出テクニックは、簡潔にまとめられており読者にとって非常に読みやすい構成になっている。また、Mモード法およびドプラ法に用いられる断層像、描出テクニックおよび見え方も同様である。
そして、心エコー検査の基本である各断層像での評価ポイントを多くの写真を用いて具体的に示している。心エコー検査では様々な計測を行うが、計測に用いる断層像の描出の注意点、計測方法のポイントや注意点および判断基準なども別枠に書き出されている点がありがたい。心機能評価については、従来から用いられている指標の内容が充実しており、参照値等も詳しく出ている。特に、パルスドプラ法を用いた左室流入血流や連続波ドプラ法を用いた逆流血流等から得られる情報に関し充実した内容となっている。また、新しい技術として導入されている組織ドプラ法を用いた心機能評価の新た指標とその解釈が紹介されている。
臨床例に関しては、第1版では後天性心疾患としてまとめられていたものが後天性弁膜症、高血圧性心疾患、心筋疾患、心膜疾患と腫瘤とそれぞれ独立した章から構成されており、多くの臨床例を通して心エコーを理解できる。また、先天性心疾患も短絡性疾患・弁異形成と狭窄性疾患に分けて詳しく解説されている。
そして、非常にユニークなのが、各章の最後に小テスト問題があり、各自がどの程度内容を理解できているか自己判断できる点である。また、付録としての心エコー計測値の参照値がより充実されており、牛、犬、馬、猫およびその他の動物での品種別や年齢・体重別の参照値が記載されている。
心エコー検査を行っている者にとって、本書はぜひ手元に置いておきたい1冊ではないかと思われる。
「獣医畜産新報」2012年5月号 掲載
『Oral and Maxillofacial Surgery in Dogs and Cats』
2012年・Elsevier発行・¥61,490(税込)
小動物臨床における獣医歯科学や口腔外科学の専門書は多く出版されているが、そのほとんどは英語で記載されたものである。翻訳されたものも徐々に増えてはいるが、その数はいまだに少なく、獣医歯科学をしっかり学びたい獣医師にとってはこの現状に不満足であるかもしれない。しかし、英語の書で学ぶことによって得るものは多く、優れた書は英語にかかわらず、手にしていただきたいものである。日常診療では、歯周病はじめ、さまざまな口腔疾患に遭遇するが、さてどの専門書で獣医歯科学を勉強したらよいか分からないといった意見を耳にすることが少なくない。
その点、本書は、きわめて鮮明な大きなカラーの写真とイラストが随所に掲載されており、大変理解しやすい。本書1冊で口腔および顎顔面における外科に必要な内容がほとんど網羅されている。最初は、英語の歯科学の専門用語に慣れないと読みにくいかもしれないが、辞書を片手に読む価値は十分あり、直ちに臨床に生かせる内容である。単なる技術書にとどまらず、生理や解剖なども同時に学べ、口腔および顎顔面における種々の疾患の最新のエビデンスに基づいて書かれており、ぜひ推薦したい1冊といえる。
本書は、下記のように全部で11章から構成されている。これを見ただけでいかに豊富な内容が満載されているか理解できよう。
第1章:外科の生物学
口腔軟組織の外傷の治癒、顎顔面骨の治癒、抗生物質と消毒剤の使用法、麻酔と疼痛管理、経腸栄養
第2章:外科
器具・体位・無菌処置、縫合糸の種類と生体用材料、レーザー治療、顎顔面における微小血管手術、犬と猫を用いた顎顔面の外科手術の実験的試み
第3章:抜歯
抜歯の原理、単根歯の単純抜歯、犬の犬歯の抜歯、犬の多根歯の抜歯、猫の抜歯の特徴、抜歯の併発症
第4章:歯周外科
歯周外科の原理、歯肉切除術と歯肉形成術、歯周フラップと歯肉粘膜外科手術、歯周外科における骨伝導および骨誘導物質、歯冠延長術、歯周の外傷治療
第5章:歯内治療
歯内治療の原理、根尖切除術
第6章:顎顔面における外傷治療
顎顔面の外傷治療の原理、顔面の軟組織の外傷、下顎および上顎の外傷への外科的アプローチ、切歯領域を含む下顎結合の分離と骨折、非侵襲性テクニック・骨内ワイヤー・ミニプレートとスクリュー・創外固定を用いた顎顔面骨骨折の整復、顎関節を含んだ骨折と脱臼、顎顔面骨骨折の併発症
第7章:口蓋の外科
口蓋裂と口蓋の外科の生物学的基本、口蓋裂の整復術、後天的口蓋欠損の修復
第8章:顎顔面腫瘍と嚢胞の治療
顎顔面腫瘍の臨床ステージとバイオプシー、臨床病理学的相関、非歯原性腫瘍・歯原性腫瘍の臨床的特徴、非腫瘍性増殖性口腔疾患、口腔腫瘍外科の原理、舌・口唇・頬の腫瘍の外科治療、上顎骨・下顎骨切除術、歯原性嚢胞の臨床的特徴と治療、進行した顎顔面の再形成術
第9章:唾液腺の外科
唾液腺外科の原理、唾液腺腫瘤の外科治療
第10章:その他の顎顔面の外科
口唇形成術、下唇小帯形成術とtight-lip症候群、顎顔面骨壊死症の治療、未萌出歯の治療、顎関節形成異常
第11章:耳・鼻・咽頭の手術に対する口腔のアプローチ
軟口蓋過長症の治療、咽頭切除術と咽頭切開術、鼻腔と鼻咽頭への口腔アプローチ、扁桃切除術
「獣医畜産新報」2012年4月号 掲載
『Veterinary Computed Tomography』
2011年・Wiley-Blackwell発行・¥31,790(税込)
この10年間、CTはわが国の小動物臨床に急速に普及した。短時間で撮影できる多列検出器CTの出現が、CTの普及に拍車をかけた。今では、1診療圏に1台程度普及し、診断のツールとして重要な役割を担っている。しかし、CTについて調べようと思っても、 CTが系統的に説明されている獣医師向けの教科書はなかった。そのため、学部学生時代にCTの講義を受けていないわれわれの世代は、文献検索をして情報を探し出すしか方法はなかった。そんな中で、本書に出会った。
本書は、CT画像構成の原理はもちろん、現場で遭遇するアーチファクトについても解説されている。また、三次元ソフトウエア、PACSを利用したデジタル環境、CT導入の費用対効果といった周辺領域についても詳しい。さらに画像については、小動物の各部位別の疾患に加えて、馬、牛、豚、ウサギ、ネズミ、鳥、カメの画像も示されていて、予期せぬ患者さんに遭遇しても慌てない秘密の引き出しである。
また、日本では施設によってバラバラな断層画像表示(横断画像は、画像の上が動物の背側、画像の右が動物の左)が定義されている。さらに、断層方向(人と動物では頭部のtransverse、 dorsalの表示が異なる)の用語の定義が示されている。毎回同じ向きで画像を表示することは読影の基本である。読影に際し、統一された呼称と画像表示で議論することが、わが国のCT診断の更なる発展のために必要である。
医学放射線領域とは異なり、われわれの現場には診療放射線技師がいない。CTの操作から読影まで全て獣医師の仕事である。つまり、獣医師はCTについてオールマイティな知識が求められる。鑑別診断リストを頭に浮かべながら、必要な画像再構成関数を考慮にいれてCTを操作し、撮影後はウインドウレベルを操作しながら診断しているのが現実である。本書は、そんな状況でCTを利用している獣医師、これからCTを学ぶ獣医師にとって必見のバイブルである。
読み進めていくと、私の論文がFurther Readingとして3つ紹介されていた。ますますこの教科書が好きになった。
「獣医畜産新報」2012年2月号 掲載
『Kirk and Bistner's Handbook of Veterinary Procedures and Emergency Treatment, 9th ed.』
2011年・Elsevier発行・¥17,050(税込)
5年程前に本書8版の書評を依頼され、その書き出しを以下のように綴った。1969年にKirk先生とBistner先生が当時の急速に発展する小動物診療の状況を踏まえて、臨床獣医師が要求される諸問題に対処しなくてはならないことを念頭におき、その指針として“診療技法と救急対処法”を刊行した。以来、多くの臨床獣医師に活用され、また改版を重ね、初版から37年目の今年、第8版がR.B. FordとE.M. Mazzaferronoの両先生によって上梓されたのが本書である。診療の鉄則である迅速な対応を主眼とする構成は初版以来貫かれているが、そこには小動物臨床の最新知識と最高水準の技法が包含されている。この書評の第8版もそれ以前の版と同様に江湖に受け入れられた。
そしてこの度2012年度版として、第9版が発刊されることは誠に喜ばしく思われる。最近の獣医臨床の進歩はこれまでになく加速しているので、改定新版には特別な関心を抱いて通覧した。本書も初版の精神を受け継ぎ、第8版と同様の考えで編纂されており、随所に読者の便を図りながら新情報が加筆されている。ここで著者らは本書を本年1月に亡くなられたKirk先生に奉げるとしている。Kirk先生は何回か来日されているが、コーネル大学の獣医内科学教授を務め獣医界の発展に尽力された方である。また小動物皮膚科の発展にも貢献され、この救急医療書のシリーズやCurrent Veterinary Therapyシリーズの出版を牽引された功績は大きい。
本書の表紙を開くと先ず緊急時における主な治療対象がアルファベット順に記載され参照する頁が示されている。また裏表紙には緊急時のホットラインと臨床検査の参考値が表示されている。本書は本文のみで700頁に及ぶ大著で、前版同様6章から構成されている。第1章は救急対応の基本的事項に関するもので、即刻診断治療できるように配慮され本書の約40%の300頁を占めている。受診前対応、初診時対応、緊急処置、疼痛の評価と対応、特殊状態の緊急処置について記載さあれている。第2章は初診時対応、カルテの記載、各器官系の精査についての記述である。第3章は主要な臨床徴候の解説で、定義、関連徴候、鑑別診断(主に箇条書きで表示ないし流れ図)および診断計画で、問題中心の対応である。第4章は診断治療の手法の説明で、日常臨床の現場において必須とされる手技の解説で習熟の助けになるものと思われる。第5章は所謂臨床病理で、臨床検査の進め方、検査の手法などが詳述されている。第6章は各種動物(犬、猫、げっ歯類、ウサギ)に関する基礎的情報や臨床検査値が表示されており、100頁にも及んでいる。勿論常用薬剤の適応や用量の表(約60頁)も含まれている。
以上のような内容の本書であることから、臨床獣医師は勿論のこと、獣医学・獣医療関係者をはじめ獣医師を志す学生にも推奨できる一書である。
「獣医畜産新報」2011年10月号 掲載
『Small Animal Clinical Pharmacology & Therapeutics 2nd ed.』
2011年・Elsevier発行・¥20,130(税込)
まず、そのボリュームに驚く。本文で1200頁を超え、全体で1300頁を超える大型の書物である。およそ10名の著者で書かれておりこのボリュームにしては著者数が少ない。内容を統一的にして読みやすくするためにはこれくらいの人数がよいのかもしれない。
書籍内は症例の写真はほとんどなく、本文とその説明のための図表で占められており情報がぎっしりと詰まっている。おそらく診療中に用量や副作用をすばやく調べる本ではない。レベルの高い教科書的な書籍で、腰を据えて毎日少しずつ読み込んでいくタイプの本であろう。特定疾患の治療のための薬剤に迷うときなど、やや詳細に情報が必要な場合にも本書は有用であろう。
内容としては、基本的な臨床薬理の解説に120頁(全体の約1/10)のボリュームを使っており、残りはすべて各論。基本的には感染症、消化器、循環器などすべての分野を網羅的している。対象動物は犬・猫である。各論の構成は書き手や分野によりそれぞれ若干異なっているが、病態や生理的な解説から始まり、基本的な薬理作用(理論)、各個別の薬剤の効果や副作用、同型薬剤間の比較などが詳細に記載されている。エビデンスに基づく記載をポリシーにしており、本文中には極めて多くの文献を引用している。よくこれだけの情報が集められたものだと、著者らの努力には頭が下がる。これまで動物での情報が手薄であった、各薬剤の吸収(例えば経口投与での利用率)、薬物動態(体内での分布や半減期)などの情報も豊富で、これらの知識は実際の処方の際に役に立つであろう。
臨床薬理の書籍には薬理作用中心のものもあり、臨床家としてはなかなか読みにくいものであるが、本書は臨床的に有用なものをという立場で書かれているようで、興味深く読み進めることができる。いまから本格的に小動物臨床を学ぼうとする学生(高学年)や若い獣医師には推奨できる。また十分に詳細な情報が盛り込まれているのでベテラン獣医師でも1年くらい時間をかけてじっくり読破すれば、臨床のレベルが1つ(または2つ)上がる、という書籍だと思う。また、このボリュームと内容でこの値段は喜ばしい。
「獣医畜産新報」2011年9月号 掲載
『Fowler's Zoo and Wild Animal Medicine Current Therapy Vol.7』
2011年・Elsevier発行・¥33,330(税込)
『Fowler's Zoo and Wild Animal Medicine』 のシリーズは、爬虫類から哺乳類までの獣医学的情報を網羅的かつ総論的にまとめて出版した後、数年間はこの分野における最新情報を各論的に提供するのが特徴である。ちなみに、本シリーズの第5巻は、『野生動物の医学』(中川志郎監訳)として2007年に文永堂出版から刊行されている。今回発刊された第7巻は、上記した各論的情報の提供に該当するが、取り上げている内容は魚類から保全医学に関するものまで多様かつ豊富である。とくに、野生動物医学が種の保全に対して如何に貢献するかを、"One Health"という最新の概念を緒言で記しているのは注目すべきことである。近年問題となっている野生動物と家畜と人のインターフェイスにも一章が当てられている。単に希少種保全だけが、野生動物医学の目的ではないことを改めて認識させられた。北米における野生動物医学の方向性を示した選択だと思う。
本書の頁を開いて最初に目を引くのは、執筆者の多さである(119名!)。野生動物医学に関わっている専門家がこれだけいることに感動する。しかも、シルバーエイジの私が知っている研究者の名前は少なく、世代交代が確実に進んでいることを実感した。国内でも、いつかこのような専門書を出版できるよう、野生動物医学に関わる若い研究者や臨床家の育成と、学術領域における基盤構築を行いたいものである。
書評の字数が限られているため、83章もあるタイトルのすべてを紹介できないのが残念だが、個人的には第47章の "Haemosporidian Parasites: Impacts on Avian Hosts" と第56章の "White-Nose Syndrome in Cave Bats of North America" に関する最新情報が参考になった。鳥インフルエンザに対する動物園の対応(第45章)も、国内の関連施設にとっては役立つであろう。
特筆すべき本書の新規性は、これまでになくカラフルであること、写真や図表が多いこと(280点)である。各タイトルの文字色も、分野別に色分けされており、直感的に内容を把握しやすく配慮されている。ビジュアルを重視する若い世代の読者を意識したせいかもしれないが、これらの配慮は英語圏に属さない国の読者にとっても有難い。写真を見てそのキャプションを読むだけでも、臨床や研究の参考になるに違いない。
本書は、野生動物もしくは動物園動物の臨床や研究に関わっている方々に、かなりお勧めの好著である。翻訳本の出版など期待しないで、早く購入し英和辞書を傍らに置いて読んだ方が賢明だろう。
「獣医畜産新報」2011年8月号 掲載
『Color Atlas of Diseases and Disorders of Cattle 3rd ed.』
2011年・Elsevier発行・¥26,510(税込)
英国の臨床獣医師であるBlowey氏は相変わらず精力的で、牛疾病アトラスである本書も3版となった。掲載された疾病写真は848枚に及び、第2版より96枚増えている。これらには少なくとも19種類の疾病の写真が新しく追加されている。そうであるのに本書はわずか250頁ほどで見やすく使いやすい。また3版では各写真にはキャプション(短い説明文)が追加されており、よりわかりやすくなっている。本文が簡潔で要を得ていることは前版と同様であるが、とくに第2版(2003年出版)以降においても大問題であり続けている、口蹄疫、ブルータング、BSEの項目は新たな研究成果も追加されて改訂されている。また本文中の他の多くの部位でも疾病管理法や類症鑑別について加筆・修正されている。
私も診療のときに多くの疾病の写真を撮影するが、ピントがあっているのは当然だとしても、視覚から感じ取った印象を写真に表現するのはなかなか難しい。このアトラスでは実にうまく表現されており、リアルである。食事の時間以外にパラパラと頁をめくって、写真をながめるのも楽しく、そうだったのかと新たな視点を得ることもある。また疾病の視覚的特徴や写真の表現法になるほどと思わせることも多い。つまりどのような感性で疾病を見(診)るべきかを示している。
この本を購入すると出版元のエルゼビア(Elsevier)のサイトで、pageburstというアプリケーションを用いてebooksにアスセスして、自分だけのポートフォリオを作ることができるようなっている。つまり購入書籍だけからではなくインターネットサイトを介して新しい学びのスタイルを得ることができるというしかけである。ぜひ本書とともに試していただきたい。本書は牛の臨床家のみならず、農場管理者、生産関係者、学生にも幅広く有用な“百聞は一見にしかず”の1冊である。
「獣医畜産新報」2011年8月号 掲載
『Small Animal Bandaging, Casting, and Splinting Techniques』
2010年・Wiley-Blackwell発行・¥10,230(税込)
人間であれば、小さな絆創膏ひとつで済む傷でも、犬や猫では大げさな包帯を必要とする場合が多い。例えば尻尾の先端の小さな傷でも、時には尻尾の付け根まで包帯を巻くことになる。ところが折角厳重に包帯をしても、尻尾の一振りで、あっという間に根こそぎ抜け落ちてしまうことがある。動物の場合、包帯を施すことが如何に難しいかがよく分かる。
この場合には、ちょっとしたコツがある。適当な幅の粘着テープで尻尾の両側に“あぶみ”なるものを予め張り付ければよい。これは四肢の包帯にも役立つコツでもある。ところが、こうしたコツを文章で説明するのは結構難しい。うまく表現して綴ったつもりでも、読者にはなかなか理解できないこともある。本書では写真を不断に使って、その包帯の仕方を段階的に示しており、極めて理解しやすくなっているのが特徴といえる。
本書は5章に分けられて構成されている。包帯は基本的には三層からなる。すなわち第一層は直接創傷に当てる部分であり、創傷の性質や状態によってその材質が異なる。第二層は創傷から体液を吸収、排出する層として働き綿パッドや巻いたコットンなどが使われる。第三層は第一、二層を保護する層となり、粘着テープや自己接着テープなどが使われる。第1章はこうした包帯の材質をはじめ、包帯の効能、注意事項など、総論的な内容が記されている。
第2章から第4章までは体の部位ごとの項目に別けて、包帯法が記されており、いずれの項目も、適応、手技、アフターケア、利点と問題点についてそれぞれ述べられている。第2章は頭部と耳の包帯法、第3章は胸部、腹部、骨盤部の包帯法が記されている。第4章では四肢の包帯、ギプス包帯、副子包帯、吊り包帯などの方法が記されており、この章が全体のかなりの部分を占めている。ちなみに、前述の尻尾の包帯法もこの章で分かりやすく写真を使って事細かに記されている。最後の第5章はエリザベスカラ―など、折角の包帯が外されないように予防する方法が記されており、なかでも胡椒が刷り込まれているテープや軽い電流が流れるテープなど興味をそそられる紹介もある。
数年前に『Animal Restraint for Veterinary Professionals』(『獣医療における動物の保定』文永堂出版)なる書籍を翻訳させて戴いたことがある。この場合も紐の結び方をはじめ、動物の押さえ方など経時的な写真が極めて効果的であった。文章を読まなくても写真を見ただけで直感できるものがある。こうした技術とコツを必要とする内容の書物では、写真やイラストを不断に使うことが必須であり、そういった意味から本書は親切で効果的な書物といえよう。
包帯は日常茶飯事の処置であり、動物に不安感や違和感などを抱かせないためにも適切な包帯法が重要となる。学生や研修医は勿論のこと経験ある獣医師にも十分役立つ書物と言えるであろう。
「獣医畜産新報」2011年6月号 掲載
『Handbook of Veterinary Neurology 5th ed.』
2011年・Elsevier発行・¥20,130(税込)
この本は初版から読んでおり、この第5版も以前の図や記事を思い出しながら読むことができた。しかし、著者が、私が顔見知りだったOliverやKornegayから新しい著者に代わっており、以前からの著者はLoenzだけで時代の流れを感じたが、著者が代わったために新しい情報が豊富に取り込まれた内容になっていた。
この本は、初版から、高度の確定診断機器をもっていないクリニックの臨床獣医師のための本という目的を貫き通している。したがって、神経障害があると思われる動物が来院したとき、最初から障害の原因を調べるのではなく、神経学的検査を基本とした局在診断により病変の存在部位を明らかにすることから神経診断を開始していくべきであるという、一種の哲学に撤している。この本が他の本と異なるこの特徴は、最初の3章に凝縮されている。したがって、この3章は初版からそれほど変わってはいないが、確定診断の章になって初めてMRIやCTのような高度画像診断を用いた説明が出てきて、神経病の各論では新しい知見が豊富に引用されている。
この本のもうひとつの特徴は、小動物の神経病が中心であるが、馬や家畜の神経病も説明されている点である。また、本に添付されている“Book Pin”を用いてウェブサイトを開き、神経病の小動物・大動物20症例のビデオをパソコンのディスプレイで見ることができる。文字の小さいのが難点ではあるが、文章は500頁未満であるため、獣医神経病の全体像を理解したいという臨床獣医師、あるいはこれから神経病を理解したいと考えている獣医学生には、是非ともお薦めしたい本でもある。
文章の内容を要領よく表にまとめてあることも特徴のひとつである。読んでいると、いちいち表を参照しなければならないために最初は戸惑いがちになるが、読み慣れてくると違和感がなくなり、特に再度内容を参考にしようとするときには非常な利便性を感じるようになるのであろう。
この本の最後に付録として、犬や猫の他に、牛、山羊、馬、羊、豚の先天性、遺伝性、品種特異性の神経疾患と筋疾患の表がついており、これらの表の後に、この本の引用文献がアルファベット順に記載されているのも便利である。各章の最後に引用文献の一覧表がついているが、引用順に配列してあるために、特定の著者の文献を探すのは非常に困難なので、1,000を超える文献の一覧表は非常に便利である。同時に、この本の著者達が、これだけの数の研究論文を如何に丁寧に調べて引用しているかが分かり、この本の価値を暗示しているようであった。
「獣医畜産新報」2011年4月号 掲載
『Canine and Feline Nephrology and Urology 2nd ed.』
2011年・Elsevier発行・¥17,490(税込)
日常の診療の中で、泌尿器疾患の占める割合は極めて大きい。私たちに泌尿器に関する多くの情報を提供してくれる尿検査は、日常のルーチン検査の筆頭にあげられるが、私たちはこの尿検査の中から、本当に重要なことをどれほど汲み取っているのだろう。「おしっこ」の示す情報は、腎臓や尿路からの重要なメッセージである。また、腎機能の評価についても、私たちはBUNや血清クレアチニン濃度がある程度高値を示さない限り、無頓着なことが多くないだろうか。無頓着なあまり、末期腎不全となって劇的な尿毒症の症状を示して死に至るまでに、泌尿器から繰り返し送られる信号を見逃してはいないだろうか。本書は、そのような泌尿器の異常に関する信号を診断する方法と、その臨床的意義、そして各種泌尿器疾患の治療法について解説してくれる実際的なマニュアルである。
ここでご紹介する『Canine and Feline Nephrology and Urology』は、1986年に発行された『Manual of Small Animal Nephrology and Urology』(Dennis J. Chew & Stephen P. DiBartola著)の第2版にあたる。初版は文永堂出版より『小動物の腎・泌尿器疾患マニュアル』(武藤 眞、渡邊俊文、小村吉幸 訳)として出版され、多くの臨床家に愛読されてきた。第2版である本書では執筆者にミシガン州立大学のPatricia A. Shenckを加え、新しい書式でよりわかりやすく、またDennis J. Chew と Stephen P.DiBartolaの両先生のオハイオ州立大学Veterinary Teaching Hospitalでの30年間にわたる臨床経験に基づく多彩なコメントがちりばめられている。第2版では、特に「What Do We Do ?」「Thoughts for the Future」「Common Misconceptions」「Summary Tips」「Frequently Asked Questions」という新しいコーナーが設けられて、臨床家の日頃感じている疑問に対する答えやヒントが織り込まれている。また、陥りやすい間違いについても、解説されている。
本書は、犬と猫の泌尿器病疾患の病態生理、診断法とその臨床的意義、そして治療法についてわかりやすく項目立てて解説されているが、それだけでなく泌尿器が尿を産生して排出するまでのしくみと役割についても鮮やかに解説されている。各項目では要点が箇条書きにされていて、大変読みやすい。また要所要所に図表が配置され、これが大変わかりやすく、読者の理解を助けている。写真も、美しい。そして臨床家にとって非常に重要な治療の際の薬物投与の仕方や投与量についても解説されており、日常の診療の際にすぐ役立つように考えられている。したがって、本書は、これから臨床獣医療を目指す学生諸君にとっても、そして若い獣医師や、もうベテランの域に達した臨床家にとっても、すぐに使える1冊である。是非、お手に取って試して貰いたい。私の、お勧めの1冊である。
「獣医畜産新報」2011年3月号 掲載
『Small Animal Endoscopy 3rd ed.』
2011年・Elsevier発行・¥31,680(税込)
伴侶動物の内視鏡分野の草分け的な書籍で、第2版から12年ぶりの改訂となる。650頁を超える意欲的な書籍であり、画像診断系の書籍ではあるが、画像だけでなく説明文章にも多くの労力をさいている(すごいボリュームである)。
内容としては機器の構成や基本的な操作法にはじまり、最新の手技まで非常に詳細に記載されており、網羅的な内容になっている。消化管内視鏡、腹腔鏡など内視鏡を扱う様々な分野においてビギナーだけでなく熟練者にも読みごたえのある1冊である。
フレキシブル内視鏡を使用した消化管検査が本書の前半を占めており、残り半分は硬性鏡に充てられていることも本書の特徴である。硬性鏡では、機器の説明や操作方法からはじめ、腹腔鏡、胸腔鏡、膀胱鏡、鼻、耳、関節など内視鏡が用いられているすべての分野について具体的手技が記載されている。硬性鏡を用いた伴侶動物の画像診断分野はまだまだ情報が少ないので、各種内視鏡手技の詳細を記載した本書の価値は高い。
本書は内視鏡について広い分野をカバーしている。そのため1人の臨床家が本書に記載それているすべての手技を習得することはできないと思われるが、発展の著しい内視鏡分野での先端技術を把握し、自分が実施できない手技については適切に二次診療施設等に紹介するための知識を得るのに適している。また高度獣医療施設や教育動物病院などさまざまな内視鏡獣医療を取り入れている施設では本書の網羅的な内容はスタッフの教育などにも大変有用であろう。
「獣医畜産新報」2011年3月号 掲載
『Diagnosis and Management of Lameness in the Horse, 2nd Edition』
2011年・Elsevier発行・¥38,170(税込)
馬の跛行のテキストブックといえば何と言ってもアダムスの『LAMENESS IN HORSE』であり、初版は1962年に出版され、現在5版を数える。一方、この書評で取り上げたDiagnosis and Management of Lamenes in the Horseの第1版は2003年に出版されている。アダムス本はどちらかというと馬跛行のエンサイクロペディア(疾病の記述的説明)で、解剖から始まり、跛行疾病の記載も解剖学的部位別に順序立てて整理されている。本書ではDiagnosis and Managementとタイトルにあるとおり、より実際的あるいは臨床指向といってよく、応用編といえるだろう。Managementという言葉もTherapyでないところが意味深長で、臨床というものが必ずしも正確な診断や治癒に導くことができない場合にも、その馬をなんとか有用に用いるようにすることが含意されている。
第1章は跛行の臨床診断と画像診断である。画像診断にはX線、超音波はもちろんであるが、核医学、CT、MRI、Thermography、内視鏡を含み、ここまでで270頁を割いている。第2章は大幅に増補された蹄病(生体力学と跛行の項が追加され、CT、MRI画像項が充実している)である。第3章:前肢の跛行疾病、第4章:後肢の跛行疾病、第5章:体軸骨格の跛行疾病、第6章:DOD、第7章:関節炎、第8章:軟部組織、第9章:治療学、第10章:運動競技馬の跛行となっており、文献と索引をいれると1400頁に及ぶ大著である。この本もアダムス本と同様に、臨床場面の疑問に該当する部分をめっくっては読むという使い方はもちろんであるが、第1章の跛行診断と第2章の蹄の部分はぜひともその始めの頁から全部を読破したい。臨床家の経験とは何か、新しい画像診断の発展で開けた地平とは何か、そして私の臨床家としての診療行為の基本や考え方をどう向けて行くべきかを考えさせられる。画像診断万能の時代であっても、臨床家の触診や観察をないがしろにしては正しい診断が得られないことにも警鐘を鳴らしている。第1版では跛行の動画(CD-ROM)が添付されていたが、第2版ではウエブサイトにアクセスすることで一般的跛行についてのナレーション入りの47編の動画をみることができる。
「獣医畜産新報」2011年3月号 掲載
『Equine Ophthalmology 2nd ed.』
2011年・Elsevier発行・¥33,660(税込)
獣医臨床の場において、眼科疾患の割合は決して多いとは言えないが、無視できないことも事実である。しかし、眼科の診療には特別な機器が必要であり、またそれらが高価であるというイメージを持たれて、積極的な眼科診療を行っていない臨床獣医師は多いと思われる。本書は、まず第1章で眼科検査法が書かれている。その中には基本的な眼科検査法に始まり、細隙灯顕微鏡検査や眼底検査、さらには網膜電図検査、CT検査などについても書かれている。これらの検査は、特殊な機器が必要であったり、熟練した技術が必要であったりと、実際の診療現場では難しいことも多くある。
しかしこれでは、今までのように眼科診療を諦めてしまう。ここまではほとんどの眼科の成書と同様であるのだが、本書にはその後に特徴がある。確かに非常に高価な診断機器や治療機器、特殊な診断機器が必要である場合もあるが、眼科診療の全てにそれらが必要なわけではない。第2章では「Practical General Field Ophthalmology」と題して、特殊な眼科診断機器がなくても実際の診療現場で実施可能な眼科検査法や管理の仕方などが書かれている。また、巻末には眼科の専門用語の解説が書かれており、眼科用語に馴染みの薄い獣医師にとってはありがたい。さらに各部位の疾患では、眼の症例写真は全てカラー写真でありとても見やすい。このように本書は、これから眼科診療を始めてみようという獣医師にとって、非常に有益な本である。
しかし、本書はすでに眼科診療を専門的または積極的に行っている獣医師にとっても有用である。第3章以降は、眼の各部位について、それぞれの解剖、生理から始まり、各疾患の病態、治療法、予後、さらに手術手技については模式図もありそれら詳しく解説されている。とくに、回帰性ぶどう膜炎(equine recurrent uveitis:ERU)については、独立した章が設けられており、その病因、病態生理、治療法が最新の情報を基に詳しく書かれている。私自身が動物の視覚について研究させていただいているため、個人的に最も興味深かったのは、馬の視覚についての章、そして盲目となった馬の管理についての章である。馬の視機能については、人や犬・猫と異なることは他の眼科の成書にもある程度書かれていることであるが、本書は非常に詳しく解説してあり、とても勉強になった。
現在のところ、わが国では馬の眼科診療を行っている獣医師は非常に少ない。本書は、いわゆる眼科初級者にも、上級者にも、さらには研究者にとっても役立つ本であり、本書をご活用いただき、馬の眼科に興味を持つ獣医師が増えることを期待したい。
「獣医畜産新報」2011年2月号 掲載
『Behavior of Exotic Pets』
2010年・Wiley-Blackwell発行・¥17,050(税込)
近年のペットブームによって、犬・猫の飼育家庭の数の増加はもちろん、これまで動物園などで見ることが楽しみであった動物が次第に家庭の中で飼育されるケースが増えてきている。エキゾチックアニマルと呼ばれるこれらの動物種は、最も広く飼育されているハムスターやカメなどから、珍しいオウムやトカゲなど、多様化しつつある。これら動物種は家畜化の過程を経ていないことから、野性味にあふれ、観察する者たちを強く惹きつけている。しかし、エキゾチックアニマルに関する生理学的、行動学的知見が少ないこと、またそれに輪をかけて、獣医診療や行動治療、さらには飼養管理法についての知識が非常に乏しいのが現状である。
そのような時代背景に即して、本書は作成されたと思われる。エキゾチックアニマルの行動学、特にその問題行動や異常行動と生理学的なメカニズム、さらには薬物治療や、適切な飼育、動物倫理的側面に関して網羅的に言及したはじめての書と言えよう。
本書の扉を開くと、まずその扱っている動物種の多さに圧倒される。鳥類から爬虫類、小型の哺乳類など、近年ペットとして飼育が増加している動物17種が含まれている。特に今回の書が、獣医師あるいは訓練士などの家庭動物を主に診ている人に向けてまとめられていることから、動物園動物などは含まれていない点も特徴的である。各章が、これらの動物種ごとに、その専門獣医が執筆していることからも、行動上の問題の把握からその対象法までが記載された専門性の高い書となっている。
各動物種について、まずはその動物の示す繁殖、養育、社会コミュニケーションなどの正常な行動が記載されている。これらを踏まえた上で、動物の行動上のニーズに対応するための飼養管理法が紹介されている。さまざまな動物にとって、適切な飼養管理を施すことで生態学的な行動特性が保証され、問題行動の発現率が軽減されることから、非常に重要な点といえる。また、飼育管理上、問題行動として飼い主から相談を受ける事項とそれに対する対処法に関しても取りまとめられており、一般の飼い主はもちろん、臨床現場における有用性も高い。
著者のValarie V. Tynes博士はテキサス州で獣医診療、特に問題行動の治療に従事してきた。大学卒業後はUC Davisの行動治療科にて専門的な問題行動の治療に携わり、その経験を積み重ねてきたようである。今回の著書の冒頭にUC DavisのJ. Hart先生からの寄せ書きが掲載されているが、これは彼女の恩師にあたることに由来するだろう。また行動治療のみならず、彼女自身が一般診療経験をもっていることから、生理学的な知見が要所に含まれており、これらの点も獣医師としてはありがたい。今後、多様化する臨床獣医場面において、非常に重宝する1冊になること間違いなし、お勧めである。
「獣医畜産新報」2011年2月号 掲載
『Diagnosis Radiology and Ultrasonography of the Dog and Cat 5th ed.』
2011年・Elsevier発行・¥28,710(税込)
現在、小動物臨床の現場で用いられている画像検査としてX線検査、超音波検査、X線CT検査およびMRI検査があげられる。近年、多くの動物病院がX線CTを導入し、また我が国の獣医大学が次々にMRIを導入し、これらの高度画像検査機器が広く臨床の現場で活用されている。結果、X線検査や超音波検査では判読が困難、あるいは判読ができなかった事柄がX線CTやMRI検査を実施することで、評価が可能となり画像診断の有用性が広く認識され、画像診断に興味を持っている私としても非常に喜ばしいことだと思っている。しかしながら、その一方で危惧していることもある。それはX線検査や超音波検査を行わずに、あるいはきちんと読影せずに直ぐにX線CTやMRI検査を実施するなどX線や超音波などを用いた検査がおざなりになっている傾向があることである。言うまでもなく画像診断の基本はX線そして超音波検査である。先ず、これらの検査を行い、その上でより精査な情報が必要な場合、あるいはこれらの検査が不得手である頭蓋内、鼻腔内や脊髄内などの情報が必要な場合にX線CTやMRIといった断層撮像検査を行うという順序を忘れてはならない。本書を手にとって内容を熟読して欲しい。ごく、日常的に遭遇する多くの疾患が単純X線、造影X線そして超音波検査によって十分に診断が可能であり、そしてどのような疾患であればX線CTあるいはMRI検査が良いのか?さらに放射性物質を用いたシンチグラフィー画像で何を見るのかについてもシンプルにかつ実用的に示している。また各種画像検査の原理や基本的な手技などについても非常にわかりやすく解説している。本著は画像診断学を学ぶ学生にとっては教科書として、そして日々の診療に係わっている小動物臨床医にとってはX線や超音波検査の有用性を再認識することができる1冊である。
「獣医畜産新報」2011年1月号 掲載
『Note on Small Animal Dermatology』
2010年・Wiley-Blackwell発行・¥14,410(税込)
本書を手にして、大学を卒業しクリニックに勤務した25年前を思い出した。臨床の現場では覚えておかなければならないことがあまりにも多く、必須事項を書き込んだ手帳をポケットに忍ばせ、ことあるごとに書き込みや書き直しをしていた。この手帳はいつしか1冊のノートになっていたが、持ち歩くにはひどく痛んでいた。この度出版された『Note on Small Animal Dermatology』はまさにこれに相当する一品である。これはWilley-Blackwellによって企画された小動物診療に必要な診断治療知見を概説したノート・シリーズのひとつである。すでに内科、循環器疾患、ウサギ診療、猫診療が上梓されており、これに次いで皮膚病が出版された。
その内容は臨床家に優しく、基本的な皮膚科診療ツール、主徴からのアプローチ、病態からのアプローチ、発疹分布からのアプローチ、そして皮膚科の治療が色による付箋で整理され、さらに巻末には病歴カルテ、診察カルテ、飼い主様にお渡しする除去食試験のレター、薬物情報に関するアドバイス、グルココルチコイドを安全に使用するガイドまで添付されている。しかも品の良いカラー写真がほどよく配置され、診断アプローチの理解を助けるアルゴリズムまで用意されている。これぞまさにポケットに忍ばせたかったノートである。
本書のタイトルで使用されているsmall animal dermatologyは、獣医皮膚科聖書(成書ではなく)と呼ばれているかの有名なテキストと同一であり、これを情報源とした臨床家向けの書であることがうかがい知れる。その出来映えには眼を見張るも、恥かしながら著者のお名前を存じていなかった。さっそくウエブで検索した。著者は英国、エディンバラの下に位置するノーサンバーランドにあるCroft Veterinary Hospitalの皮膚科主任であった。この病院は24時間、365日救急診療を行う地域拠点病院であり、ここで28年の皮膚科経験をもって日々の診療に当たる中心的スタッフであった。なるほど、本書が臨床家の、臨床家による、臨床家のため皮膚科ノートであることに納得させられた。忙しい臨床家をサポートするノートとしてはもちろんのこと、新人臨床家や学生の皮膚科研修ガイドとしてもきわめて魅力的な1冊である。
「獣医畜産新報」2011年1月号 掲載
『Feline Emergency & Critical Care Medicne』
2010年・Wiley-Blackwell発行・¥19,800(税込)
猫に特化した救急医療の本はこれまでなかったが、やはり獣医学の進歩と共に、猫専門の本ができるようになったのだろう。この本を読むと、すべての器官系の疾患における猫の特殊性が各章の最初の囲みに箇条書きで書かれており、救急医療を一通りマスターした獣医師がその部分だけ拾い読みしても十分に学べる本であることがわかった。
さらに、重症の猫へのアプローチ法、心肺脳蘇生(CPCR)、ショック、創傷、重症患者への麻酔、重症患者の疼痛管理、輸液療法、重症患者の栄養サポート、呼吸器系エマージェンシー、心臓系エマージェンシー、血栓症といった通常の救急医療の教科書に掲載されている記述に加え、消化器系、尿路系、神経系、血液系のエマージェンシー、中毒、さらには内分泌系、電解質異常、眼科、皮膚科疾患にまで、とくに救急ではないものにも記述が及ぶ。
結局の所この本は、エマージェンシーを切り口にした猫の内科学の総合教科書であり、箇条書きのコンパクトな記述法により、簡単に読めるハンドブック的なものとなっている。様々なテクニックや病気の説明にはカラー図版が豊富に使用されている。また、いくつかの章には、薬用量の表も掲載されている。
編者のDrobatzはペンシルバニア大学獣医大学の救急医療の教授であり、Costelloはペンシルバニアの救急医療専門動物病院のスペシャリストである。著者は米英の大学の専門家、専門病院のスタッフなど40名を超える。救急医療のためには全部読んで身につけておくべきであろうが、それでも全体を通読して、どこに何が書いてあるかを把握しておけば、急に必要になった時に参照できる貴重な教科書と思われる。
「獣医畜産新報」2011年1月号 掲載
『Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion Small Animal Emergency and Critical Care』
2010年・Wiley-Blackwell発行・¥18,260(税込)
Dr. E.M.Mazzaferroの編集による『Clinical Companion Small Animal Emergency and Critical Care』を手にした。これは最近、盛んに出版されている5-Minuete Veterinary Consultシリーズの1つである。
本書は114章から構成され、1つの章で1つの疾患・病態が解説されている。通常、テキストのタイトルに“Emergency and Critical Care”の文字が並んでいると、我々は無意識のうちに「重症動物の管理法に関する教科書」を連想するのではなかろうか? 確かに緊急処置やICU管理が必要な疾患も扱われているが、これだけでなく実に様々な疾患・病態が扱われている。具体的には、アセトアミノフェン、チョコレート、殺鼠剤などの中毒、代表的な不整脈や酸塩基電解質障害、ショック、各種感染症など我々が日常診療の中でたびたび遭遇または疑診する疾患・病態が内科・外科を問わずびっしりと配列されているのである。
各章(つまり各疾患・病態)の解説は非常に簡潔で明快である。随所でカラー写真が挿入されており、シンプルな記載を補助している。例えば「ナトリウムの異常(26章)」は、定義、病因・病態生理、シグナルメント・病歴、臨床的特徴、原因鑑別、診断法、治療法、コメントにわけて低ナトリウム血症および高ナトリウム血症が5頁で解説されている。ナトリウムの代謝異常の解説としては、決して充実しているとは言えないが、このことは本書の編集方針が「5分間で相談できる(理解できる)」ことに徹している証拠でもあろう。すなわち、診断や治療方針に迷った時などに、本書は我々の迅速で良き相談相手(まさに5-Minuete Veterinary Consult)になってくれるであろう。同時に、本書の頁を全て括ってみて、「小動物臨床家である以上、どのような場合であっても本書の内容は忘れてはならない」と本書は我々に囁いているようにも思えるのである。換言すると、本書はいわゆるCommon Practiceの内容やレベルを我々に具体的に提案していると思える。実際の症例と対峙していなくても、日頃から本書を身近において通読しながら、必要な箇所はより詳しく解説された専門書を参照することで、様々な分野の知識が整理されるだけでなく、診療の幅やレベルが向上することは間違いないであろう。
「獣医畜産新報」2010年12月号 掲載
『Small Animal Pediatrics -The First 12 Months of Life-』
2011年・Elsevier発行・¥19,360(税込)
子犬と子猫に関する小児科学の新刊が出版された。比較的コンパクトなボリュームの中に臨床の現場に携わる獣医師にとって重要な項目のすべてを収めつつ、それらをきわめて把握しやすいように分類していることが本書の特徴である。
母子の看護や管理、各種の感染症、そして主要な器官系についての新しい知見に基づいた解説だけにとどまらず、エマージェンシー、X線検査および超音波検査、そして麻酔ならびに鎮痛治療などの項目を設けているところがいかにも新しい編集の意図をうかがわせる。
本書は大きく4つのセクションに分類されており、第1章の一般的考慮事項から始まり、第2章が幼若な子犬および子猫で一般的な感染症、第3章が診断と治療のためのアプローチ、そして第4章の診断と治療のための系統的な臨床アプローチへと続く。
第3章と第4章は表題が似ているが、前者では、子犬および子猫におけるX線撮影時の考慮事項、超音波検査法、麻酔法、外科的な考慮事項、骨折の治療管理、疼痛の評価と管理、薬理学的考慮事項、中毒、診断検査施設の有効活用法、臨床化学検査、そして剖検法を解説している。後者は心血管系、血液リンパ系、呼吸器系、歯牙および口腔、消化器系、肝胆道および膵外分泌、尿路系、生殖器系、神経系、皮膚および耳、筋骨格系、眼科、栄養学的アプローチ、そして人動物共通感染症を網羅している。
このように分類された項目が、第1章の第1項の母犬および母猫に対するケアから始まり、全46の項目へと順序良く解説されていく。各項目が具体的に挙げられているので、いま何についての情報を得るためにどこを開けばよいのかが一目瞭然であり、目にとまりやすく色分けされたページや本文中のサブタイトルもうれしい配慮の1つである。
また、獣医学英語を勉強中の方にとっては、臨床で出会う様々な分野の単語や表現が1冊の本の中に出てくるので、本書の各項目を読破することにより、大変効率よく獣医学用語の勉強を進めることができると思う。
さて、骨成長板の閉鎖時期を調べるときはどの本だったか? 子犬、子猫のALPは月齢でどのくらい変化するのだったか?etc. さっと本書を開くことができるように、現場の書庫の最前列に置くこととしよう。
「獣医畜産新報」2010年11月号 掲載
『Saunders Solutions in Veterinary Practice,Small Animal Neurology』
2010年・Elsevier発行・¥13,970(税込)
本書は臨床家向けに神経病学を分かりやすく解説した本である。そのため、神経疾患動物に対する病歴の取り方や神経学的検査の項は基本的なこととなり、目新しいことはほとんどない。しかし、「神経病の診断は、病歴、身体検査や神経学的検査を中心にした臨床診断が大きなウエイトを占めることから、MRIのような高価な画像診断装置を買うかわりにこの本を買ってください」という著者の言葉にあるように、本当に大事なことは基本的なことである。
さて、各論に入ると大項目で「意識レベルの変化」「行動の変化」「発作」「脳神経機能」「歩様」などなど、これらがさらに小項目に分かれ、それぞれ症例の紹介、臨床検査所見、治療法、予後、疾患の解説となっている。読み進むうちに著者の教育講演を聞いているように感じられる。また時代を反映して、きれいなMRI写真も豊富に使ってあるのでかなり楽しく読むことができる。
個人的に興味深かったのは、キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルの頚部の異常感覚(うちの病院では以前から「キャバリアのカイカイ病」と言っていて、おそらく脊髄空洞症に関連した掻痒症と考えている)に痛みを伴う症例が紹介されている。動物の自覚症状は獣医師にとって確認不可能であるものの、異常感覚であれば中には痛みを感じる症例がいてもいいか、と妙に納得してしまった。
獣医師は神経疾患が疑われる動物に対して「神経系に病変が存在するか?」「病変部位はどこか?」「どのような性質の病変か?」という3点を検討し、暫定的に診断していくものである。本書は、これらのことを丁寧に解説して暫定診断に至る考え方を身に付けるように書かれている。したがって、初心者にも中級者にも役に立つ本である。
「獣医畜産新報」2010年10月号 掲載
『Handbook of Small Animal Radiology and Ultrasound-Techniques and Differential Diagnoses-2nd ed.』
2010年・Elsevier発行・¥16,390(税込)
近年、様々な画像診断法が身近になり、とかくX線CTやMRIといった画像診断法が注目されている現状にある。しかしながら、大雑把ではあるものの全体像を容易に把握できるX線診断法、断層によってより詳細に病変部の構造を把握できる超音波診断法が、画像診断法の基本になっていることは言うまでもない。これら画像検査法によって鑑別診断や治療方針を絞り、そこからさらにその他の画像診断法が必要となるのかを決定する必要がある。また、X線CTやMRIをこれから撮影する動物についても、X線所見や超音波所見を判断し、造影検査を付け加えたり、撮影法を変更したりして、より情報量が多く得られるように撮影を工夫する必要がある。したがって、X線CTやMRIが日頃使用できる獣医師にとってもX線診断や超音波診断は非常に重要である。
本書は、X線診断法と超音波診断法に限定された画像診断書である。12のチャプター(1.骨一般、2.関節、3.付属骨格、4.頭頚部、5.脊椎、6.下部呼吸器、7.心臓、8.胸部、9.腹部、10.消化器、11.尿路、12.軟部組織)からなり、各チャプターともに始まりには一般事項(撮影法、解剖、X線解剖、超音波での描出法等)が記載されている。これらの内容は、箇条書きで要点に絞られて記載されている他は、従来の画像診断書と何ら替わりが無い。本書が他の画像診断書と異なる特徴を有しているのはこの後で、X線画像や超音波画像の異常所見が大きな項目として挙がり、鑑別診断が列挙されている点である。ただそれだけの非常にシンプルな構成である。
画像診断書の多くは、疾患名(診断名)の項目があり、それに続いて各種画像診断法における異常所見が述べられている。この形式は、勉強する上で理解しやすいものと思われるが、診療の合間で診断に迷った際、チラッと確認するには非常に不便な作りである。診断名が不明だからこそ検査をしているわけで、異常所見から診断名がみつけられる本書の書式は非常に臨床に即している。また、どの様な検査法でも所見から1つまたは2つの疾患名に絞って診断を進めていくと、外れたときに混乱するといった経験は多いものと思われるが、鑑別診断リストを示してくれる本書のような形式の書籍は非常に心強い。
これらの記載は、英語であるものの、全て箇条書きであることがら、診療時のクイックリファレンスとして非常に役立つ1冊と思われる。また、これから画像診断を学ぶ学生にとっても、臨床に即した学習が可能な書籍と考えられる。仕事柄、様々な画像診断書に目を通す機会が多いが、「あっ、これいいな」と久しぶりに思えた1冊である。
「獣医畜産新報」2010年10月号 掲載
『Manual of Equine Reproduction 3rd ed.』
2011年・Elsevier発行・¥15,400(税込)
生産地で働いていると馬の臨床繁殖は離れられない課題なのだが、経験が乏しい若い獣医師にとっては難しい分野でもある。なにせ膨大な回数の直腸検査の必要にかられ、診断機器といっても超音波装置が使えるくらいで、それ以上というといきなりホルモン測定のナノグラム・ピコグラムの世界になってしまう。そして、結果は妊娠したか、しなかったかの二つに一つしかない。勉強しようにも、臨床的な観点から馬の繁殖について書かれた本はほとんどなかった。繁殖分野では扱う臓器は限られているが、特有の生理学を基礎とし、用語も独特で門外漢には取り付きにくい。楽しく読めて、必要なときには簡単に調べることができるハンドブックやマニュアルが望まれる理由だろう。
本書は馬の臨床繁殖学の「マニュアル」の第3版で、ペーパーバックとはいえA4判で325ページもある。特筆すべきは写真の多さで、超音波画像を除けばすべてカラーである。写真には人の姿がずいぶん写っていて診療の実際のようすがわかるし、手元を写した写真も多くて、処置や操作のやり方がよくわかる。図、表、グラフ、本文中の見出しもカラーでたいへん見やすいし、楽しく読める。
著者はテキサスA&M大学の獣医繁殖の専門医の先生達で、このマニュアルは学術的に正しい最新情報を基礎としながら、豊富な症例、実践経験から書かれている。各章の始めには「目的」と「学ぶ上での課題」が明示されているので、それを念頭において各章を読めばポイントが頭に入る仕組みになっている。
「雌馬の解剖構造」には直腸検査の方法が解剖体での写真を使って説明されている。「雌馬の繁殖器官の外科」、「雄馬の繁殖器官の外科」では外科の成書にもないカラー写真や図を使って手技が解説されている。「新生子馬の処置と管理」では新生児学的記載もある。サラブレッド以外の馬も対象になっているので、「精液採取と人工授精」「精液保存」「受精卵移殖」の章もある。他には「妊娠していない馬の生理学」、「雌馬の繁殖上の健康検査」、「臨床繁殖の経直腸超音波検査」、「子宮内膜炎」、「妊娠:生理学そして診断」、「妊娠喪失」、「妊娠馬の管理」、「難産と分娩後の疾患」などの全19章からなっている。生産地の獣医師をはじめ、馬の繁殖に関わる人にとって重宝する書だろう。
「獣医畜産新報」2010年9月号 掲載
『Veterinary Ocular Pathology -A Comparative Review-』
2010年・Elsevier発行・¥62,260(税込)
獣医眼科病理の本というと、果たして何人の人が購入するだろうか?と思わないでもないが、かく謂う私は出版前に予約をして出版直後に入手した。偶然にも書評の依頼を頂戴したが、書評を依頼されたから良いことを書くのではなく、この本の出版を心待ちにしていた者として本書をお勧めしたい。
獣医病理学に従事する方はもちろん、専門的・準専門的に獣医眼科臨床に従事する獣医師のみならず、眼科を取り扱う一般臨床獣医師においても、非常に有益な情報が本書には満載されている。本書の取り扱っている眼科病理の症例は犬猫が中心ではあるが、馬や牛の眼科病理についても記載があるので、臨床獣医師といっても小動物獣医師だけでなく大動物獣医師にとっても重宝されることと推察する。
本書の筆頭著者のDr. Richard R. Dubielzig(私は親しみを込めて「Dr. Dick」と呼んでいる。決してDubielzigが発音しにくいからではない…)はウィスコンシン大学の獣医病理医で、特に眼科病理に特化したComparative Ocular Pathology Laboratory of Wisconsin(COPLOW)のヘッドである。これまでに2万5千を超える獣医眼科の病理組織を診てきており、世界一の獣医眼科病理医といって差し支えないだろう。
私個人は獣医眼科を専門に診療する立場にあるため、症例の検体を病理検査の外部機関へ委託することがある。しかし獣医眼科病理(獣医病理の眼科)についての情報は少なく、獣医病理医も眼科はちょっと苦手…という方が多いように感じる。実際に、自分自身でDr. Dickらの研究データを探して標本の再評価を行わないといけないことは少なくない。本書を是非活用して頂いて、外部検査機関の病理診断の精度がさらに向上することを期待したい。
臨床家にとって本書が有益な理由は、臨床的な所見から病理所見、予後などの情報が掲載されていることである。私自身が数例しか経験がない疾患で、かつ獣医眼科の成書にも情報が少ない眼科疾患についても、本書にはその膨大なデータからの記載が多数みられるので非常に重宝する。また病理組織の写真だけでなく、摘出した検体のマクロ写真が多く、臨床的な外観や眼底の写真も非常に豊富である。これは臨床家にとってはありがたい。
目次はあっさりしているが、各章の冒頭に詳細な目次がついていること、正常な解剖についての記載もあり、各章の最後にある参考文献は疾患ごとにまとめられているなど、Dr. Dickの細やかな配慮が伺い知れる1冊である。
当然ながら、「これ1冊で全てを満たす」という本は存在しない。利用される各位の状況に合わせて他書も参考にし、なおかつ本書もご活用いただくと非常に有益となるであろう。
「獣医畜産新報」2010年9月号 掲載
『Saunders Solution in Veterinary Practice Small Animal Oncology』
2010年・Elsevier発行・¥14,190(税込)
本書は一言でいうと「症例から学ぶ腫瘍学」についての本である。腫瘍学の教科書の多くが、各臓器に発生する腫瘍ごとに論じられ、これまでのエビデンスを基にまとめられているのとは異なり、本書は鼻汁、流涎、嘔吐、血便、貧血といった症状を呈する患者において、どのような腫瘍性疾患が認められたかというケーススタディになっている。例えば、「第5章:The cancer patient with sneezing and/or nasal discharge(くしゃみや鼻汁を認める症例)」では3つの症例がとりあげられ、それぞれのシグナルメント、主訴、病歴、臨床検査所見、鑑別診断リスト、診断評価、検査所見、治療が順を追って述べられている。この流れは私たちが日常行っている診療手順や思考回路と同じであるために非常に判りやすい。エビデンスを重視して構成されている従来の教科書は、参考書としては非常に有用であり科学的でもあるが、初学者には病気の全体像がとらえにくいという欠点がある。しかし本書では具体的な症例の検査・診断といった一連の流れの中で、「theory refresher」という項では疾患の概要が簡潔にまとめてあり、病気の全体像がつかみやすくなっている。
また「clinical tip」という項では生検や画像診断などにおけるツボについて注意が喚起され、「nursing tip」の項で診断治療に際して発生しうる問題点やそれに対する対処・看護法などがメモされるなど、非常に臨床的なまとめ方になっている。先に例として挙げた「くしゃみや鼻水を認める症例」の項では鼻腔腫瘍、鼻鏡腫瘍が解説されているが、鼻鏡に発生した腫瘍に対する外科療法の術後経過や、外科以外の治療法、例えば光線力学療法(photo dynamic therapy:PDT)を行った例など豊富な写真とともに記載されている。
通読してみると、著者の1人が外科専門医であるためか、腫瘍内科専門医による教科書と比較して、外科治療の術式が詳細に述べられている点が印象的である。上顎に発生した口腔内メラノーマの症例についての記載では、術中の経過写真が複数掲載されていることで、「どこからアプローチして、どの程度剥離し、腫瘤の切除後の粘膜フラップはどのようになされているか」が判りやすくなっている。腫瘍外科を行う獣医師にとって非常に役立つのはもちろんのこと、実際にメスをにぎることはない筆者(内科担当医)にとっても「この腫瘍は外科的に切除可能かどうか?!」ということを考慮する上で非常に参考になるであろうと感じた。
さらに、本書が非常に臨床的であると感じたのは、「How to」について詳細に述べられているという点である。第1章では「How to obtain the perfect biopsy(完璧な生検を行うには)」と題され、生検法について写真で手順を追いながら解説されている。第3章の「Principles of cancer chemotherapy(化学療法の基本原則)」では抗癌剤の投与準備、静脈内留置針を入れる方法(注意点を含む)が8枚も!の写真で解説されている。「どうやって抗癌剤を投与するのか?」「どこに気をつければいいのか?」という化学療法初心者が感じる疑問(実は質問されることが多いのだが…)にも対応できるように構成されている。
ただし、本書は「あの病気何だっけ?」「この腫瘍について調べてみよう」という参考書としての利用にはあまり適していない。参考書的利用の場合は、臓器別・腫瘍の種類別に記載された従来の教科書が引きやすいであろう。本書は症例に即して記載されたコンパクトな実習書ととらえていただけたら、最も有効に利用できると考えている。その意味では腫瘍学の初学者~中級者におすすめの1冊であり、是非一読されたい。
「獣医畜産新報」2010年8月号 掲載
『Color Atlas of Veterinary Anatomy Vol.1 The Ruminants 2nd ed.』

本書はきわめて個性的な牛の解剖書である。第一に局所解剖書であること、第二に解剖体の局所の写真とその解剖図からなっていること、第三に外貌写真と解剖写真が符合するようになっていることである。これらは実際の動物体の体表の手触りや凸凹からその部位が解剖構造のどこに当たるのかを学び、解剖写真とその図によって体表と体内構造の関係を理解することを目的にしている。すなわち実際の動物に向かって行う五感による臨床検査のことを意識的に取り入れた解剖書である。もともとは学ぶべきことが膨大に膨らみ、実習時間もままならない学生側と常に解剖体を準備できない先生側の双方を助けるために考え出された方法でもあるという。
解剖学を学んだだけでは、多くの学生が牛の膝蓋骨がどこにあるのかを実際の牛で指さしたり、触診したりできないことは皆さんも経験があるでしょう。私自身、この本の第1版を見たときは衝撃的であったことを覚えている。
現在、第1版が手元にないので、解剖写真や解剖図に新しく付け加えられたところがどこなのか定かではないが、骨のX線解剖の章が終末に追加されている。しかしこの章のX線写真の画質は悪く、あまり役立つものにはなっていない。もうひとつ難をいえば、たとえば肢の腱の走行などに関して二次元の解剖写真では三次元的に連続したり、交差する構造がわかりにくいことである。また局所・局所でわかってもそれが全体的にどう繋がって関連しているのかは他の解剖書をみなければならない(局所解剖書だから当たり前だが)。解剖写真の筋肉や臓器のほとんどが赤茶色なので判別しがたい部分もある。
とはいっても革命的な牛の解剖書であることはまちいがいなく、装丁もソフトカバーになり使い勝手もよくなっている。BSE問題で牛の解剖をみることができなくなった学生と臨床獣医師、体表と解剖構造の関係を今ひとつイメージできない学生と臨床獣医師、手術や損傷部位をもう一度確認するために、罹患部位を調べ直さなければならない学生と臨床獣医師にはうってつけの本だといえる。なお牛の写真はすべてジャージー種が使用されている。
「獣医畜産新報」2010年6月号 掲載
『Human-Animal Medicine Clinical Approaches to Zoonoses, Toxicants, and Other Shared Health Risks』
2010年・Elsevier発行・¥13,200(税込)
私達の周囲には、家畜、ペット、野生動物などさまざまな動物が存在しており、これらの動物と人が密接に関わる現代社会では、それぞれが相互に影響を及ぼしあい、複雑な関係を構築している。また、世界各地では人口増加と温暖化に代表される環境破壊、食料不足、エネルギー不足が急速に進行し、深刻な問題となっている。さらに、ボーダーレスな人々の移動や物流の活発化に伴って、各地で高病原性鳥インフルエンザ、狂犬病、パンデミックインフルエンザなどの感染症が次々に発生し、わが国も対岸の火事とはいえない状態となっている。こういった状況から、「One World、One Health」という概念が近年欧米を中心に広く用いられるようになってきた。これは、「世界は切り離すことのできない緊密さで繋がっており、人、動物、環境を含めた健康の維持には1国だけでなく地球規模で対応する必要がある」という概念で、適正な人と動物の相互関係、適切なリスク管理、人獣共通感染症の統御、感染症以外の疾病制御には、これまでのように個々の専門分野が独自で対応するのではなく、医学と獣医学が連携して問題解決に当たる必要性が提唱されている。
本書では、動物が人へ及ぼす影響には、少なくとも3つの形態があると考えている。第1は、動物との接触による人獣共通感染症、動物アレルギーと咬傷、刺咬の危険性。第2は、ヒューマン・アニマルボンドといった心理社会学的効果が身体に及ぼす恩恵、第3は、環境中の化学物質や感染症など人への危害となるものに対する「歩哨」としての動物役割である。14章から構成されている本書では、人と動物にとって共通の問題である人獣共通感染症、化学物質による中毒およびその他の健康危害の問題を広い視点から取り上げており、医学・獣医学の両視点に立って記述している。各章では、人や動物の健康危害について、豊富な写真と図表を用い、具体的な事例を挙げて分かりやすく解説している。特に、感染症の写真の中には、海外のみで流行していたりすでに日本では見られなくなったものが多数掲載されていることから、不測の事態に遭遇した際の格好の資料となるであろう。本書は、One Healthの概念に基づいて記述されており、医学・獣医学両分野の臨床家や公衆衛生に携わる専門家が人と動物の健康を理解する上で必携の書といえよう。
「獣医畜産新報」2010年5月号 掲載
『Consultations in Feline Internal Medicine Vol.6』
2009年・Elsevier発行・¥27,830(税込)
このシリーズはほぼ3年毎に改訂版が出版され、Volume 6に達した。猫の内科学に関する最新の話題を、器官、系統別に書いた本である。しかもこのシリーズは、これまで翻訳出版されていない。これまでの猫の内科学に精通しているなら、この本1冊で知識の補充となるだろうが、この分野における新しい知識の集積はめざましく、猫専門の認定医制度もわが国ではないため、そのような人もなかなかいないだろう。
緒言にも書いてあるとおり、このシリーズは1冊で完結するものではなく、前々からの知識の積み重ねで学ぶようになっているため、この号だけを手にとっても、抜けている記述はたくさんある。これまでの知識で、まだあまり変わっていない内容は、これまでのバックナンバーで参照するように作られている。
それにしても、これだけ新しい知見が出てきたのかと驚くような内容が本書である。感染症分野では、膿胸のような基本的な病気の記述もあれば、インフルエンザウイルス、アスペルギルス症のような珍しいものも登場し、さらにレトロウイルス、FIPについてはアップデートもある。栄養学では、慢性下痢症や慢性腎臓病の食事療法、プロバイオティックス、救急医療と食事などの記載が新しい。消化器系では、機能試験、超音波診断、高分化型リンパ腫、炎症性肝疾患、新しい制吐剤など、興味をそそる内容にあふれている。内分泌系では、よくある質問への答え、甲状腺機能亢進症と腎臓病の関係、新しい長時間作用型インスリンの使い方、皮膚病ではインターフェロンの皮膚病に対する使い方、メチシリン耐性ブドウ球菌などが新しい。その他、心臓病、呼吸器病、泌尿器系、神経病、血液病、腫瘍学と、広範囲に猫の内科学に限った最新の記載がある。また、ポピュレーションメディスンという新しい分野にもかなりのページ数がさかれている。
昔から変わっていない項目についてある程度広い理解があり、最近の知見をかなり網羅したものが欲しければ、前号のVolume 5と本号のVolume 6を手元に置くとよい。それにより、最新の猫の内科学の恩恵を受けることができるだろう。
「獣医畜産新報」2010年3月号 掲載
『Practical Small Animal MRI』
2009年・Wiley-Blackwell発行・¥40,920(税込)
1978年、MRによる人体撮像が初めて成功し、1983年、日本で初めてMRI薬事が認可された。この様に医学領域におけるMRI検査の臨床応用は1980年代前半であり、およそ30年である。しかしながら、その間におけるMRI機器の性能向上はめざましく、様々な撮像法が開発され、形態診断ばかりではなく生理、機能診断にも臨床応用されている。
一方、獣医学において、MRIが臨床応用されるようになってからは、十数年が経過している。初期は獣医大学を中心に導入され、臨床例に用いられてきた。その頃、MRI診断に関する論文は、散見される程度であり、書籍の形態で出版されていたものはMRI断層像と解剖学的名称が記載されているMRI断層解剖アトラスのみであった。しかしながら、現在では、伴侶動物に対するMRI検査の有用性が認知されるとともに、社会的ニーズがあいまって、様々な民間病院にも導入される様になった。若干地域差はあるものの、近隣の検査センターを利用すれば、一般開業医においても容易に検査が行える現状にある。また、MRI診断に関する論文数も豊富となり、診断にともなって治療に関するものもかなり充実してきている。そのような中、MRI診断について初めてまとめられ、書籍の形態で出版されたものが本書である。
本書は、MRIの原理やアーティファクト、脳脊髄、骨関節、腹部、胸部、神経疾患以外の頭部といった内容で構成されている。退屈な原理やアーティファクトについての記載は必要最低限であり、ページの多くは他の画像診断に関する書籍と同様、MRIに即した解剖学や各種疾患のMRI診断に割かれている。従来は診療の合間、MR画像を前に解剖や各種疾患のMRI所見についてその場で知りたいと思っても、文献の検索や収集が必要であるため、容易に調べることができなかったが、本書があれば容易にその場で検索することが可能であると思われる。また、一般開業獣医師が多くの文献を入手することは、我々のような大学勤務の獣医師よりもさらに手間と時間を要する。以上から、本書は洋書であるものの、MRI診断に関わる獣医師のみではなく、一般開業獣医師にとってもクイックリファレンスの書として有用であると考えられる。
「獣医畜産新報」2009年9月号 掲載
『Handbook of Avian Medicine 2nd ed.』
2009年・Elsevier発行・¥23,100(税込)
ルリコンゴウの表紙でお馴染みの『Avian Medicine』(2000年初版)の第2版が、表紙の鳥種をスミレコンゴウに、書名を『Handbook of Avian Medicine 2nd ed.』と替えて刊行された。この書は、各章をその分野の専門家が分担執筆する共著書であるが、新版では新たに6名が編著者に加わった。
旧版は、順に解剖生理・栄養学的特徴、身体検査、臨床検査、画像診断、病鳥看護、インコ・オウム類、フィンチ・カナリア・マイナー類、タカ類、ツル類、ダチョウ類、水禽類、家禽類、オオハシ類、ハト類、海鳥類、動物園飼育鳥類、薬用量に関する17章の構成であったが、この度の改訂では最終章が削除、第1章として鳥類の発生進化に関する章が、さらに付録(主要鳥種の体重・血液学的・血清生化学的データ、オウム類の英名学名対照表)が追加された。今回の追加章の如き内容は、とりわけ即戦力を求めがちな開業医にとっては、臨床に直結しない興味に欠ける情報かもしれない。しかし、実際には、こうした知識こそが、鳥類の解剖生理学的特性、臨床手技の原理原則、病態などを理解、説明するために役立つのである。本書では、臨床に絡めた解説を所々にとり入れ、臨床家にも苦痛なく読めるよう配慮されている。各章には、2008年までの文献に基づいた新知見が補足され、重要な箇所には目印を付して、文字も太字になっている。図は150点から356点に増え、飼い主に対する説明や指導を行ううえで有用な図が多数追加されている。さらに、写真はすべてカラーを採用、これにより術式や病状は格段に理解しやすくなったと考える。なお、著者が替わった第3章(身体検査)と第17章(動物園飼育鳥類)は、内容が一新した。こうした改訂により、本書の総頁数は初版の411から478になったが、紙質を替え、図と文字を小さくすることで本の厚みは初版とほぼ変わらない仕上がりである。しかしながら、縮小による不便さはまったくなく、見出し、写真、表、囲み記事がすべてカラー化されたことで全体的にめりはりがつき、むしろ見読しやすくなったと感じる。鳥類医学は、1980年代後半にAAV(Association of Avian Veterinarians)が発足して以降、急速な進歩を遂げている。とくに外科学、栄養学、感染症(微生物学)、臨床検査の分野においてもたらされた成果は大きく、1990年代に入ると多数の成書が出版されるようになった。よく「どれが良いか」と訊かれるが、どれも一長一短、「これ1冊あれば」というものはない。本書にも海外との飼育事情や診療環境から生じる難点はあるが、今日の鳥類診療に必要な情報は概ね網羅されており、幅広い飼育種に対応できる参考書として備えておきたい1冊といえる。
「獣医畜産新報」2009年8月号 掲載
『Color Atlas of Veterinary Anatomy, Vol.3 , The Dog and Cat, 2nd ed』
2009年・Elsevier発行・¥24,090(税込)
評者は以前、この初版本の訳出を手がけたことがあった。訳出後、評者はこの本が、「実際に、時間をかけた緻密な犬の解剖を通して、今までにあまり例のない、わかりやすくて詳細なアトラスを完成させたもので、あたかも犬体の解剖室が本棚に収まり、読者は必要に応じて見たい部分をいつでも取り出して見ることができるたいへん有用な本だ」との感想を述べたことを昨日のことのように覚えている。今回、この初版本にひきつづき第2版(2nd ed.)を読む機会があったのでここにあらためて紹介する。この第2版もその基本的な構成は初版本とほぼ同じであるが、いくつかの点について変更が加えられている。例えばこの第2版の第1章は犬の体表および外貌について解説しているが、初版でこの章にあった体の各部位のX線画像や表層解剖図をここでは略してあり、それらは第2章以降、いわば各論である頭部、頸部、胸部、腹部、前肢、後肢、骨盤部そして猫と、体の各部位に振り分けて載せて、画像診断のための一助となるようその有用性をより高めているようである。また、その第2章以降各章のはじまりには、その部位の一般的な特徴あるいは特有な構造について概略的ならびに網羅的な解説をつけ、有益な情報がまとめられている。また初版本にはなかったが、第2章以降、必要に応じてCT断層画像が各部位の最後に挿入されており、断層画像診断の手助けとなるように工夫されている。このようにいくつかの点についてその体裁に変更が加えられているが、基本に流れるこの本のコンセプトは以前と同じ、犬の体の表層から深層にかけて連続的で緻密な解剖であり、これらの写真を目で追うことにより、まるで自分が実際に解剖をしているような経験が得られる、『本棚の中の解剖室である』ことには変わりないように思え、安心した。したがって、この本は単に犬と猫の体に興味を持つ人のためばかりではなく、小動物臨床の現場で日々犬や猫に向き合う臨床獣医師にとって是非1冊は手元に置いておきたい本であると思う。
「獣医畜産新報」2009年8月号 掲載
『Equine Breeding Management and Artificial Insemination 2nd ed.』
2008年・Elsevier発行・¥22,880(税込)
「いい、これはいい。」最初に手に取った時の素直な感想である。本書は2000年に出版された書籍の第2版であり、編者は現在馬の臨床繁殖の世界で最も精力的に活動している獣医師の1人、Samper博士である。第2版で変更が加えられた点としては、本のサイズが洋形B5判から洋形A4判へと一回り大きくなり、ページ数(336ページ)が初版よりも30ページほど増えた上に、文字サイズが一回りだけ小さくなったこと、すなわち大幅に情報量が増えたことである。それでいて格段に読みやすくなっている理由は、初版の写真や図表が全てモノクロであったのに対して本書では全編を通してフルカラーの図表や写真がふんだんに使用されているからである。特に、イラストの多くがカラー化に伴って新たに描き直されていて、非常に見やすい。また、近年繁殖学領域においても知見が増えてきたカラードップラーによる卵胞や黄体、胎子の画像や、蛍光色素で染色された精子の鏡検像なども今回追加されていて、カラー写真ならではの特徴が活かされている。
馬の繁殖や臨床繁殖に関する書籍はいくつかあるものの、なかでも本書は繁殖管理の現場において実用的な情報が満載されていて、繁殖成績を向上させるために必要な事項を網羅している。合計で27章から構成されていて(初版は全18章)、種雄馬の管理、交配前後における繁殖雌馬の管理、分娩管理、分娩後の雌馬の管理、新生子ケアのみならず、馬の獣医療において応用されつつある新しい補助生殖工学技術についても1章が割かれている。初版の最後の章「馬の生殖工学の将来」において、『10年以内にクローン馬誕生の可能性もある。』との記載があるが、実際、それからほどなくしてクローン馬が誕生し、以来現在まで欧米における馬の体外受精や補助生殖獣医療の発展は目ざましいものがある。今版においても体細胞クローン馬作成技術について詳細な解説がなされている。
Samper博士とは2年前の学会で同じテーブルでランチを取ったことがある。その際、私がかかえていた患者(牝馬)の繁殖障害の症例について質問をしたのだが、真剣に耳を傾けて状況を聞いてくれたことが今でも思い出され、博士のプロフェッショナルとしての意識の高さが強く印象に残っている。そんな著者のプロ意識を本書からも感じ取ることができる。
本書は臨床獣医師や馬の繁殖に携わっている関係者のみならず、馬の臨床繁殖学を学ぼうとする獣医学徒にとっても有用な参考書として推薦したい1冊である。
「獣医畜産新報」2009年4月号 掲載
『Equine Anesthesia Mnitoring and Emergency Therapy 2nd ed.』
2009年・Elsevier発行・¥22,550(税込)
本書は馬の麻酔学全般を体系的に記したテキストブックの第2版である。初版は1991年に発行されており、17年ぶりの改定である。新しい内容には疼痛管理、麻酔補助薬による麻酔導入・維持・覚醒の改善、ロバとラバの麻酔などが追加されている。
疼痛管理に関する章は、薬物の説明を中心とした章と周術期の疼痛評価と治療を中心とした章の2つに分けられている。また巻末には疼痛管理計画シートが付いており、疼痛評価と治療の実際的使用の参考になるだろう。
完全静脈麻酔(TIVA)および吸入麻酔時の麻酔補助薬の章では、TIVAのための薬物コンビネーションが麻酔時間別に記され、propofolを用いたTIVAについても記載されている。また吸入麻酔薬量を減らすための静脈内投与薬とその方法と効果についてもよく説明されている。個人的に驚いたのは局所麻酔の章で、硬膜外麻酔のための薬物(とコンビネーションおよび容量)が20種類以上示され、効果発現、無痛時間、副作用がみごとな表で示されていることである。吸入麻酔薬の章では旧版に載っていなかったsevofluraneやdesfluraneについても記載されているのはもちろんである。
このような17年間の進歩の記述は麻酔リスクの最も高い動物種である馬の麻酔ストレスを実際的に軽減することになるだろう。また馬の麻酔は馬医療を概括する物語ともなっている。つまり痛みの克服、すなわち麻酔法の進歩が医学の歴史のうえで最も劇的な発見であったことが、馬においてもそうなのである。
本全体も少し大判となり、図表と文章の配置は旧版より見やすくすっきりしている。馬の麻酔学の専門書というだけでなく、生理学(とくに循環器と呼吸器)、薬理学・薬物学、臨床外科学の理解を深めるテキストとしても十分に堪能できる。
「獣医畜産新報」2009年4月号 掲載
『Atlas of Dental Radiography in Dogs and Cats』
2009年・Elsevier発行・¥21,670(税込)
口腔疾患を診断、治療、予後判定および経過観察する際に口腔内検査は重要である。その中で口腔内X線検査は避けて通れない最も重要な検査といっても過言ではない。歯の萌出障害、交換異常、発育障害の評価、歯の損傷における評価、歯周病における歯周組織の評価、歯内疾患における歯髄腔や根管および根尖周囲の評価、抜歯する際の歯根形態、骨性癒着(アンキローシス)、嚢胞、吸収病巣などの有無やその程度、矯正前後の歯根や歯槽骨の状態の評価、ならびに口腔内腫瘍の浸潤の評価など、ほとんどの口腔疾患において必要不可欠な検査である。実際、口腔内X線写真では、歯槽骨の吸収の状態を確認することが多いが、得られたX線写真では、通常生じている骨破壊の30~40%はX線写真には表れないといわれているので、その点を踏まえてX線写真を読影することが重要と思われる。
口腔内という非常に狭い部位を撮影するために、口腔内X線撮影は、経験を積まないと撮影することが困難であることは経験するところである。しかし、撮影法には一定の法則があり、下顎臼歯部以外は、2等分面法という特殊な撮影法を習得することにより誰でも撮影できる。撮影できてもX線写真を読影できなければ診断や治療に結びつかないことは当然であるが、その点、本書ではこれから口腔疾患を勉強し始めようとする方でも理解しやすいように構成されている。すなわち、本書は4つの章から構成され、1章は序章、第2章はX線解剖(犬の口腔X線解剖、猫の口腔X線解剖、顎関節)、第3章はX線検査における各疾患のエビデンス(歯周疾患、歯内疾患、吸収病巣、腫脹と腫瘍、歯の発育障害、外傷、その他の疾患)、第4章は歯科X線検査法と歯科用X線撮影装置について解説されている。
本書は、すべての画像が鮮明で、挿入写真が大きく、美しい。また画像の解説に留まらず、その疾患の診断、治療法、さらには予後判定や術後の管理法、注意事項まで述べられている。口腔内X線写真の読影に慣れていない方では、とくに第2章のX線解剖から読み始めると理解しやすいと思われる。頭蓋、歯、歯周組織のどの部位が、どこにどのようにX線写真で写って見えるかを豊富な写真を用いて丁寧に解説されている。第3章では、各疾患ごとに豊富に症例が提示されているので、ほとんど重要な口腔内疾患は網羅されていると思われる。第4章では、犬・猫別々に各歯の撮影法が詳細に図説されている。すなわち、各々の頭蓋骨を用いた口外法による撮影法、ならびに口内法による上顎切歯、上顎犬歯、上顎前臼歯、上顎後臼歯、下顎切歯、下顎犬歯、下顎前臼歯、下顎前臼歯および下顎後臼歯に対する撮影法について分かりやすく解説されている。また撮影に失敗した場合、失敗した画像を分析して、その失敗の原因と解決法まで述べられている。
近年、徐々にではあるが、このような獣医歯科関係の専門的良書が我が国にも紹介されてきているので喜ばしい限りである。
「獣医畜産新報」2009年2月号 掲載
『Saunders Solutions in Veterinary Practice: Small Animal Dermatology 』
2008年・Elsevier発行・¥13,970(税込)
Saunders(Elsevierグループ)の新企画である獣医臨床に関するシリーズ本が刊行される運びとなり、Fred Nind先生が編集主幹を担当されている。その1冊として最初に上梓されたのが、小動物獣医皮膚科の本書である。執筆者は獣医皮膚科専門医であるAnita Patel先生と同じくPeter Forsythe先生である。
本書の構成を俯瞰すると、最初に皮膚科診療での問診や身体検査の基礎と臨床検査の概説と以下の7項目を取り上げている。すなわち、痒を中心とする問題、落屑・痂皮、脱毛、潰瘍・糜爛、色素異常、結節・腫脹および各部位に関する問題である。それぞれの項目には、緒論の章があり、その後に症例に即して数章が記載され、本書の中心をなしている。これらの章では、主に病歴、臨床所見、鑑別診断、診断、予後、病理発生、疫学、治療、監視について統一されて記述されている。
本書は全体で57章から構成されており、末尾に付録として自己研修に役立つように5択の試験問題とその解答が掲載されている。そして、皮膚科で汎用される抗生物質の一覧、使用器具、皮疹別の疾患一覧、シャンプー療法および人獣共通感染症について纏められている。さらに理解を深められるように参考図書や文献が各章ごとに記載されている。また書物の活用に欠かせない索引も要領よく配置されている。
全体を通して要領よく記述されており、写真も多く適宜挿入されており理解に役立っている。そしてエキゾチック動物の例もあるが、主に犬と猫の頻度の高い、最近注目されている疾患、症例が取り上げられている。1例を挙げると、脱毛については病変が対称性のもの、病変が多発しているもの、全身症状を伴うもの(腫瘍随伴症候群)に分けて取り上げている。また、融解棘細胞の認められた皮膚糸状菌症の犬の症例、代謝性表皮壊死症の犬の症例、多発性紅斑の犬の症例など、最近日本でも報告の見られる問題に関しての解説も多い。
したがって、皮膚科臨床に興味を持つ人のみならず、小動物臨床に携わる多忙な先生方には是非手元に置いて参考にして頂きたい1冊である。
「獣医畜産新報」2008年11月号 掲載
『Manual of Exotic Pet Practice』
2009年・Elsevier発行・¥20,020(税込)
エキゾチックペットあるいはエキゾチックアニマルと称される動物の臨床について、幅広い動物種を対象としてまとめた書物である。
本書は全体を19の章に分け、初めの2つの章を総論とし、第1章はエキゾチックペットの歴史、第2章はエキゾチックペットの診療を始めるための準備について記載している。それ以降は、無脊椎動物と観賞魚、両生類にそれぞれ1つの章(第3章-第5章)を割りあて、爬虫類はワニ類、ヘビ類、トカゲ類、カメ類に分けて4章(第6章-第9章)とし、また、鳥類は1つの章(第10章)にまとめているが、哺乳類は有袋類、マウスとラット、フェレット、ウサギ、ハムスターとスナネズミ、ハリネズミ、モルモット、チンチラに各1章の計8章(第11章-第18章)を割いている。そして、最後の第19章は、エキゾチックペットというわけではないが、野生動物を扱っている。鳥類は1つの章であるのに対して、爬虫類は4つの章になっているなど、動物のグループによって割りあてている章の数に粗密があるが、飼育されている個体数や診療機会の多寡を考えれば、妥当な構成であると思う。
評者は、エキゾチックペットに関する獣医学書は、少なくとも哺乳類に関しては、将来的にはできる限り動物種ごとに、それが難しければ科(family)または目(order)程度の分類のレベルで1冊にまとめるべきであると考えている。しかし、その一方、入門書としては、ここに紹介する書物のようにエキゾチックペットの全領域を俯瞰した書物も必要であろう。本書は、そのようなエキゾチックペットの全般を扱っている書物のなかで、ほぼ最高位に位置するものと思う。ただ、難をいえば、章によっては、昨今の書物としては写真の掲載数が少なく、そのため、動物そのもののイメージがつかみにくかったり、あるいは外科的処置の手技がわかりにくいかもしれない。
ところで、これは評者の個人的な好みであるのだが、本書は無脊椎動物にも比較的多くのページを割いているところが嬉しい。エキゾチックペットの診療がふつうに行われるようになったとはいえ、それでも無脊椎動物は、養蚕あるいは養蜂という産業のために飼育されているカイコやミツバチを除けば、獣医臨床の対象とはなりにくい ( 「なりえない」というべきか) のが現状である。しかし、ヨーロッパやアメリカ合衆国では近年、無脊椎動物が獣医学の対象になりつつあるらしい。無脊椎動物の診療は、意外とおもしろいように思う。近い将来、日本においても無脊椎動物の診療を得意とされる臨床家が現れることを期待している。
「獣医畜産新報」2008年10月号 掲載
『An Atlas of Interpretative Radiographic Anatomy of the Dog and Cat 2nd ed.』
2008年・Wiley-Blackwell発行・¥50,160(税込)
『An Atlas of Interpretative Radiographic Anatomy of the Dog and Cat』は2002年に初版が出版され、2003年にはインターズー社から神谷新司先生監訳による『犬と猫のX線解剖アトラス』として翻訳出版された。このたび原書の2版が出版されたので、評者の手元にある旧版翻訳書と見比べて本書の書評としたい。
本書は臨床家が日常のX線画像診断を進める際に手元に置き、症例のX線画像と本書の正常像とを対比させて、読影力を高めるのに最適な成書である。本書は基本的には旧版と同じX線画像および等倍でトレースした線画による模式図を対にレイアウトして、読影のポイントを解説している。X線画像をトレースした線は当該部の特徴をよく捉え、頭部などの陰影が複雑な箇所では複数枚の線画を使い分けて解説しているので理解しやすい。また臨床家が異常所見と見誤りやすいピットホール(落とし穴)の画像についての解説も実践的である。さらに撮影時の動物の体位と照射中心が附図として掲載されているので、臨床家がX線撮影する際に参考となる。本書で用いているX線画像は1975年から1995年の間に撮影されたフィルム・スクリーン系のアナログ写真である。最近のX線撮影ではデジタル化が進み、Computed Radiography(CR)やフラットパネルディテクター(FPD)による画像を見る機会が多くなった。本書のような精密なアナログ写真を見ると、デジタル写真より遙かに大きな画像情報量を持つことが改めて実感できる。
単純X線写真では、犬と猫の骨格系と軟部組織が系統立てて掲載されている。犬では犬種により体型が大きく異なることから特徴的な犬種の画像を紹介し、犬と猫の月齢別骨成長のX線画像を並べているのも興味深い。本書では、旧版で記述の少なかったX線画像を評価する場合の正常臓器の大きさや位置関係の計測法を事細かに線画を使って解説しており、異常所見を診断するに役立つ。旧版との大きな違いは造影X線写真が充実したことである。胆嚢造影、経静脈性尿路造影や逆行性膀胱二重造影、脊髄造影などでX線写真と模式図が大幅に増えた。一方心血管系の造影X線写真が掲載されていないのは片手落ちである。本書は651ページのアトラスでかなり重たい。これ以上の紙面増は実用性に問題があるのかもしれない。
超音波画像、X線CT画像、MR画像など、獣医画像診断は近年大きく飛躍した。これら画像診断に進む際の基本情報はX線診断から得る。X線診断のスキルアップに本書は最適な参考書となるだろう。
「獣医畜産新報」2008年9月号 掲載
『Saunders Solutions in Veterinary Practice - Small Animal Ophthalmology』
2008年・Elsevier発行・¥13,970(税込)
この本は小動物眼科、犬、猫およびウサギの眼科学が非常にわかりやすくまとめられている。
本全体の構成は眼瞼、角膜など解剖学的部位別に記述されているが、病気の臨床症状、ヒストリー、検査とその進め方のポイント、鑑別診断のポイント、治療および動物看護士へのアドバイスなどが詳しく述べられており理解しやすい。加えて鮮明な画像や手術手技のイラストなどが多数用いられており眼科初心者にも理解しやすいように工夫されている。各セクションの文頭には、飼い主様からの主訴となる「眼が赤い」、「痛い」、「眼が見えない」などのキーワードが載っており、眼科診療を行う上で非常に役立つと思う。またケーススタディも多数掲載されており、診療の合間や通勤時や就寝前などにこれだけを読んでいても凄く勉強になると考える。
この本は、一般臨床医にとっても、これから眼科の勉強を始めようと思っている獣医師にとっても、また眼科専門医にとってもお奨めできる1冊である。
「獣医畜産新報」2008年8月号 掲載
『Saunders Solutions in Veterinary Practice - Small Animal Dentistry』
2008年・Elsevier発行・¥13,970(税込)
通常の専門書では、「この疾患は、このような症状で、この検査や治療を行う」といった画一された内容で構成されていることが多いように思われる。しかし、口腔疾患においては、1つの疾患に罹患しているとは限らず、他の口腔疾患も併発することも少なくなく、咬合や咀嚼といった機能についても考慮しなければならない。したがって、臨床現場では、教科書通りに事が運ばず、口腔疾患の症例に諸検査や治療を行う際に混乱を招くことも少なくない。すなわち、現在診ている症例において何をどのように検査して、どのような結果であれば何を疑い、どのような診断をして、何を優先して、どのように治療していくか、予後はどうかなど分かりにくく複雑なものとなる場合がある。口腔疾患の中で、同じ疾患に罹患した場合においても、個体により歯周組織の状態、あるいは歯や口腔粘膜の損傷の程度などが異なり、他の口腔疾患も併発していることもあるため症例ごとに治療法が異なる場合があるからである。
その点、本書は臨床における実践書といえる。最初の章は、歯と歯周組織、ならびに咬合に関する解剖と生理が学べ、次の章では、口腔検査とそのデンタルレコードの書き方、ならびに口腔X線検査の方法が簡潔に解説されており、口腔疾患を最初に学ぶ獣医師にも大変理解しやすく構成されている。次いで、第3章からは応用編となり、主に歯周病、慢性歯肉口内炎、歯根吸収、不正咬合、根管および根尖病巣における項目で、それぞれ5~9症例紹介され、合計で35症例ほども症例紹介されている。その内容は、症例の紹介から始まり、その症例の既往症、無麻酔下での口腔検査、麻酔下での口腔検査、さらなる諸検査、口腔X線検査所見、プロブレムリスト、疾患の解説、治療法のオプション、本症例における治療法、術後のチェック、予後、ならびに考察の順に詳細に解説されており、臨床獣医師にとって同じ疾患でも症状が異なる実例や反対に異なる疾患であっても共通した症状を示す実例が豊富に掲載されている。そのため、この症例の場合であれば、このような検査を行ってこのように治療すればよいということが分かる構成になっている。いわば、本書は1例1例チェックすべき点が詳細に解説されているので適切に治療するための指南役を果たしているといえる。
また、付録としてホームケア(口腔衛生管理)、歯科器具・機材の解説、抗生物質と消炎剤、ならびに歯内治療についての情報を得ることもできる。さらに、著者が薦める専門書や文献も掲載されているためにさらに調べたい場合、非常に参考になる。ぜひ、臨床獣医師に推薦したい1冊である。
「獣医畜産新報」2008年8月号 掲載
『Handbook of Pig Medicine』
2007年・Elsevier発行・¥20,020(税込)
今、養豚現場が抱えている一番大きな問題は疾病対策である。その疾病対策を担っているのは獣医師である。PRRSやサーコウイルスの出現以降、豚病は複合感染が主流となり、適切な解決策を提示するためには、高度な技術、知識が要求されるようになってきている。近年専門的な養豚獣医師を望む声が高くなってきた背景には、こうした事情が反映されている。
しかし獣医学を教える教育現場である大学には、豚病学を講座として設置している大学は皆無に等しく、養豚獣医師を目指す獣医師は独学でその道を切り開くか、または海外に勉強の場を求めていくしか手立てがない。独学で勉強する場合にまずぶち当たる壁は、適切な教科書が見あたらないことである。本書は、これから養豚の世界に飛び込もうとしている若き獣医師にとっては、まさに“バイブル”的な教材になるだけの内容を備えているだけでなく、経験者にとっても十分参考になる内容となっている。
本書は著者が英国人ということもあり、第1章では聴診や触診など個々の豚に対する診療指針が細かく記述されている。現在の養豚獣医医療は群管理が主流となっているが、群を構成する個体の観察無くして、群診療は行えないことをこの本は教えてくれている。また病気の各論では、運動器、呼吸器、消化器、皮膚、神経系などの系統別に解説され、さらに本書に掲載されている図、表、写真は全てカラーで構成されており、そのため病気の症状、病理所見などが非常に理解しやすくなっている。
本書は現場で混迷する養豚獣医師に対し、適切なアドバイスを与えてくれるものと確信する。
「獣医畜産新報」2007年12月号 掲載
『Handbook of Zoonoses:Identification and Prevention』
2007年・Elsevier発行・¥10,780(税込)
本書はノースダコタ州立大学を退官した臨床獣医師J. L. Colvilleと同校の臨床微生物学者D. L. Berryhillによるzoonosisのコンパクトな解説書である。序文で述べられているように本書は健康管理に関わる学生や、医療・獣医療の従事者を主な対象としているが、それ以外の読者にも分かりやすいよう書かれている。2部構成の前半でzoonosisの基礎、後半で42の代表的疾患について、病原体、宿主、伝播様式、動物および人の症状、診断、治療、予防についてまとめている。各疾患の罹患率と致死率を4段階に分けて表示することで、各疾患の公衆衛生上の重要度が一目で分かるような工夫がされている。各疾患はアルファベット順で掲載されているが、第1部に病原体あるいは宿主動物に基づいた分類表を載せることで参照を容易にしている。また疾患によってはhistorical factあるいはhistorical noteとして、名称の由来やちょっとした逸話などが挿入されている。
Zoonosisは疾患数で200を超え、病原体は900種近くに上る。また、人に感染する病原体の約6割はzoonosisの病原体である。したがって、どのような視点でzoonosisを捉えるかによって、扱う対象は大きく異なる。本書はすでに述べたような層を読者として想定していることから日常の獣医療で遭遇する可能性の高いものが主に選ばれているが、一方で、稀な疾患であっても一般の関心の高い疾患についても取り上げている。60の図表が使われているが、視覚的にやや劣るところが惜しまれる。原版がカラーであるにも拘わらず白黒である点も残念である。
記述はできるだけ正確であるように心がけたとしているが、一部疑問の残るところもある。例えばSalmonellaの表記が最近の知見とあっていない点や、Salmonella typhimuriumをパラチフスの病原体のように記述していたり、狂犬病の記載で、人を咬んだ犬の取り扱いに疑問のある部分があったりする。また、インフルエンザに関してもH5N1亜型に偏った扱いになっている点も気に掛かるところである。節足動物媒介性感染症の予防に関する記載が、多くの疾患で重複していることも改善すべき点に思われる。
巻末のAppendixはいずれも理解を助ける上で役に立つと思われる。
類書が多く出版されている中で、本書が特に優れているとも言い難いが、zoonosisの入門書として、あるいは臨床現場における参考図書としてはそれなりに役立つものと思われる。
「獣医畜産新報」2007年10月号 掲載
『Color Atlas of Veterinary Pathology 2nd ed.』
2007年・Elsevier発行・¥27,170(税込)
獣医病理学を学ぶ上での大切なことは何よりもまず目で見ることてある。病気、病変が非常に多くあることは言うまでもないが、それぞれが多くの臓器、器官に発生し、さらにその進行度合の差によって、すなわち初期像、最盛期、終末像とそれぞれ異なり、これらの組合せで膨大な数の肉眼所見になることは明らかである。
それらの全てを実際の経験、自らの知識として貯えることは希むべくもない。これらを補うものとしてのカラーアトラスがある。
この『Color Atlas of Veterinary Pathology』は獣医学を学ぶ学生、研究所で獣医学的な仕事に従事する卒業生、食肉検査に従事する人を対象に作られたもので、初版は1982年に刊行された。
初版にはそれまでの20年間に獣医病理学の知識が急激に増大し、獣医学を学ぶ学生に大きな負担となっていると述べられているが、当時から現在に至るまでも、さらに事実、知識が多く集積されていることから、この第2版には旧版には見られなかった事柄を増補することでより現状に即したものとなっている。
初版では、とくに「病気と病気の進行過程の理解」を目的とし、細胞病理学、炎症、循環障害、腫瘍を各臓器、組織ごとに明確にしているが、この第2版では、その内容をさらに進め「臓器、組織の一般的な形態的反応」というように拡張して、自由度をもって考えられるようにしている。
また、このアトラスでは学生諸君が取り付きやすいように、各臓器、器官ごとに一般的な導入部を設けてあるのも親切な点である。
また先に述べたように、新しい材料が加えられ、多くの写真が拡大されているのも利用者にとって参考にしやすいことであろう。
病変の取り上げられている動物も馬、牛、羊、山羊、犬、猫、ウサギと多種に亘り、このようなアトラスで従来ありがちであった大動物に片寄ることなく、日常多く出会う動物、特に小動物臨床で多く出会う犬、猫の例が多く、鮮明な写真で見られることは学生、研究者ばかりでなく一般の臨床家にとっても役立つところが大きいと考えられる。
獣医師の実際の業務においては死後の検査もしばしば要求されることから、病理学の専門家以外であっても肉眼的病変をその場で見分けるための知識も必要となる。そうした知識を広く養うためにも、本書は有用で、獣医業に従事する者は、是非書架に1冊備えておきたいアトラスである。
「獣医畜産新報」2007年4月号 掲載
『Current Therapy in Equine Reproduction』
2007年・Elsevier発行・¥28,050(税込)
この10数年、馬の繁殖管理に関する幾つかの著書が刊行され、様々な新知見を目の当たりにできるようになってきた。それらの中でも、ここで取り上げる『Current Therapy in Equine Reproduction 』(2007, Saunders)は61名の著者によって書かれたもので、馬の繁殖管理に関わる66話題が豊富な新知見をベースに載せられている。
本書の特徴の1つは著者の多くが実際にフィールドで日夜馬の繁殖管理を含む診療に携わっている獣医師であることだ。また、若手の大学教員や学生、大学院生とおぼしきメンバーが執筆しているのには、さらに驚かされるとともに、この分野の研究の拡がりに深い感銘を受ける。
内容は、開業の獣医師や、学生、さらには馬の繁殖管理者をターゲットにして、馬の繁殖に関する管理の全てが実にバランスよく網羅されている。繁殖障害の診断、あるいはその外科的処置も含めた治療法についても言及している。馬の内分泌動態の研究成果が披瀝されていることや、豊富なエコー像はこれから馬の繁殖学を学ぶ学生や、フィールドでの繁殖管理の理解に欠かせないものとなっている。
本書は全部で8章に分かれている。第1章には雌馬の卵巣動態と子宮の変化、発情や排卵の同期化処置、加えて発情の抑制法などについて書かれている。第2章には雌馬の繁殖障害に関わる問題に焦点をあわせて、卵巣、卵管、子宮、外陰部の病的な状態について記述され、内分泌的、細胞遺伝学的、外科的処置が網羅されている。第3章と4章には種雄馬の正常な生殖器の構造と機能、その検査法、障害について書かれているとともに、第5章では受胎率の向上に欠かせない精液の採取、採精液の評価について記述されている。そして、第6章には胚移植を含む最新の生殖補助療法について紹介され、第7章では妊娠に伴う諸問題が、第8章では分娩後の繁殖管理のポイントがよく述べられている。このように本書は高い生産性が求められている馬の繁殖管理に利する優れた指導書となっている。
ただ残念なのは、著者の中に日本人研究者・獣医師の名前を発見できなかったことだ。わが国には西川義正先生を筆頭に、馬の繁殖管理や指導に長けた多くの獣医学関係者による研究成果を基に、今日の日本の馬産が支えられてきた。しかし、西川義正先生は別格として、それらの成果はまだ国際的な評価を得るに至っていないかもしれない。是非とも、大いに海外の研究を凌駕するような独創的で、優れた研究の進展が望まれているところであり、今日その芽は大いにあると思っている。青雲の志をもって、日本発『馬の増産』の発刊に期待するところである。
なお、Wisconsin-Madison大学のGinther,O.J.教授が、『Reproductive Biology of the Mare』の第3版を近々出版の予定と聞く。本書の刊行とあわせて、馬の生殖科学および繁殖管理に関わる新知見が続々と現われることは、馬生産に携わる獣医学関係者にとって真に喜ばしいことだ。
「獣医畜産新報」2007年3月号 掲載
『Veterinary Herbal Medicine』
2007年・Elsevier発行・¥22,880(税込)
洋の東西を問わず、古くから植物を治療に使用し、その効果についての記載が集積されてきた。中国においては数千年の経験に基づき後漢時代にまとめられた神農本草綱目が古典として有名である。我が国においても、中国からの影響を享受しつつ我が国の医学として発展をとげ、漢方医学として今日に至っている。江戸時代には、我が国独自の本草綱目が出版されている。獣医療においても医療に追従して進歩してきたことは周知の事実である。このような伝統的な医学が、近代科学を基盤とした医学における問題を解決するために最近特に注目されるようになっている。
獣医東洋医学会もこのような時代の趨勢にあって創設され、この分野の発展に努力している。また2005年にアジア伝統獣医学会が設立され、2006年10月北京で第1回大会が開催されている。西洋にあっても薬草の歴史は古く、その研究も盛んであり、獣医領域における関心も年々高まっている。
今般、Wynn, S.G.とFougere, B.J.の両先生が編纂された『Veterinary Herbal Medicine』がMosby 社から出版された。現在、この関連各分野で活躍中の20名に及ぶ執筆者による約700頁の大著である。
本書は5章から構成されており、第1章は緒論で、歴史を踏まえた薬草医学の概説である。第2章は薬草の治療における位置付けを明らかにする必要性やその手続きについて紹介している。第3章では、薬草として使用される植物についての解説で、薬学的背景を主体に論述されている。第4章は臨床における有用性を中心とした項目である。臨床の実際面と馬や牛での治療上の問題が記述されている。また、200頁以上を割いて各薬草それぞれの特性を記載している。最後の第5章は付録で、用語解説など実用上役立つ5項目について示されている。
したがって、本書はこの分野を志す後学にとって必見の書物であり、初心者は勿論のこと経験を積んだ臨床獣医師や研究者にとっても極めて利用価値の高い好著であると思われる。
「獣医畜産新報」2007年2月号 掲載
『Canine Internal Medicine Secrets』

面白い本が出版された。臨床でよく遭遇する諸問題の重要なポイントについて、神経および神経筋肉、心臓、呼吸器、内分泌、消化器、泌尿器、生殖器、多発性/全身性の問題、血液リンパ系、感染性疾患の10カテゴリーに分け、Q&Aの形式で解説してある。我々が日頃接するセミナーでも、熱心な講師は受講者から質問されることをとても喜ぶ。真剣に耳を傾けてくれている証拠だからである。しっかり理解しようとすれば、誰でも知識の浅い部分がおのずから顔を出して出てくるものである。そこに気づくことができるからこそ、楽しく有意義な勉強なのである。また、“自分がわからないときは人も同じ! あなたの疑問は周囲の10人の疑問でもある!”とよく言われる。コンピュータがいうことを聞かないときに、マニュアル本を読み返すよりも、サポートページの“よくある質問”をチェックすることが役に立った経験があることでしょう? そんなことを考えつつ読み進めると意外に早く読破できる。実力試験のつもりで利用してみると面白い。本書の英文は簡潔明瞭であり、日ごろよく使われる表現満載である。そこで、臨床獣医学英語を勉強中のインターンにはダブルの利益が得られる格好の勉強材料であろう。“IBDとは何でしょう?”、“IBDの臨床徴候とは何ですか?”と後輩に聞かれたとき手短に何と答えるか。それとも本書を手渡すか? Seeing is believing! ぜひ、ご一読いただきたい。
「獣医畜産新報」2007年2月号 掲載
『The Dog Breeder's Guide to Successful Breeding and Health Management』
2006年・Elsevier発行・¥5,610(税込)
本書はアメリカの犬のブリーダーを対象として書かれたものである。著者のRoot Kustritz女史は犬の繁殖学の著名な学者であり、2001年に獣医師向けに出版された、現在この分野で最も定評を得ている“犬猫の獣医繁殖学”の著者の1人でもある。従来の犬のブリーダー向けの本はややもすると一部の分野に偏っていたり、素人向けの平易過ぎる内容であったりと1冊の内容としては不十分な本が多かった。その点本書は犬のブリーダーは勿論のこと、毎日の診療で犬の繁殖に従事することの少ない獣医師にも大変参考になる実践的かつ有益な情報が網羅されている。これらの内容の多くは“犬猫の獣医繁殖学”を簡略に書き直した観があるが、前著書と異なり全編に亘りカラー写真が豊富に使われており、読み飽かせないよう工夫されている。さらに、内容の理解度を確認するために小項目ごとに、ブリーダーから良く受ける質問コーナーや理解度診断コーナーが設けてある。
内容は大きく分けて4章から構成されている。すなわち、1章:栄養と基礎科学、2章:雌犬の臨床管理、3章:雄犬の臨床管理、4章:犬の繁殖に関する一般的管理である。1章と4章は犬のブリーダーを特に意識した内容であり、本の本来の趣旨に最も合致した部分である。2章と3章は雌雄犬の臨床管理とあるように、犬のブリーダーが実際に行う内容というよりは、臨床獣医師の診療内容を理解させ、獣医師に診療を依頼する時に必要な犬の徴候変化などを教示した内容になっている。したがって、これらの部分は臨床獣医師に大変参考になる内容であることは疑いない。若い獣医師からは、大学卒業以来犬の交配や分娩立ち会いの経験がほとんどないために、飼い主にどのような徴候が現れたら来院指示すればよいのか、確信が持てないとの意見を聞くことがある。この本はそのような獣医師に是非読んでもらいたい書である。
最近、我が国においても、犬の凍結精液人工授精で生まれた子犬を登録認定しようとする機運が高まりつつある。しかしながら、新しい理論に裏打ちされたホルモン測定による交配適期診断や子宮内に精液を送り込む人工授精技術の両方が伴わないと、犬の凍結精液による受胎はほとんど期待できない。そのような意味で犬の繁殖に長年携わってこられた獣医師にも推薦したい本である。
「獣医畜産新報」2006年7月号 掲載
『Handbook of Equine Anaesthesia』
2007年・Elsevier発行・¥13,640(税込)
臨床現場(病院とフィールド)での馬の鎮静法と麻酔法のガイドラインを記したコンパクトな最新のハンドブック(190ページ)である。最新であることの意味は、麻酔薬や麻酔薬に対する馬の反応に関する理解の著しい進歩、新しい麻酔薬、新しい技術、古い薬の新しい使用法などによってより安全でコントローラブルな馬の麻酔が可能になったことに起因する。しかし、この小さな本は最新であるばかりでなく、基本的な馬の麻酔手技を網羅した臨床マニュアルであり、「元来、安全な麻酔薬などはなく、安全な麻酔者だけがいる」ことを前提に、麻酔を安全に実行することをコンセプトとしている。したがって、鎮静法・無痛法・麻酔前処置法、静脈内麻酔法、吸入麻酔法とその薬物使用といった教科書型知識の羅列ではなく、麻酔モニター法と麻酔に付随して起こる問題についてもそれぞれ章を設けて写真と図とともに要領よく説明されている。さらに子馬、妊娠馬、帝王切開、整形外科、急性損傷、疝痛、眼科手術などの特別の場合の麻酔法についてその病態生理から麻酔覚醒までの麻酔手順がまとめられている。臨床現場のハンドブックとしての使用はもとより馬の鎮静・麻酔法全般を理解するためにも一読の価値がある。索引の項目は非常に使いやすく適切で、また本に付いている赤と白の2本の紐状のシオリはかわいらしく、便利である。馬の麻酔に関わる臨床家あるいは学生にとってポケットや卓上に常にあるべき本の1冊である。
「獣医畜産新報」2006年6月号 掲載
『Saunders Manual of Small Animal Practice 3rd ed.』
2006年・Elsevier発行・¥34,760(税込)
古来よく言われるように、書は読むべきものであって読まれないように注意しなくてはならない。同様に、手引書や指針の類についても当てはまるものと思われる。マニュアル通りなら間違いないとか、マニュアルの習得のみに終始することは論外である。マニュアルを忠実に実行することは、それなりに利点の多いことも事実である。すなわち、活用の仕方によるし、利用者の態度に左右される。強く打てば大きく響き、弱く叩けば小さく鳴るのは常識である。
本書の初版は1994年に上梓され、6年後に第2版、そしてさらに6年を経て、改訂第3版として発刊されたものである。米国オハイオ大学獣医教育病院の臨床を支えるStephen J. Birchard とRobert G. Sherdingの両先生による初版以来の編纂で、一貫した考えのもとに纏められており、獣医臨床の最前線で活躍中の約150名の執筆者による力作である。最近の獣医臨床の進歩を包摂して、現場の診療に適合した内容へと充実を図った佳書と言えよう。疼痛管理やワクチン接種指針の項目なども追加され、また挿入された多数の図表が理解の助けとなっている。
いずれにしても、多忙な臨床獣医師をはじめ、獣医師を志す学生にとっては、座右において知識の確認や習得に役立つ1冊であることはこれまでの経緯からしても窺い知られるところである。
「獣医畜産新報」2006年5月号 掲載