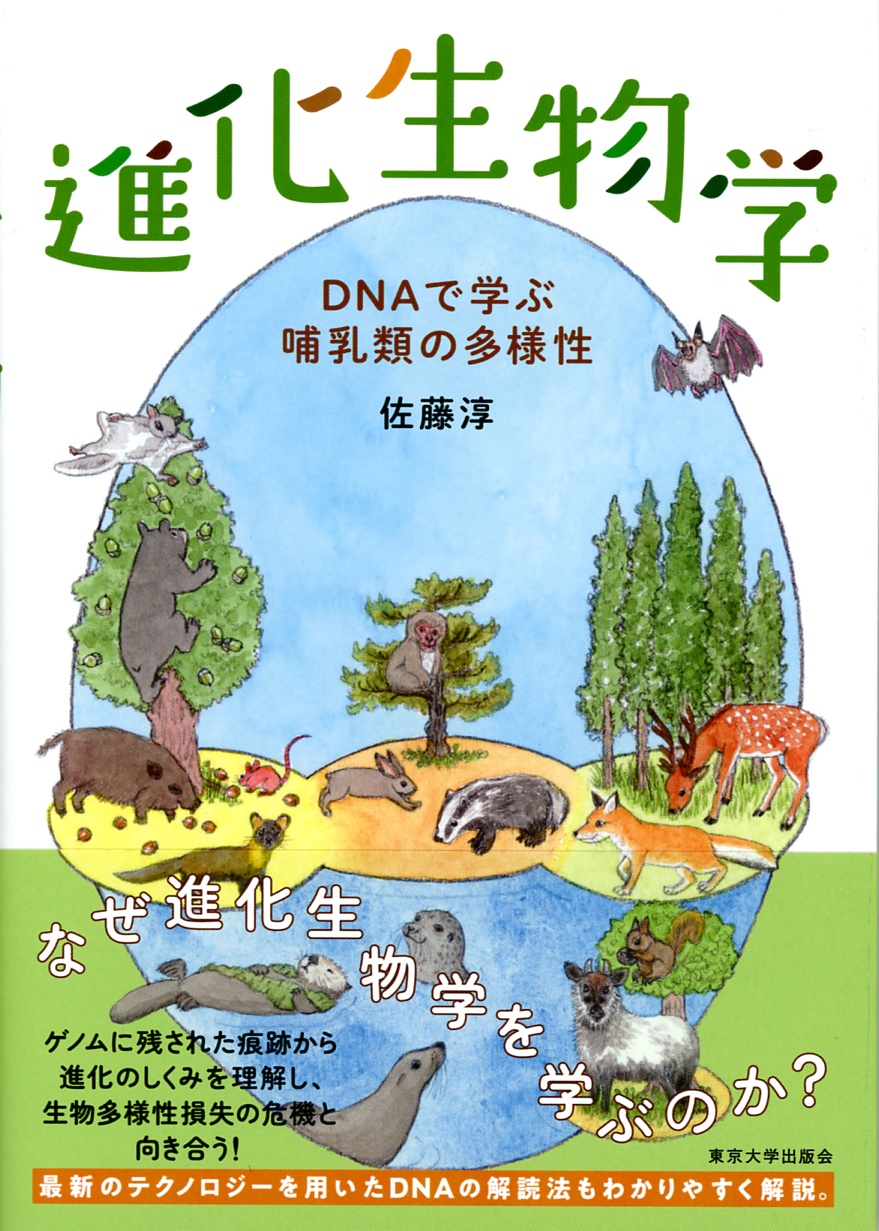HOME >> JVM NEWS 一覧 >> 個別記事
- 著者:佐藤 淳
- 発行:2024年7月10日、東京大学出版会
- 定価:3,080円(本体2,800円+税)
- 頁数:176頁
- 詳細:https://www.utp.or.jp/book/b10084325.html
- 評者 浅川満彦(酪農学園大学 獣医学類 医動物学ユニット)
本書は次の六つの章で構成される。
- 美しい島
- 日本列島と進化
- 進化の痕跡
- 退化の痕跡
- テクノロジーと進化
- なぜ進化生物学を学ぶのか
加えて、主題と副題から受ける印象から、本書籍が獣医療関連の媒体で紹介されるのは、不自然と感じられたのではないか。が、ワンヘルスについて提示された著者の考え(146~147頁)は、今後の獣医学が目指すべき方向の一つである。なお、このような考えを保全生態のセンスを有した屈指の進化学者が示された事実は、ワンヘルスが、時に、獣医関係者の独り相撲になっているような状況が払拭されたようで安堵もした。
したがって、安心してお読み頂きたいが、特に、エキゾチックのような多様な飼育種や感染症などで悩ましい野生種の哺乳類と本気で、つまり行き当たりばったり的ではなく理解しながら診療/疫学調査・研究に臨むのなら、前半の三つの章は明らかに有益である。もっとも、その端緒と本文内で随所に示される事例が、瀬戸内海の島々(芸予諸島)に生息するアカネズミの遺伝子解析結果に基づく生物地理であり、敬遠されてしまう危険性がある。たとえ、この野ネズミが日本固有種でユーラシア大陸の祖先型から約600万年前に分岐し、森林生態系を維持し、あるいは害虫捕食により農作物を守っていてもだ。幸い、私もこのネズミに強い関心があったので、最初からひきつけられたが、そうではない方々にはある種の関門となるかもしれない。所詮、「自分に関わるものしか関心がない」という著者の諦観(146頁)は、それを予感しているのだろう。
しかし、「なんだ、ネズミか」的理由で本書が見限られては、誰にとっても損失であり、何としても避けないとならない。そこで、まず、多くの獣医師あるいはそれを目指す学生さんたちに読んで頂くため、関連情報を織り込んだ少々長めの文章量となる(乞うご容赦)。次いで、先程、私はアカネズミに関心があると述べたが、正確にいうと、その体内に寄生する線虫、特に、牛捻転胃虫の仲間である毛様線虫類2種の地理的分布に注目している。これら両種は小腸管腔に住みつき、牛捻転胃虫のように鮮紅色を呈すが、吸血しているわけではなく、消化管内容物のおこぼれや腸内細菌を食べているようだ。外見も似ているが、サイズが異なり、体長数ミリを小型種、十数ミリを大型種としよう。その虫卵はアカネズミの糞便とともに排出、外界で幼虫が孵化し、土壌細菌などを食べ、2度脱皮した後、第3期幼虫(感染幼虫)となりアカネズミの餌に乗っかって経口的に感染する。このように成虫は内部寄生してはいても、幼虫の生存は外界の湿度や気温などにより影響を受け、極端な条件下では死滅する。また、アカネズミ個体数が減少すると、感染機会を失い、同じく死滅する。こういったことが続くとアカネズミの線虫は絶滅するはずで、実際、欧州の島にいるアカネズミの親戚筋に寄生する大型種の親戚筋では知られていた。同じようなことが日本の島でもあるだろうと追いかけ、確かに伊豆諸島や九州地方の島々では、確かに、絶滅したらしいことまではわかった。もし、この機序が明らかにされれば、自然環境に負荷を与えないで線虫をコントロールする手段に応用できよう。ご存知のように、イベルメクチンのような駆虫薬が生態系内では不可欠の土壌生物を殺滅し、あるいは、予防的に家畜に投与することによりこの薬物に抵抗性のある寄生線虫が出現しつつあるのはご存じの通り。しかし、研究は始まったばかりなので、データの蓄積が必要である。
それならば、アプローチしやすい瀬戸内海の島々ではどうだろうかとなり、本書(19頁)にある愛知学院大学と共同で調べた。その結果、存否の結果を得たが、規則性の解釈は漠然としたままであった。それら島々の地史やそこに分布するアカネズミの情報が欠如していたからである(以上、古瀬ら 2018)。
前置きがとても長くなったが、奇しくも、本書にはこの欠如情報が明示されていることがわかり興奮した。氷期における瀬戸内地方の古代河川(今はその河岸とともに海底)に隔離された丘陵(今は島)により隔離されたアカネズミたち。その遺伝子のハプロタイプによりクラスターに分けられるようだ(23頁)。さっそく、そこで示されたデンドログラムと分布地図に線虫の存否情報とあわせてみた。残念ながらクリアな説明ができうるものではなかったが、ここ何年か味わったことが無かったような興奮をし、本当に楽しかった… 。病原体の疫学情報は、たとえば、このような基盤が無いと、一歩も進まないのである。話が前後するが、このようにして、私は最終章“なぜ進化生物学を学ぶのか”を実感したのである。
そもそも、著者が芸予諸島のアカネズミに注目したのは、彼が勤務する大学に近く、その教育研究のためのフィールド開拓の一環であったようだ。そして、その成果はこちらの一家言「教育そのものを目的とすべきではない」(62頁)に集約されている。大学は研究を基盤に教育をする場であるので当然であるが、そのためには学生さんたちが教員(研究者)と同じ目線、目標を持つことが前提であり、その実現のためにも、芸予諸島のアカネズミは優れたモデルであったのだろう。そして、このモデルで得た経験値はアカネズミ以外の陸棲哺乳類(一部水棲)にも展開し、第2および3章につながるのである。とりわけ、41頁にある日本産種の分岐年代は病原体疫学研究で、また、61頁イヌ亜目と64頁有胎盤類の分子系統樹は臨床検査や診療などで情報が少ない種を扱う場合、参考になろう。
“退化の痕跡”の章は、打って変わって海獣における味覚を司る遺伝子が鰭脚類(およびペンギン類)で欠如している事例の解析である。ここでは恐竜を含む鳥類の丸呑みする生態と絡めてのストーリー展開である。私がほんの少し気になった点として、恐竜もまた多様性を示す動物であるが、それをあまり考慮していないと誤解される書きぶりであった。すなわち、「鳥類でTas1r2が失われている理由は祖先である恐竜の生き方にある」(90頁)である。約6500万年前の災難により生じた植生を鑑みると(大量に残された種子のみ)、今の鳥類のような消化器系を持った恐竜の一群のみが乗り越え、鳥類として生きながらえたとする説が流布されているようなので、ここは恐竜自体の生き方(生態)ではなく、生き残り方(結果)が適切な気がした。いずれにせよ、恐竜は人気のある動物なので、読者を逃さないためにも丁寧に書いて欲しい。
著者(「地方の私立大学に勤める」)の哲学は「初学者にわかりやすく解説すること」であると、本書“はじめに”で謳っている。それを具現化しているのが“テクノロジーと進化”であり、ここではDNA研究で用いた原理と歴史などが丁寧に説かれていた。多くの方はご存じのモノゴトであろうが、それを分かりやすく説明するとはどのようなことなのか、そもそも、わかるとはどのようなことなのかを体感できうる章であった。
そして、大団円“なぜ進化生物学を学ぶのか”になだれ込むが、その意義については、私も大賛成で、当方が行った些細な経験をもとに愚見を披瀝した。また、その章では日本のあまり明るくない未来についても言及されている。私は著者がフィールドとして頻繁に訪れた島々の人々と接するうちに醸成されたものと想像している。瀬戸内島民の悲哀と現実については、佐野(1997)の見事な筆致で感じ取っていたし、私自身も瀬戸内含め島めぐりで見知っていた。高齢化と過疎化はまさに日本の未来の縮図がこれら島々で展開していたのであろう。著者の幅広い見識と豊かな感受性、そして未来を見通す卓越した能力の表現型が最終章に結実していた。
引用文献