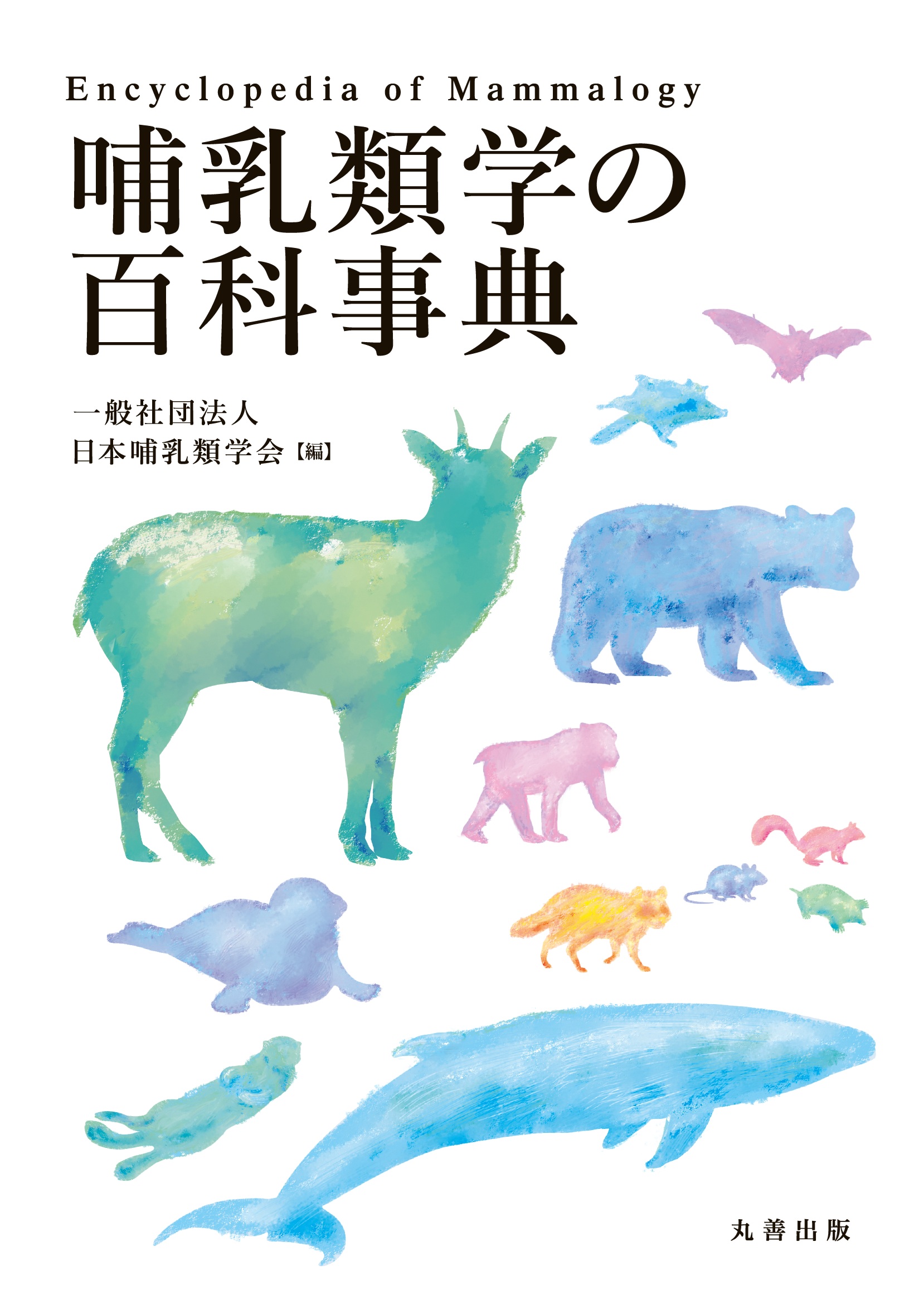HOME >> JVM NEWS 一覧 >> 個別記事
浅川満彦
酪農学園大学獣医学類/同・元野生動物医学センター
あるモノゴトを過不足なく、かつ意味を反映し体系的に記載・配列された書物が事典である。この点、規則ではあるが、意味性とは無関係に羅列した辞典と異なる〔辞典の例をあげると『新獣医学辞典』(新獣医学辞典編集委員会,2008,緑書房/チクサン出版社,1563pp.)〕。もし、これらを通読する事態になったとしたら、後者は受験勉強のような単語帳の記憶作業のような辛さを伴う。しかし、目当てのワードだけを調べる時にだけにこういった辞典(辞書)を頼るので苦痛は感じない。検索が日常となった今では、紙である必要性もだいぶ薄れつつある。一方、事典はある程度のストーリー性を楽しむことが可能なので、他書籍同様、紙派/電子書籍派に分かれそうだ。
さて、前置きが長くなったが、今般、哺乳類全般の事典である『哺乳類学の百科事典』(日本哺乳類学会 編)が丸善出版株式会社から刊行された。
各項目の構成は、「進化・系統分類」「多様性」「分布」「形態」「遺伝」「感覚・生理」「生態」「社会」「保全管理」「研究手法」「日本の哺乳類の現状と課題」となる。形態・生理など基礎獣医学に関わる事項は飼育動物以外に興味を持つ初学者に知的興奮を惹起することになろう。また、現在のコアカリ獣医学には野生動物学が含まれるので高学年となっても参考になる。ただ、用語に軽微の差異があるので注意したい(こちらの保全管理はコアカリでマネジメントor保護管理)。分担執筆者には、ほぼ全ての章に獣医大関係者(いずれも日本哺乳類学会員でもあるが)も含むので、所属するゼミ(研究室)を選択する際や卒業論文研究の進め方で、間違いなく参考になる。
紹介者である私の専門は寄生虫(病)学なので、広く病態獣医学が気になるところであった。ダイレクトに「哺乳類の病気」(感覚・生理の章)、「人獣共通感染症」(保全管理の章)、「(病理学の)死んだ野生動物の研究」(研究手法の章)」などとあるのは明確である。しかし、私が担当した「寄生」は生態の章で扱われ、比較的近接した概念である「食物網」「捕食・被食」「スカベンジング」「労働寄生」「多種共存」などに紛れていた。だが、寄生という現象がいかに進化してきたのかの究極要因の側面から履修生に理解してもらうには便利な並びになるだろう。なお、ムシ屋個人として注目したのが、「古代DNA」(遺伝の章)を分担した小金渕佳江氏であった。縄文人糞石で寄生虫DNAを探索、先史時代の感染症拡散と移住経路を明らかにしていた。また、同じ章には「内在性レトロウイルス」(水平伝播して哺乳類進化の原動力)や「マイクロバイオーム」(哺乳類の体表や腸内などに存在している微生物群集)などの項目も散見され、病原体の研究者は関心を持つはずだ。
過去に『生物の事典』(原勝敏・末光隆志 編,2010,朝倉書店,560pp.)、『動物の事典』(末光隆志ほか 編,2020,朝倉書店,772pp.)の2冊の事典の分担執筆を行った。そして本書分担執筆の打診を頂いた際、「おお、生物、動物、そしてついに哺乳類へジャンプか!なんと美しいラインナップ!!」と感激、即決快諾をし、初校ができるまでそのように思い込んでいた。しかし、先の2冊と本書はまったく別の出版社とは気が付かずに引き受けてしまい、まさに汗顔の至りであった。
『生物の事典』『動物の事典』の章構成は、「生物=生命とは何か」「生命の誕生と進化」「遺伝子」「形・構造・構成」「生息環境」「機能」「行動と生態」「社会」「人類/動物=分類」「進化」「遺伝と遺伝子」「細胞」「形と器官系」「生理」「発生」「脳・神経系」「ホルモンとホメオスタシス」「免疫」「生息環境」「行動と生態」「バイオテクノロジー」「動物の利用」「動物と文化」である。
そして『生物の事典』『動物の事典』『哺乳類学の百科事典』の3冊の同一項目を流し読みすると生物⇒動物⇒哺乳類の流れが見え、実に快感であった。
最後に、『新獣医学辞典』『生物の事典』『動物の事典』の3冊における私の分担項目を列挙しておく。
- 『新獣医学辞典』:「食性」「性的二型」「性淘汰」「動物地理」「ブラキストン線」「渡瀬線」
- 『生物の事典』:「動物の病気と診断」
- 『動物の事典』:「動物地理区」「個体群と密度効果」「寄生」
もし、誤りなどを見出されましたら、是非、ご一報を。